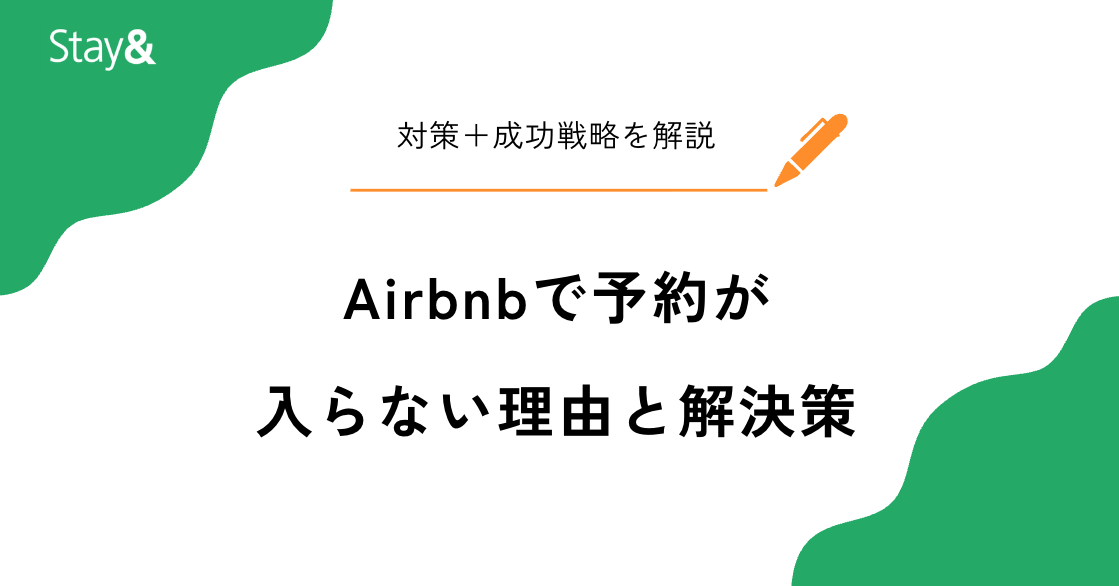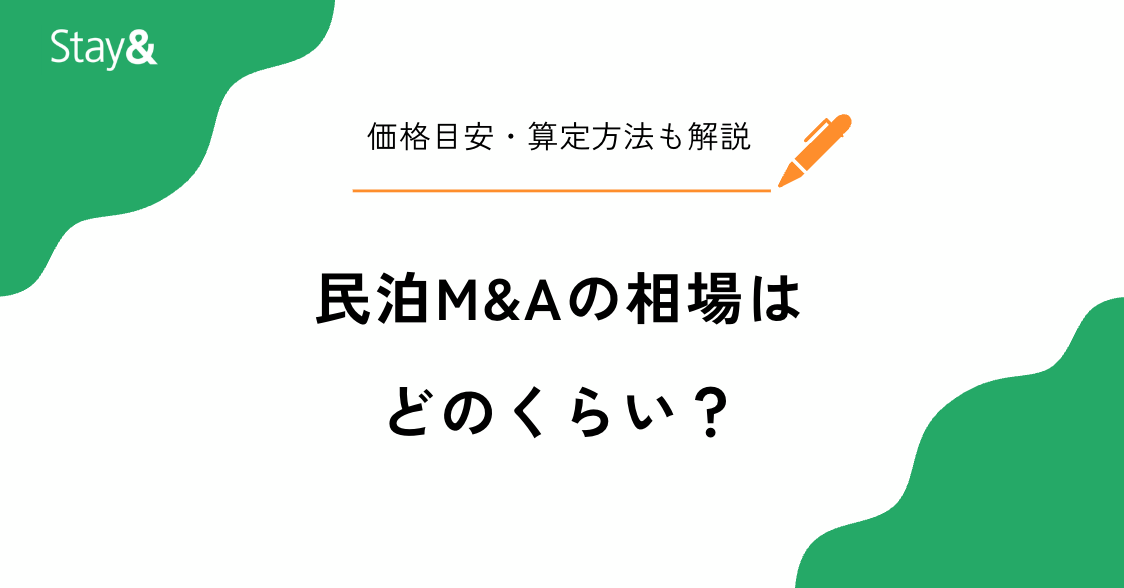古民家で民泊経営を成功させる方法【失敗しない始め方・注意点・補助金まで解説】
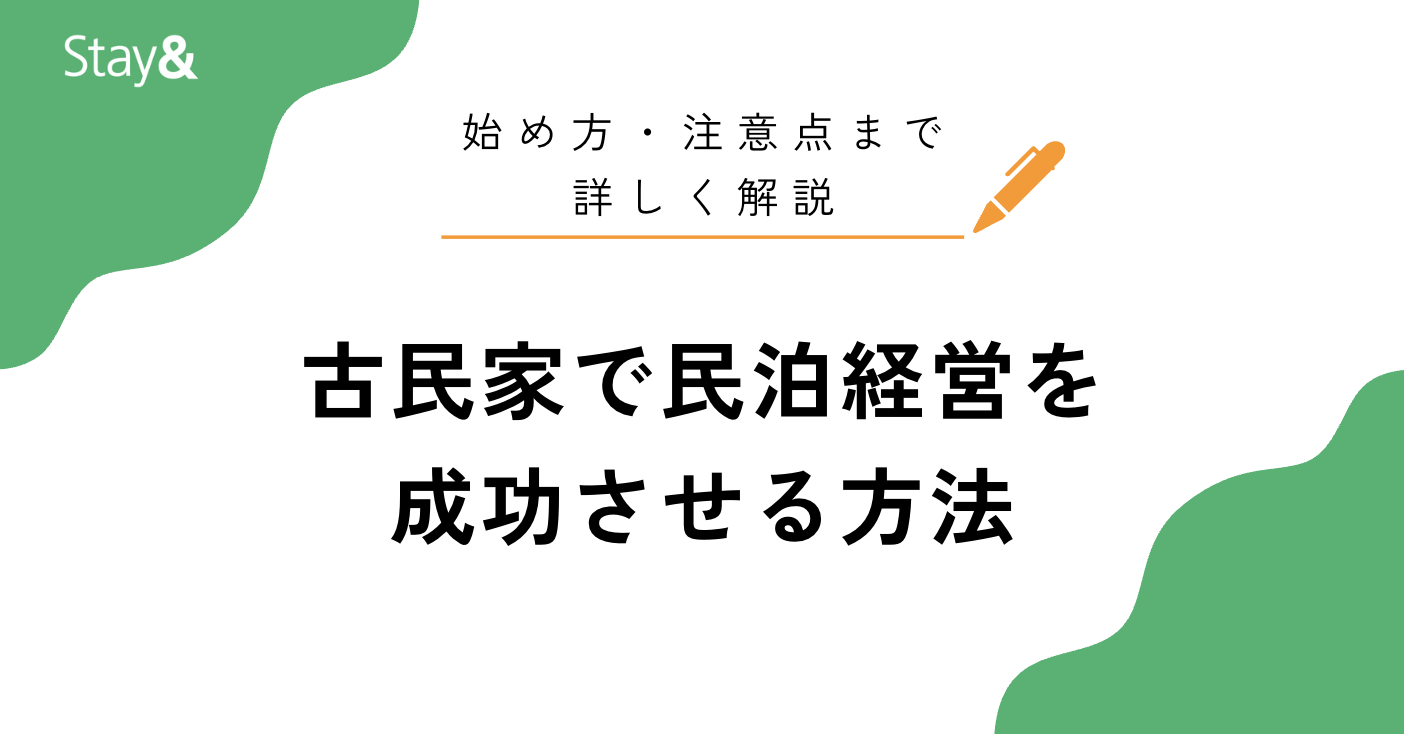
「古民家を活用して民泊を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない…」
そんな方に向けて、本記事では古民家民泊の始め方から注意点、補助金の活用方法までをわかりやすく解説します。
伝統的な日本家屋を活かした民泊ビジネスは、インバウンド需要の高まりや地方創生にもつながる注目のスタイルです。
しかし、古民家ならではの法的制約やリノベーションの課題もあるため、正しい知識と準備が成功のカギとなります。
この記事を読むことで、古民家民泊の魅力や現実的な運営ステップが具体的にイメージできるようになります。
目次
古民家で民泊を経営する5つのメリット
古民家を活用した民泊経営は、他の宿泊形態にはない独自のメリットが数多くあります。
- 伝統的な日本の暮らしを体験できる
- 一棟貸しによる高い収益性
- 地域への貢献や空き家の再生
といった社会的価値も見逃せません。
ここでは、古民家民泊の代表的な5つのメリットを紹介します。
日本の伝統的な雰囲気を味わえる
古民家民泊の最大の魅力は、日本の伝統的な暮らしや建築様式を体感できる点です。
畳のある和室、木の温もりが感じられる柱や梁、囲炉裏や土間など、昔ながらの日本家屋ならではの要素が、訪れるゲストに「本物の和の体験」を提供します。
特に海外からの旅行者には好評で、他のホテルや民泊との差別化ポイントにもなります。
一棟貸しで高い客単価が見込める
古民家は一棟まるごと貸し出すスタイルが主流であり、1泊あたりの客単価が高く設定しやすいのが特徴です。
複数人での宿泊や長期滞在にも対応できるため、1組あたりの売上が高くなりやすい点が経営上のメリットです。
また、プライベート空間を重視する現代の旅行ニーズにもマッチしています。
地域貢献や空き家活用になる
古民家民泊は、過疎化や空き家問題に悩む地方において、地域活性化の手段として注目されています。
使われなくなった古民家を再活用することで、地域に人の流れを生み出し、経済効果や雇用の創出にもつながります。
また、観光客との交流を通じて地域文化の発信にも寄与します。
差別化しやすくSNS映えする
古民家の独特な外観や内装は、他の民泊やホテルとは違う「映える空間」として注目されています。
特にInstagramなどSNS上での拡散力が高く、自然と宣伝効果を得られるのも大きな利点です。
囲炉裏のある居間や、障子越しの光といった写真映えするシーンが多く、口コミでの集客にもつながります。
比較的低資本で始められる場合もある
物件次第では、初期費用を抑えて始められることも古民家民泊の魅力です。
空き家バンクなどで格安の古民家が手に入ることもあり、自治体の補助金や助成制度を活用すれば、リノベーション費用の一部もカバーできます。
うまく条件が整えば、自己資金が少なくても開業可能です。
そもそも古民家民泊とは?

そもそも古民家民泊とは
古民家民泊とは、築50年以上の伝統的な日本家屋を活用し、旅行者に宿泊体験を提供するビジネスです。
主に「一棟貸し」のスタイルが多く、家族やグループでの滞在に人気があります。
現代的なホテルとは異なり、畳・木材・障子といった日本独自の建築様式を楽しめる点が特徴です。
運営には一定の許可や手続きが必要ですが、空き家の再利用としても注目されています。
なぜ今、古民家民泊が注目されているのか
観光客のニーズが「非日常」や「本物の日本文化」へと変化したことが、古民家民泊が注目される最大の理由です。
特に海外旅行者(インバウンド)にとって、古民家での滞在は“リアルな和体験”として高い評価を受けています。
また、地方では空き家が増加しており、古民家を民泊として活用することが、空き家問題の解決策としても期待されています。
SNS映えする空間としても人気が高まっています。
インバウンドや地方創生との関係性
古民家民泊は、訪日外国人向けの観光コンテンツとして高いポテンシャルを持っています。
囲炉裏体験や田舎の暮らしを提供することで、都市では味わえない体験価値を創出できます。
また、地方に観光客を呼び込むことにより、地域経済の活性化や雇用創出にもつながります。
国や自治体もこうした取り組みを後押ししており、補助金や支援制度が整いつつある点も魅力です。
古民家民泊の始め方・開業までの5ステップ

古民家民泊の始め方・開業までの
5ステップ
古民家で民泊を始めるには、物件選びから行政手続き、リノベーション、集客準備までを段階的に進めることが大切です。
以下では、初心者でも迷わず取り組めるように、古民家民泊の開業に必要な5つの基本ステップをわかりやすく解説します。
1. 古民家物件を探す(オンライン・オフライン)
最初のステップは、民泊に適した古民家物件を見つけることです。
オンラインでは「空き家バンク」や「古民家再生協会(古民家住まいる)」など専門サイトが便利です。
一方で、現地に足を運んで地域の不動産業者に相談したり、空き家を直接見て回ると、ネット未掲載の掘り出し物に出会えることもあります。
民泊向きの立地・構造かも事前にチェックしましょう。
また、他の方がすでに古民家で民泊をしていて、その結果、投げ売りされている物件もあります。
そうした物件なら、さらに安く始められる可能性があります。
投げ売りの物件の探し方については「民泊物件の投げ売りが急増中!売却理由・価格相場・買い方まで徹底解説」の記事をご覧ください。
2. 民泊制度の選定(新法・旅館業・特区)
民泊には「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「旅館業法」「国家戦略特区」の3種類の制度があり、どれを選ぶかで運営ルールが異なります。
新法では年間180日までの営業制限がある一方、旅館業や特区では365日運営可能です。
立地やビジネスモデルに合わせて、適切な制度を選ぶことが成功の鍵になります。
3. リノベーションと設備整備
古民家を民泊として使うには、一定の快適性と安全性を確保するためのリノベーションが必要です。
特に重要なのが水回り・耐震補強・断熱・害虫対策など。
また、キッチン・冷暖房・Wi-Fi・寝具といった基本設備の整備も欠かせません。
伝統的な雰囲気を残しつつ、現代の生活に適した機能性を加えることが大切です。
4. 行政への申請・届出(必要書類と注意点)
民泊運営には、管轄自治体への届出や許可申請が必要です。
具体的には、住宅宿泊事業届出書、図面、所有者の同意書、管理者情報などを提出します。
提出書類の内容や形式は自治体ごとに異なるため、事前に保健所や役所に確認しておくとスムーズです。
また、消防設備の設置基準なども満たす必要があります。
5. OTAやSNSでの集客をスタート
準備が整ったら、Airbnb・楽天トラベル・じゃらんなどのOTA(宿泊予約サイト)や、InstagramなどのSNSで集客を始めましょう。
古民家はビジュアルに魅力があるため、写真の質が集客に直結します。
プロに撮影を依頼するのも効果的です。
地域体験やコンセプトを打ち出すことで、リピーターや海外からの予約にもつながります。
なるべくコストを抑えて高品質な集客用写真を用意したい場合は一眼レフカメラのレンタルを活用するという選択肢もあります。
古民家物件の見つけ方|失敗しない物件選びのコツとは?

古民家物件の見つけ方
失敗しない物件選びのコツとは
古民家民泊を始める上で、最初にして最重要なのが「どの物件を選ぶか」です。
ここでは、オンライン・オフラインそれぞれの古民家探しの手段と、選定時のポイントを解説します。
オンラインで探す方法を活用する
インターネット上には、古民家に特化した物件サイトが複数存在します。
たとえば「古民家住まいる」「家いちば」「ふるさと情報館」などでは、空き家・古民家の情報を地域別に検索できます。
物件概要だけでなく、民泊向けかどうか、リフォーム歴の有無も確認できるサイトを選びましょう。
物件の探し方の詳しくは「民泊物件の探し方7選!見つからない時の対処法も紹介」の記事で詳しく紹介しています。
現地で探す(オフラインでの物件探し)
オンラインに出回っていない掘り出し物を見つけるには、現地調査が有効です。
地域を実際に歩いてみることで、空き家の雰囲気や周辺環境を体感できます。
また、空き家に「売家」などの張り紙があることも。
近隣住民に話を聞いてみると、思わぬ情報が得られることもあります。
地域密着の不動産会社を活用する
地方の物件は、大手ポータルサイトでは見つからないことが多いため、地元の不動産会社への相談がおすすめです。
特に「空き家の管理もしている会社」や「移住支援に積極的な自治体」と連携している業者は、民泊活用できる物件情報を持っている可能性が高いです。
空き家バンクや移住支援サイトを活用する
全国の自治体が運営する「空き家バンク」では、地域内の空き家情報を無償または格安で掲載しています。
中には、民泊利用を前提とした活用事例もあり、補助金制度と連動していることも。
自治体によって内容が異なるため、比較検討しながら問い合わせてみるとよいでしょう。
古民家民泊を経営する際の7つの注意点

古民家民泊を経営する際の
7つの注意点
古民家を民泊として活用するには、魅力だけでなく「古い建物特有のリスク」や「法規制」にも十分注意が必要です。
トラブルを避け、快適で安全な宿泊施設を提供するために、運営前に確認すべき7つの注意点を以下に解説します。
老朽化・耐震性を確認する
古民家の多くは築50年以上が一般的で、老朽化による構造的リスクが懸念されます。
特に重要なのが耐震性です。1981年以前の建築物は旧耐震基準の可能性が高く、耐震補強が必要な場合があります。
床の傾き、基礎のひび割れ、屋根の損傷なども見落とさないようにしましょう。
建築基準法や用途地域を確認する
民泊を始めるには、
- まず建物が建築基準法に適合しているか
- その地域が宿泊施設として営業できる用途地域かどうか
の確認する必要があります。
とくに、市街化調整区域では民泊の営業が制限されることが多く、場合によっては開業できないこともあります。
自治体によってルールが異なるため、事前にしっかり調べておきましょう。
消防法・水回り・配管をチェックする
消防法に基づき、消火器や誘導灯、火災報知器などの設置が求められます。
また、水回り(キッチン・トイレ・浴室)の配管が古いと、水圧不足や漏水の原因に。
特に13mmの配管は現代基準に満たないため、20mm以上への交換が推奨されます。
衛生面・安全面の両方からチェックが必要です。
害虫や断熱の問題に対応する
自然素材でできている古民家は、シロアリやゴキブリなどの害虫被害に遭いやすいです。
また、古い建物は断熱性が低く、夏は暑く冬は寒い傾向があります。
快適な滞在を提供するためには、防虫施工とともに、断熱材の導入や冷暖房設備の設置も検討すべきです。
雰囲気を残しつつ機能性を高める
古民家の「味」を残しつつ、現代の宿泊者が快適に過ごせるような機能性を持たせることが大切です。
たとえば、木造の天井や障子を活かしつつ、ベッドやユニットバス、Wi-Fiを導入するなど、デザインと利便性のバランスを取る工夫が必要です。
和モダンな雰囲気が特に人気です。
清掃・管理体制を整える
地方の古民家は、都市部と違って清掃業者が少ないことがあります。
開業前に、信頼できる清掃代行業者や地域の人との連携体制を確保しておくことが重要です。
清潔感はゲスト満足度やレビューに直結するため、運営の質を左右する大事なポイントです。
増改築の制限を把握しておく
古民家は景観保護区域や文化財に指定されている場合、勝手に増築・改築ができないことがあります。
また、建築確認申請が必要になるケースもあるため、リフォーム前に建築士や自治体に相談することをおすすめします。
計画的な設計と確認がトラブル回避に繋がります。
古民家民泊の費用とリノベーション費用相場

古民家民泊の費用と
リノベーション費用相場
古民家で民泊を始めるには、物件の取得費用だけでなく、改修工事・設備導入・インテリア準備など多岐にわたる費用が発生します。
ここでは費用の内訳ごとに目安を紹介します。
古民家購入費用の目安
古民家の価格は立地や状態によって大きく異なりますが、100万円〜500万円程度で購入できる物件も多く存在します。
中には無償譲渡(0円物件)や、格安で提供される空き家もあり、費用を抑えたい人には魅力的です。
ただし、築年数や傷みが激しい物件は改修費が高額になるため、購入時は現地調査が必須です。
リノベーション費用の相場
リノベーション費用は、建物の規模や改修内容によって差がありますが、一般的には1坪あたり10〜50万円が相場です。
例えば20坪の古民家をフルリノベーションすると、200万円〜1,000万円程度を想定しておく必要があります。
スケルトン工事(内部全面改装)を行うと高額になりますが、耐震・断熱・水回りを一新できるメリットもあります。
消防設備・水回り工事費
民泊運営には消防法に基づいた設備導入が必要で、消火器・誘導灯・火災報知器などの設置費用は30万円〜50万円程度が一般的です。
また、水道管が古い13mm配管の場合は、現代基準の20mmに交換する工事が発生し、費用は約40万円前後が目安です。
キッチン・トイレ・浴室の水回り工事も含めると、合計で100万円〜200万円程度になるケースが多いです。
家具・家電・インテリアの準備費用
宿泊用の家具や家電、寝具、照明、カーテンなどを揃える費用も見落とせません。
予算を抑えれば50万円前後でも整備可能ですが、デザインや品質にこだわると100万円以上かかることもあります。
ゲストの満足度に直結する部分なので、最低限の快適性と写真映えを意識して投資するのがおすすめです。
古民家民泊で使える補助金・助成金一覧

古民家民泊で使える
補助金・助成金一覧
古民家民泊を始めるには、ある程度の資金が必要ですが、補助金や助成金を上手に活用すれば、費用の負担を大きく減らすことができます。
地方自治体や国の制度には、空き家の活用や観光の活性化を目的とした支援がたくさんあります。
ここでは、古民家民泊に使える主な補助金制度と、申請する際のポイントをご紹介します。
なお、民泊で使える補助金については「民泊に使える補助金6選!空き家のリフォームに使える補助金まとめ【2025年最新】」の記事で詳しく解説しています。
地方自治体の空き家活用支援
多くの自治体では、空き家の再活用を促進するための補助制度を設けています。
補助金の内容は「古民家購入費用の一部補助」や「リフォーム費用の助成」などが中心で、上限は50万〜300万円程度が一般的です。
補助対象となる条件や用途(民泊可否)は自治体によって異なるため、事前に地元の空き家バンクや市役所窓口に確認することが大切です。
観光庁・国土交通省の補助金
国レベルでも、観光資源の整備や地方創生を目的とした補助金が用意されています。
たとえば、観光庁の「地域一体型観光・宿泊業支援事業」や、国交省の「空き家対策モデル事業」などが代表的です。
これらは自治体を通じて間接的に受ける形式が多く、複数の事業者や地域と連携することが前提になる場合もあります。
リノベーション・改修費の補助制度
古民家の改修にかかる費用に対して、自治体独自の「リノベーション補助金」が利用できることがあります。
内容は耐震補強、バリアフリー化、断熱・省エネ工事など、機能改善を目的とした改修費用が主です。
民泊用途で使う場合は、住宅宿泊事業としての条件を満たす必要があるため、対象工事かどうかも事前に確認しましょう。
古民家民泊の成功事例紹介

古民家民泊の成功事例紹介
全国各地では、古民家を活用した民泊事業が実際に成功しています。
ここでは5つの地域の具体的な成功事例をご紹介します。
長野県:農村体験型民泊の成功事例
長野県では、農業体験や地元の暮らしに触れられる「農村体験型民泊」が人気を集めています。
築100年の古民家を活用し、収穫体験や味噌作りなど、農村ならではの体験を提供。
特に海外旅行者からの評価が高く、地域の農業と観光の橋渡し役として成功しています。
山梨県:囲炉裏を活かした一棟貸し
山梨県の山間部では、囲炉裏付きの古民家を一棟貸しするスタイルが人気を集め、成功しています。
囲炉裏を囲んで食事を楽しめるといった、日常では味わえない和の体験が、特に外国人観光客に好評です。
また、写真映えする雰囲気がSNSでも話題となり、高い稼働率と安定した収益につながっています。
静岡県:観光地との連携でリピーター増
静岡県のある地域では、周辺の温泉地や観光施設と連携した古民家民泊がリピーターを増やしています。
宿泊だけでなく、地元のツアーや体験アクティビティを組み合わせたプランが好評。
地域全体で観光資源を活かすことで、高い顧客満足と再訪率を実現しています。
兵庫県:古民家カフェ併設型の収益モデル
兵庫県では、宿泊施設に古民家カフェを併設したスタイルが成功事例として注目されています。
観光客だけでなく地元住民も訪れる拠点となり、平日も安定した集客が可能に。
民泊とカフェの収益を両立させることで、年間を通じた収益モデルを確立しています。
滋賀県:地域資源を活かした宿泊体験
滋賀県では、里山の自然や伝統工芸を体験できる古民家民泊が好評です。
たとえば、和紙づくりや漆器のワークショップを宿泊とセットで提供。
地域文化を深く体験できる点が旅行者に喜ばれ、教育旅行やインバウンド客にも人気となっています。
古民家民泊のよくある質問(FAQ)

古民家民泊の
よくある質問(FAQ)
古民家で民泊を始めたいと思ったとき、多くの人が抱える疑問や不安を解消できるよう、よくある質問とその回答をまとめました。
初めての方でも安心してスタートできるよう、現場でよく聞かれるリアルなQ&Aを紹介します。
民泊として使える古民家の条件は?
基本的には、耐震性・消防法・建築基準法を満たしていることが条件です。
また、用途地域や都市計画区域の制限により、そもそも民泊営業が認められない地域もあります。
営業許可を得るには、自治体の規定や建物の現況に沿って、必要なリフォームや申請を行う必要があります。
築年数が古くても運営できる?
築年数が古くても、構造や設備が安全であれば運営は可能です。
むしろ、築100年以上の古民家は「文化的価値」として観光客から高く評価されることもあります。
ただし、老朽化が進んでいる場合は大規模な改修工事が必要になるため、費用や安全性の確認は必須です。
田舎でも予約は取れる?
田舎でも魅力的な体験や地域資源があれば、予約は十分に見込めます。
特に「非日常」「自然体験」「伝統文化」などを求める人にとって、都市部では味わえない田舎の古民家は強力な魅力になります。
SNSやOTAを活用すれば、認知度を高めて集客することも可能です。
田舎の民泊については「田舎で民泊経営は儲かる?年収の目安や成功させるコツも紹介」の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
自己資金ゼロでも開業できる?
完全な自己資金ゼロは難しいものの、補助金や助成金を活用すれば初期費用を大きく抑えられます。
格安で古民家を譲り受けられるケースもあり、自治体の空き家支援制度や改修補助を組み合わせれば、少ない資金でスタートすることは可能です。
ただし、最初の資金繰り計画は慎重に立てることが重要です。
まとめ|古民家で民泊経営を成功させるためには?
古民家民泊は、日本らしさを活かせる魅力的なビジネスです。
伝統的な建物を再利用することで、収益アップや地域への貢献、観光価値の向上につながります。
ただし、物件選びや制度の理解、法律の確認、運営体制の準備など、事前の計画がとても大切です。
費用や補助金、注意点をきちんと把握し、自分に合った方法で計画的に始めることが、古民家民泊を成功させるための第一歩となります。