
個人で民泊の始める方法|物件選びから運営開始までの手順を徹底解説
民泊は法制度を正しく理解した上で、事前準備を丁寧に行えば、個人でも十分に取り組める収益化モデルです。 空き物件を活かせるため、初期費用を抑えながらスタートできるケースも少なくありません。
しかし、「そもそも民泊って何?」「個人で始めても違法じゃないの?」「手続きや運営って大変そう…」といった疑問や不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、これから民泊を始めたい方に向けて、
・民泊の仕組みと制度の概要
・必要な許可や手続き、費用の目安
・自主管理と代行の違いや運営ステップ
・どんな人に向いているかの判断軸
といったポイントをわかりやすく整理して解説していきます。
この記事を読み終えるころには「民泊を始めるには何をすべきか」が明確になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
民泊とは?個人でも始められる副業モデル
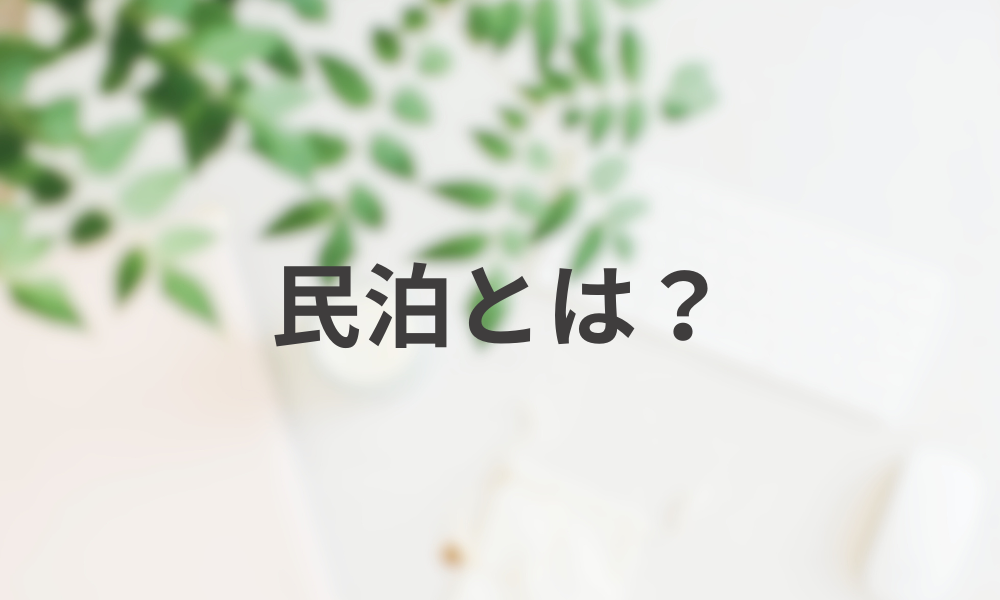
民泊とは、自宅の空き部屋や所有する物件を旅行者に短期間貸し出す宿泊サービスのことです。元々は訪日外国人向けの需要がきっかけで注目されましたが、現在では国内旅行者や出張者などのニーズにも広く対応しています。
一般的なホテルや旅館と異なり、民泊は小規模な物件でも運営可能です。たとえば、以下のような物件が民泊として活用されています。
・空き家や相続物件
・マンションの一室
・別荘やセカンドハウス
こうした物件を活用することで、大きな初期投資をかけずに宿泊ビジネスを始められます。
また、予約や集客は仲介サイトを使えば簡単に管理できるため、本業を持つ会社員でも運営しやすい副業モデルといえます。
近年では、民泊仲介サイトの操作性が大きく改善され、登録から運用開始までの手間が減ってきています。 例えばAirbnbでは、アカウント作成・物件登録・写真アップロード・料金設定・ハウスルール記入まで、すべてオンライン上で完結可能です。スマートロックや自動メッセージ機能と連携すれば、対面での対応がほぼ不要になります。
民泊とホテル・賃貸運用の違い

民泊は宿泊事業でありながら、ホテルや旅館、一般的な不動産賃貸とは異なる特徴を持っています。それぞれの違いを理解することで、民泊の立ち位置や可能性が見えてきます。
まず、ホテルや旅館は、建築基準法や旅館業法に基づき、常時営業を前提とした施設として運営されます。設備基準やサービス体制が厳格で、事業者には一定の資本力や運営ノウハウが求められます。
一方、民泊は「簡易宿泊施設」または「住宅宿泊事業」として位置付けられます。そのため、自宅や小規模物件でも比較的柔軟に運営可能です。必要な許認可を取得すれば、個人でも始められる点が大きな違いです。
また、民泊と不動産賃貸も根本的に異なります。賃貸は長期契約を結ぶことで安定した家賃収入を得るモデルです。しかし、民泊は短期滞在者を対象とするため、予約数や宿泊単価によって収益が変動します。運営の手間はかかりますが、そのぶん高収益を狙える点が魅力です。
それぞれの違いをまとめると、以下のとおりです。
| 比較項目 | ホテル・旅館 | 賃貸 | 民泊 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 1泊~数泊 | 数ヶ月~数年 | 1泊~数泊 |
| 必要な施設規模 | 大規模 | 小〜中規模 | 小規模でも可 |
| 収益モデル | 固定料金+オプション | 固定家賃 | 変動型(稼働率×宿泊単価) |
| 初期コスト | 高 | 中 | 低〜中 |
| 個人での開業 | 難しい | 可能 | 可能 |
民泊は、ホテルよりも手軽で、賃貸よりも収益性が高い可能性を秘めた選択肢といえるでしょう。
民泊と賃貸のどっちがいい?副業目線で比較
賃貸は「安定型」のビジネスです。一度入居者が決まれば、契約期間中は毎月一定の家賃収入が見込めます。支出も予測しやすく、手間もそれほどかかりません。副業にかけられる時間が限られていたり、投資に安定性を求める人には、賃貸が向いているでしょう。
一方、民泊は「成長型」のビジネスです。宿泊需要に応じて収益が変動する反面、立地や運営の工夫次第で高収益を狙える伸びしろがあります。リフォームや内装、接客の質が収益に直結するため、自分のアイデアや改善が結果に反映されやすい点も魅力です。
「できるだけ手間をかけずに安定収入を得たい」という方には賃貸、「手間がかかっても収益を伸ばしたい」「事業として育てていきたい」という方には民泊が向いています。自分のライフスタイルや副業にかけられるリソースに応じて、適切な選択をすることが大切です。
民泊を始めるには許可が必要?法律と制度を正しく理解
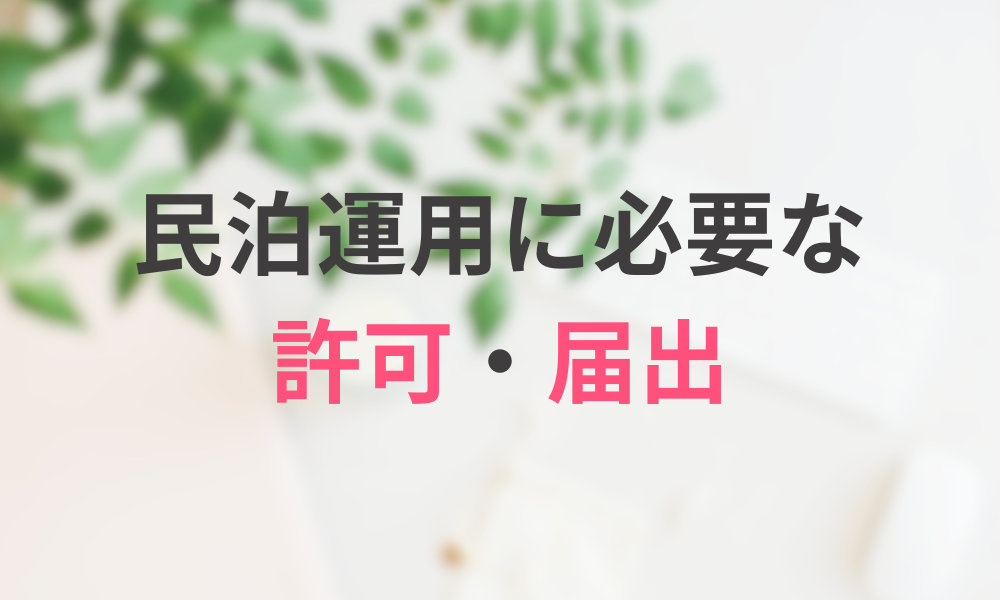
民泊を運営するには許可・届出が必要です。
民泊は誰でも気軽に始められるわけではなく、適切な許可や届出が必要な「れっきとした事業」です。法律や制度を理解せずに運営を始めると、行政指導や罰則を受けるリスクがあります。
この章では、民泊を合法的に運営するために必要な「法律上のルール」と「自治体ごとの制限」をわかりやすく整理します。
民泊を始めるために必要な許可は?
民泊を運営するには、主に次の3つの制度のいずれかに基づく許可・届出が必要です。
・住宅宿泊事業法(民泊新法):年間180日以内の宿泊営業が可能。比較的手軽に届出でき、副業にも向いています。
・旅館業法:365日営業可能。ホテルや簡易宿所など、本格的な宿泊業として運営する場合に必要です。
・特区民泊制度:一部自治体でのみ認められている制度で、条例に基づいて営業日数や条件が異なります。
たとえ自分が所有する物件であっても、無許可で宿泊させることは法律違反となるため、必ず適切な手続きを行いましょう。制度の選択によって必要な設備・運営方法・営業日数の制限が異なります。
住宅宿泊事業・旅館業・特区民泊の違い
3つの制度には、それぞれ特徴があります。
| 制度名 | 営業可能日数 | 運営主体 | 設備要件 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅宿泊事業(民泊新法) | 年180日以内 | 自主管理 or 委託 | 一定の衛生・防火基準 | 初心者向け、副業でもOK |
| 旅館業法 | 制限なし(通年営業可) | 法人・個人 | 高い基準が必要 | 本格的な宿泊施設向け |
| 特区民泊 | 条例による | 条件に合致すればOK | 自治体が定める | エリア限定、自由度高め |
とくに住宅宿泊事業は、副業として民泊を始めたい人にとって最も現実的な選択肢です。ただし、物件所在地の自治体が制限を設けているケースも多いため、確認が必要です。
自治体ごとのルールや制限に要注意
住宅宿泊事業は国の制度ですが、実際には自治体ごとに追加の制限が設けられていることがあります。たとえば、
・住宅専用地域では民泊不可
・特定の曜日やシーズンのみ営業可能
・近隣住民への事前説明が義務付けられている
など、地域によってルールはさまざまです。
具体的には、東京都の一部エリアでは「月曜〜木曜のみ営業可」とされていたり、京都市中心部では届出可能エリアが極端に狭いなど、観光地であるほど厳しい傾向があります。また、住民の反対が強いエリアでは、「マンション内に管理組合の同意が必要」などの追加条件が設けられることもあります。
民泊の届出自体はオンラインでも可能ですが、自治体によっては事前相談や現地確認が必要になる場合もあります。そのため、実際に営業を始める前に必ず自治体の担当窓口へ問い合わせておくことが大切です。
民泊運営の始め方8ステップ
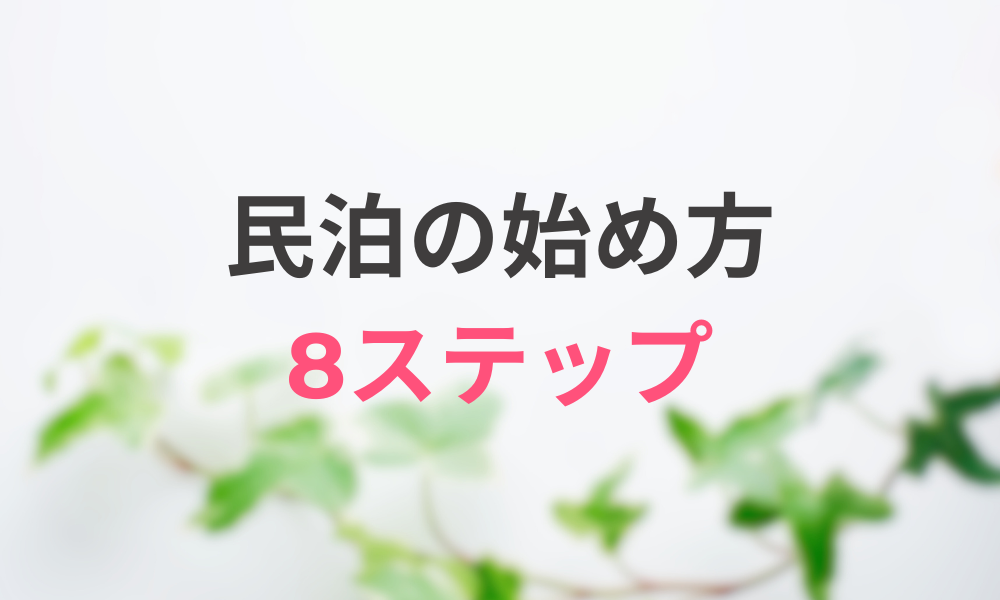
民泊を始めるには、やるべきことが明確に決まっています。以下の7ステップに沿って進めれば、はじめてでも無理なく運営をスタートできます。
民泊運営の全体ステップ
- 物件の選定と事前確認を行う
- 資金調達やローンの準備をする
- 事業計画を立てる
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出を行う
- 消防・保健所と必要な調整を行う
- Airbnbなど仲介サイトに登録する
- 営業開始・運用スタート
- 運営後の改善・リピーター獲得施策を行う
この流れに沿って、次の見出しからは各ステップを具体的に解説していきます。
ステップ①|物件の選定と事前確認を行う
民泊を始めるには、まず物件選びが第一歩です。副業として成功するには、立地や用途地域、建物の構造などをしっかり確認する必要があります。
また、分譲マンションなどの集合住宅では、管理規約で民泊が禁止されているケースも多いため注意が必要です。持ち家であっても、周囲への配慮や騒音対策も検討しておきましょう。
ステップ②|資金調達やローンの準備をする
物件が決まったら、次は初期費用の準備です。民泊の開業には、物件取得費だけでなく、改装・設備導入・届出手続きなどで数十万〜数百万円の資金が必要になることもあります。
自己資金で賄えない場合は、住宅ローンではなく、民泊対応の事業ローンや不動産投資ローンの検討が必要です。最近では、副業向けの融資プランを提供している金融機関もあるため、事前に情報収集をしておきましょう。
また、開業後すぐに収益が安定するとは限らないため、運営資金も含めて半年〜1年分の余裕資金を見込んでおくと安心です。
ステップ③|事業計画を立てる

民泊を安定的なビジネスとして成立させるためには、感覚に頼らず、数値に基づいた事業計画が欠かせません。
稼働率や宿泊単価、固定費・変動費といった基本指標を整理し、初期投資から回収までの見通しを立てておきましょう。
たとえば、以下のような要素を踏まえてシミュレーションを行います。
- 家賃(固定費)
- 宿泊単価(売上のベース)
- 稼働率(予約の入りやすさ)
- 清掃費・光熱費・手数料などの変動費
- 家具や家電などの初期投資額
こうした項目を明確にしておくことで、どれくらいの稼働で黒字になるか、いつ初期費用を回収できるかが見えてきます。
シミュレーション例1:都内のワンルームを活用したケース
- 家賃:月15万円
- 宿泊単価:1泊8,000円
- 稼働率70%(月21泊)→売上168,000円
- 諸経費差し引き後の利益:約3〜5万円/月
この場合、家具や家電の導入費として10〜20万円の初期費用も必要になるため、収支がプラスになるまでには数ヶ月〜半年ほどかかる見込みです。
シミュレーション例2:郊外や地方の一軒家(3LDK)を活用するケース
- 宿泊単価:1泊15,000〜20,000円
- 稼働:月20泊で月収30万円以上も可能
観光需要やファミリー層のニーズが高いエリアであれば収益性は高くなりますが、その分、
- 初期費用
- 家具の調達・設置コスト
- 清掃などの管理コスト
も高くなるため、資金回収には時間がかかる点に注意が必要です。
ダイナミックプライシングの活用
収益性を高めるためには、価格を柔軟に調整できる仕組みの導入が効果的です。
- 平日・週末・繁忙期・閑散期に合わせて料金を自動調整
- 宿泊単価を最適化し、機会損失を減らす
- 多くの民泊予約サイトで利用可能
特に副業として民泊を運営する場合は、こうしたツールを導入することで手間を減らしながら利益を最大化できます。
損益分岐点の把握
あわせて、事前に損益分岐点(何泊で黒字になるか)を把握しておくことも重要です。
- 黒字化に必要な月間の宿泊数
- 閑散期の赤字を繁忙期でどの程度カバーできるか
- 季節変動の幅に応じた調整戦略
民泊の収益は月単位での変動が大きいため、四半期や半年単位での収支計画を立てることをおすすめします。
長期視点での「出口戦略」も考えておく
事業計画には、撤退や運営方針の見直しといった「出口戦略」もあらかじめ組み込んでおくと安心です。
- 賃貸物件の場合:
契約更新時の撤退判断の基準を設けておく - 自宅を活用する場合:
何年運用するかなど、中長期の方針を明確にしておく
将来的な変化に備え、判断基準を事前に持っておくことで、損失を最小限に抑えることができます。
ステップ④|住宅宿泊事業(民泊新法)の届出を行う

民泊を合法的に始めるためには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が必要です。
これは、「年間180日以内の運営」を条件に、個人でも民泊を行えるようにした制度で、多くの副業民泊オーナーがこの方式を選んでいます。
主な手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類の準備:
本人確認書類、間取り図、設備の写真、近隣との境界図などが求められます。 - 物件所在地の自治体へ届出:
書類を揃えたら、所轄の都道府県や保健所などにオンラインまたは窓口で申請します。 - 受理後、届出番号を取得:
受理されると、住宅宿泊事業者としての届出番号が発行され、仲介サイトへの掲載が可能になります。
※なお、物件の用途地域によっては民泊自体が禁止されていたり、別の許可(旅館業など)が必要なケースもあるため、事前に自治体のルールを確認することが大切です。
ステップ⑤|消防・保健所と必要な調整を行う
民泊を始めるうえで見落としがちなのが、消防法や衛生面の基準を満たすための調整です。特に住宅宿泊事業の届出を行う場合でも、消防署や保健所との連携が求められるケースがあります。
消防法に関するチェックポイント
・誘導灯や消火器の設置義務
・非常口の明示
・火災報知器の設置・作動確認 など
物件の規模や構造によって必要な対策が異なるため、事前に所轄の消防署に相談し、立ち入り調査を受けることが望ましいです。
また、衛生面では以下の点に留意が必要です。
衛生面での留意点(必要に応じて)
・ゴミの分別・保管方法
・リネン類の衛生管理
・清掃頻度やチェック体制の整備
特に、キッチンやトイレなどをゲストと共有するタイプの民泊では、宿泊者の安全・安心を満たす環境整備が求められます。スムーズな営業開始のためにも、専門家や行政窓口を活用して万全の体制を整えましょう。
ステップ⑥|仲介サイトに登録する

届出や設備の準備が整ったら、いよいよ集客のスタート地点となる予約サイトへの登録に進みます。
初めて民泊を運営する方は、広く知られた仲介サイトを活用することで、集客面の不安を軽減できます。
主な登録作業の流れ
・施設情報の入力(所在地・写真・設備など)
・宿泊料金や清掃費、定員数の設定
・ハウスルールやキャンセルポリシーの記載
・予約確定後の連絡やチェックイン対応の設定
これらを丁寧に設定することが、検索順位や予約率の向上につながります。
また、掲載する写真の見せ方や説明文の構成によっても予約数は大きく変わるため、競合施設を参考にしながら工夫することが重要です。
予約サイトによっては事前審査や公開までに数日を要するケースもあります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
ステップ⑦|営業開始・運用スタート
予約サイトに掲載が完了すれば、いよいよ民泊の営業スタートです。
実際の運用では、宿泊予約の受け付け、問い合わせ対応、清掃手配、レビュー管理などやるべきことが多岐にわたります。
特に初期段階では、以下の対応を丁寧に行うことが重要です。
運用初期に意識すべきポイント
・宿泊前後の清掃やリネン交換の手配を忘れずに
・チェックイン方法はわかりやすく案内(キーボックスやスマートロックなど)
・宿泊者からの問い合わせにはできるだけ迅速に対応
・滞在後のレビューには必ず目を通し、必要に応じて改善を行う
また、初期のレビュー獲得は今後の集客力に大きく影響します。
そのため、宿泊者に気持ちよく滞在してもらえるよう、清潔さやホスピタリティの強化に力を入れましょう。
「ただ泊まれる部屋」ではなく、「また利用したい」と思ってもらえる体験を提供することが、長期的な成功につながります。
ステップ⑧|運営後の改善・リピーター獲得施策を行う

民泊運営はスタートして終わりではありません。実際の営業が始まってからの改善と調整が、収益の安定化とブランド力向上のカギを握ります。
とくに副業として行う場合、毎回の宿泊者に対応する時間を増やすよりも、レビューや再訪問の質を高める施策に注力する方が、効率よく成果につながります。
よくある改善ポイント
・レビューで指摘された不満点の改善(騒音・備品・清掃頻度など)
・価格の見直し(競合と比べて高すぎ・安すぎる設定になっていないか)
・写真・説明文の更新(季節やイベントに応じた差し替え)
・長期滞在者向けのプラン導入(割引+清掃スケジュールの工夫)
・チェックイン方法の簡素化(スマートロックや動画マニュアルなど)
また、宿泊満足度を高めた後は、再訪問してくれるユーザーを増やすための「仕掛け」が必要です。 たとえば、宿泊後にお礼メッセージや次回割引クーポンを送ったり、季節ごとに「常連向けプラン」をメール配信で案内したりすることが挙げられます。
民泊物件の選び方
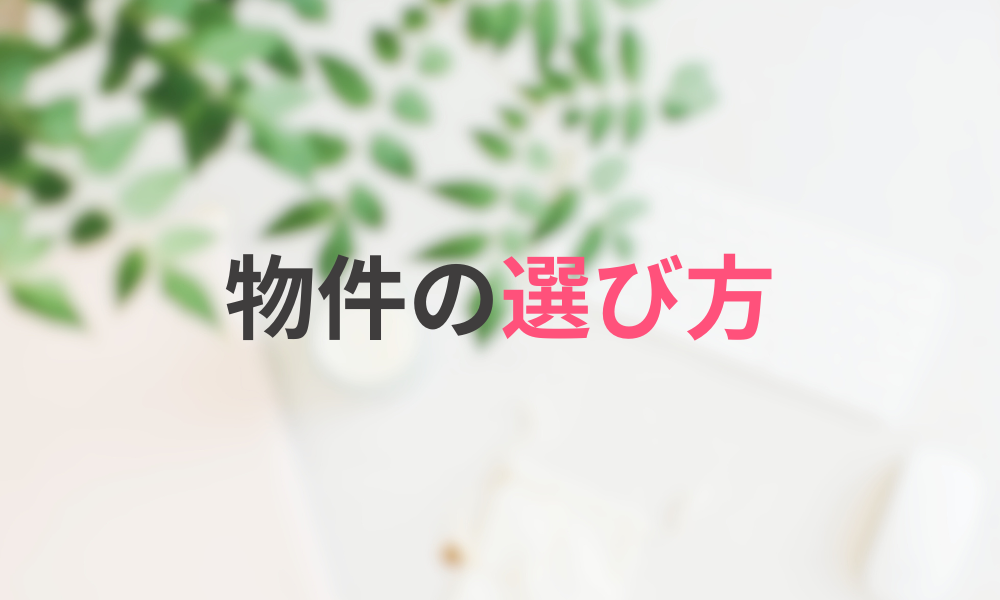
民泊で失敗しないためには、立地・構造・ルールの3点を満たす物件を選ぶことが最優先です。
どれだけ魅力的なサービスを用意しても、物件選びを間違えると民泊運営は失敗します。立地が悪ければ予約は入りにくく、構造が不向きだと騒音トラブルに発展し、ルール違反があれば運営停止にもなりかねません。
まずは以下の3つの視点で、候補物件をチェックしましょう。
①【立地】宿泊需要のあるエリアか
需要の高いエリアの条件は以下です。
- 駅から徒歩10分以内(特に観光都市やビジネス街)
- 空港・観光地・繁華街までのアクセスが良い
- 周囲に飲食店・コンビニ・コインパーキングなどがある
たとえば、東京であれば新宿・浅草・品川周辺、大阪なら難波・梅田・天王寺エリアなどが人気です。一方で、郊外やアクセスにクセのあるエリアは稼働が落ちやすく、集客にコストがかかる傾向があります。
②【構造】トラブルの起きにくい建物か
建物の構造によって、ゲストの快適性や近隣との関係が大きく変わります。
- RC造(鉄筋コンクリート造):防音性◎、断熱性◎ → 民泊に最適
- 木造:安いが音漏れしやすく、騒音クレームリスク高
- 階段の角度、玄関の位置、玄関から道路までの距離なども要確認
特にファミリー層やグループ旅行の受け入れを考えるなら、防音性の高さは必須です。
また、階段しかない3階建てや、敷地の奥まった位置にある家などは、スーツケースを持った旅行者には敬遠されやすくなります。構造的な導線の確認も忘れないようにしましょう。
③【ルール】民泊が可能な物件か
以下のようなケースでは民泊が禁止されている、または禁止される可能性があります。
- 【用途地域】第一種低層住居専用地域 → 住宅以外の営業行為NG
- 【管理規約】分譲マンションで「民泊禁止」と明記されているケース多数
- 【賃貸契約】オーナーの書面による許可がない場合 → 無断運営で契約解除のリスク
加えて、「民泊対応OK」とうたう物件でも、近隣住民の理解が得られていなければ運営継続が難しい場合もあります。騒音・ゴミ出し・出入りの多さなどに配慮した運営体制が求められます。
民泊運営に必要な設備・内装とは?
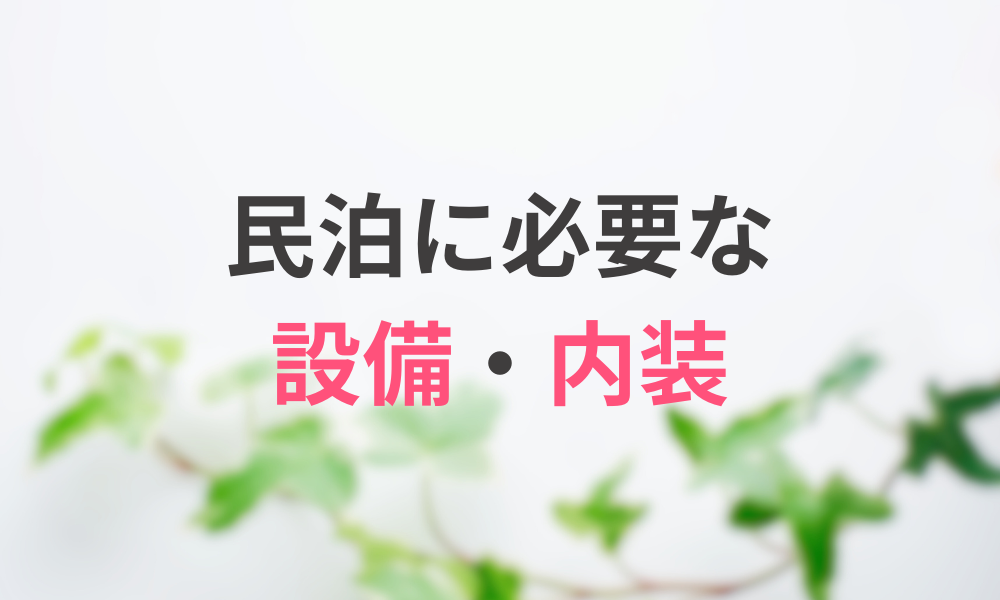
民泊を成功させるには、法律で定められた最低限の基準を満たすだけでなく、口コミ評価やリピート率を左右する「空間づくり」が重要です。
この章では、民泊運営に必要な家具・家電、アメニティ、さらにはレビューを左右する内装の工夫を紹介します。「また泊まりたい」と思ってもらえる快適で魅力的な空間づくりを目指しましょう。
宿泊設備に必要な家具・家電の例
以下は、一般的な民泊物件に求められる主な設備です。
家具の例
・ベッドや布団(宿泊人数分)
・テーブルと椅子(食事や作業用)
・カーテンやブラインド(プライバシー確保のため)
・ハンガーラックや収納棚(荷物整理のため)
家電の例
・エアコンやヒーター(季節に応じた空調)
・冷蔵庫・電子レンジ・電気ケトル(飲食のため)
・洗濯機・掃除機(長期滞在者向け)
・Wi-Fiルーター(ネット環境の整備)
これらの設備は宿泊者にとって当たり前の存在であり、不足があると低評価に直結します。設置する際は、安全性・清潔感・使いやすさを重視し、壊れていないか、動作に問題がないかを定期的にチェックすることが大切です。
これらの基本的な設備に加えて、最近では「スマートロック」や「スマート照明」など、IoTを活用した快適さと安全性の向上も注目されています。とくに非対面チェックインを想定している場合、スマートロックは鍵の受け渡しが不要で運営効率も高まるため導入の価値があります。
また、壊れやすい備品は、同じ型番の予備を用意しておくと迅速な交換ができ、クレームを防ぐのに有効です。消耗が早い設備は、あらかじめ耐久性やメンテナンス性も重視して選定しておくと、運営中のストレスを軽減できます。
配置に関しても、ベッドやソファの導線、コンセント位置、照明の明るさなど、宿泊者の動線や生活感覚に寄り添った設備配置が重要です。
レビューを左右するアメニティと環境整備

「アメニティ」と「清潔な環境」は、民泊の評価を大きく左右します。豪華な設備を設置すれば良いわけではなく、まずは基本的な配慮が行き届いているかが重視されます。
高評価につながるアメニティ例
・バスタオル・フェイスタオル(人数分+予備)
・シャンプー・ボディソープ・歯ブラシセットなどの消耗品
・スリッパやルームウェア
・コーヒー・お茶・ミネラルウォーターなどの無料ドリンク
これらのアメニティは「あると嬉しい」だけでなく、「なかったら不満」という評価にもつながるため、事前の用意が欠かせません。
さらに、季節や地域に合わせたアメニティの工夫も差別化のポイントになります。たとえば、冬季には加湿器やブランケットを設置することで、乾燥対策や寒さへの配慮が伝わり、好印象を得やすくなります。夏場であれば、虫除けスプレーや扇風機なども喜ばれます。
また、地域性を活かしたおもてなしとして、地元のお菓子や観光パンフレット、近隣のおすすめ飲食店マップを用意するのも効果的です。宿泊者は「その土地らしさ」に触れたいという気持ちが強いため、こうした小さな工夫が「また泊まりたい」という感情につながります。
また、室内の清掃や換気、ゴミの管理などの環境整備も重要です。特に水まわりの衛生状態は口コミで言及されやすいため、定期的な清掃ルールを設けて維持しましょう。
民泊向けリフォームのポイントと費用の目安
民泊を運営するにあたって、物件の魅力を高めるためにリフォームが必要になることがあります。ただし、過度な改装は費用対効果が見合わないこともあるため、目的を明確にしたうえで取り組むことを心がけましょう。
リフォームの主な目的
・民泊の法令基準をクリアするため
・内装を整え、写真映えする部屋にするため
・水まわりの設備や老朽化部分を使いやすくするため
とくに重要なのが見た目の印象です。物件の第一印象は予約率に直結するため、壁紙・照明・家具の配置など、低コストで空間の雰囲気を変えられるポイントに投資すると費用対効果が高くなります。
リフォーム費用の目安
・軽微な内装変更(壁紙・照明・家具入れ替え):10〜30万円
・水まわり改修(ユニットバス・洗面・トイレなど):50〜100万円
・フルリノベーション(間取り変更・全体改修):200万円以上
物件の状態や広さ、目的によって金額は大きく異なりますが、民泊向けであれば必要最小限で印象を良くすることを優先しましょう。
また、民泊向けリフォームで失敗しがちな点は、デザイン重視で使い勝手を犠牲にすることです。たとえば、おしゃれなデザインの照明が暗すぎたり、間接照明のみで作業がしづらかったりするケースです。とくに外国人ゲストにとっては、明るさや操作の直感性が重視されるため、機能性とのバランスを意識しましょう。
コストを抑えるためには、DIYの活用もおすすめです。家具の組み立てや壁紙の貼り替えなど、自力で対応できる範囲を洗い出してみましょう。ただし、配線や水道などの専門工事に関しては、安全性を担保するために必ず専門業者への依頼が必要です。
外国人対応・多様性への配慮も今後の鍵

近年、インバウンド需要の回復に伴い、外国人旅行者向けの対応設備も評価基準として重視されつつあります。
たとえば以下のような設備や工夫が、海外ゲストからの評価向上に貢献します。
・変圧器(変換プラグ)の用意
・多言語対応マニュアルの設置(英語・中国語など)
・宗教配慮(イスラム教徒向けの礼拝スペース案内など)
・アレルギー対応の寝具・洗剤使用の明示
また、日本人の高齢ゲストや障がいのある方への配慮として、ユニバーサルデザインも今後の選ばれるポイントになります。民泊は「ただ寝る場所」ではなく、「安心して過ごせる空間」になって初めて価値が出ます。そう意識して整備することが、選ばれる物件への第一歩です。
民泊運営の費用と収益モデルを具体化する
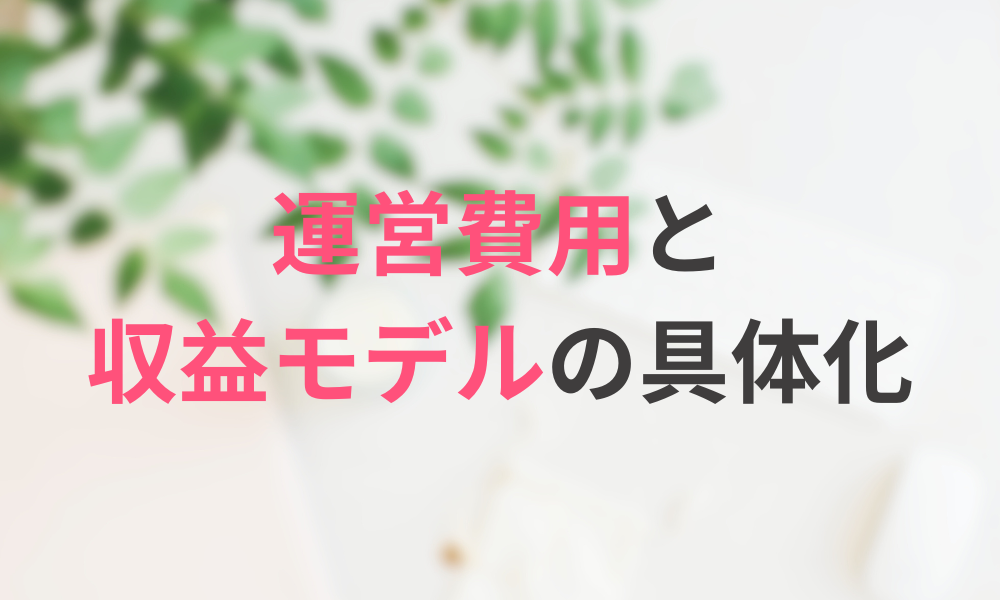
民泊を始めるうえで、多くの人が気になるのが「どれくらいの費用がかかり、どの程度の収益が見込めるのか」という点です。ここでは、初期費用・運営コスト・収益の目安など、実際の数字に基づいてリアルなモデルを解説します
初期費用の内訳と目安(物件+改装+設備)
民泊を始めるにあたって必要となる初期費用は、大きく以下の3つの項目で構成されます。
- 物件取得費(賃貸または購入にかかる初期費用)
- 改装・リフォーム費(内装や水回りの整備など)
- 家具・家電などの設備費(宿泊に必要な備品類)
それぞれの費用感を事前に把握しておくことで、無理のない資金計画を立てやすくなります。
1.物件取得費
物件を賃貸する場合でも、以下のような初期費用がかかります。
- 敷金・礼金
- 仲介手数料
- 初月分の家賃など
これらを合わせると、家賃の3〜5か月分程度を想定しておく必要があります。
一方、物件を購入する場合はさらに大きな資金が必要になります。
- 頭金
- 登記費用やローン手数料などの諸費用
これらを合わせて、数百万円規模の初期投資が必要になるのが一般的です。
2. 改装・リフォーム費
物件の状態や想定するゲスト層によっても変動しますが、基本的な改装だけでも以下のような工事が発生します。
- 壁紙の張り替え
- 水回りの補修(キッチン・浴室・トイレ)
- 室内清掃や簡易な修繕
このような最低限のリフォームでも、30〜50万円程度の費用がかかることが多いです。
また、以下のような追加工事を行う場合は、さらに費用がかさみます。
- 和室を洋室へ変更するリノベーション
- インバウンド観光客向けの内装デザイン
- バリアフリー対応や照明の交換
3. 家具・家電などの設備費
宿泊者が快適に滞在するためには、必要な設備を一式揃えることが不可欠です。主な購入品としては以下のようなものが挙げられます。
- ベッド、寝具類
- テーブル・チェアなどの家具
- 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの家電
- エアコン、照明器具、カーテン
- Wi-Fiルーターや掃除機など
設備のグレードや物件の広さによって差はありますが、おおよそ20〜50万円前後を想定しておくとよいでしょう。
これらを合わせると、賃貸物件での運用でも初期費用として合計100〜150万円前後は見込んでおきましょう。購入型で本格的に始める場合は、さらに多くの資金が必要となります。
ランニングコストと収支シミュレーション
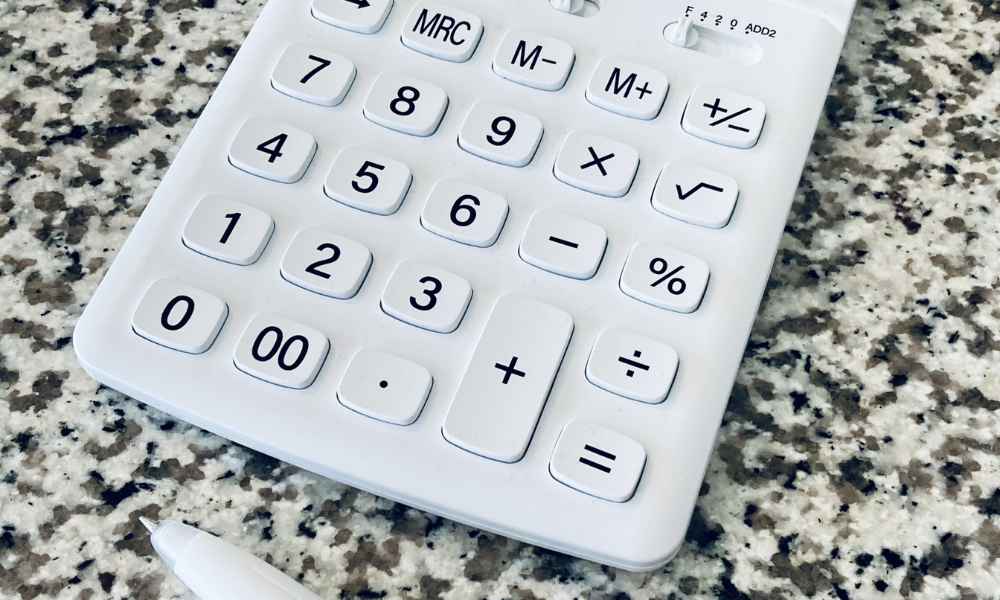
民泊運営では、初期費用に加えて毎月かかる「ランニングコスト」も把握しておくことが重要です。利益がどれほど見込めるかを予測するうえで、固定費と変動費のバランスを理解しておきましょう。
代表的なランニングコストは以下の通りです。
・家賃またはローン返済額(物件が賃貸・購入かで異なる)
・光熱費(電気・ガス・水道・Wi-Fiなど)
・消耗品代(トイレットペーパー、洗剤、アメニティなど)
・清掃費用(外注または自分で対応する場合のコスト)
・予約サイト手数料(Airbnbなどに支払うマージン)
たとえば、以下のような条件でシミュレーションを行ってみましょう。
- 家賃:月10万円
- 光熱費・清掃費・消耗品・手数料などの運営コスト:月5万円
この場合、月の固定費は合計で約15万円となります。
宿泊料金を1泊1万円とした場合、月15泊の予約があれば売上は15万円となり、損益分岐点に達します。つまり、15泊以上の予約が入ると黒字、14泊以下だと赤字という計算になります。
また、民泊はシーズンによって大きく収益が変動するのが特徴です。
繁忙期には30泊近くの予約が入ることもあり、その場合は売上30万円、利益15万円と大きく収益が伸びる可能性もあります。一方で閑散期に稼働率が下がると赤字になるリスクもある
このように、収支は月ごとに大きく変動するため、年間を通じた平均稼働率で損益を見積もることが重要です。
また、税金や保険料、突発的な修繕費用も年間コストとして加味しておくと、より現実的なシミュレーションになります。
繁忙期と閑散期の収益差と備え方
民泊はシーズンによって宿泊需要が大きく変動するため、繁忙期と閑散期の収益差を理解し、それに備えた運営戦略が必要です。
繁忙期とは、観光シーズンや長期休暇が重なる時期を指します。その時期は、多くの旅行者が宿泊先を探すため、予約が取りやすく、宿泊単価も上げやすくなります。この時期には稼働率が90〜100%になることもあり、1年の中で最も収益を稼ぎやすいタイミングです。
一方、閑散期は観光やイベントが少なくなる時期で、稼働率が落ち込むうえに、価格競争が激化します。閑散期でも最低限のコストはかかるため、赤字になるリスクもあります。
こうした収益の波に備えるには、以下のような対策が有効です。
・繁忙期に価格を戦略的に引き上げる(ピーク料金設定)
・閑散期に長期滞在者向けの割引を用意する
・イベントや観光情報を活用し、オフシーズンでも魅力を伝える
・リピーターやSNSフォロワーに向けた限定プランを展開する
また、年間収支の見通しを立てる際は、月別の売上予測を立ててキャッシュフローを管理することが、安定経営のカギとなります。
民泊を自分で回す?それともプロに任せる?
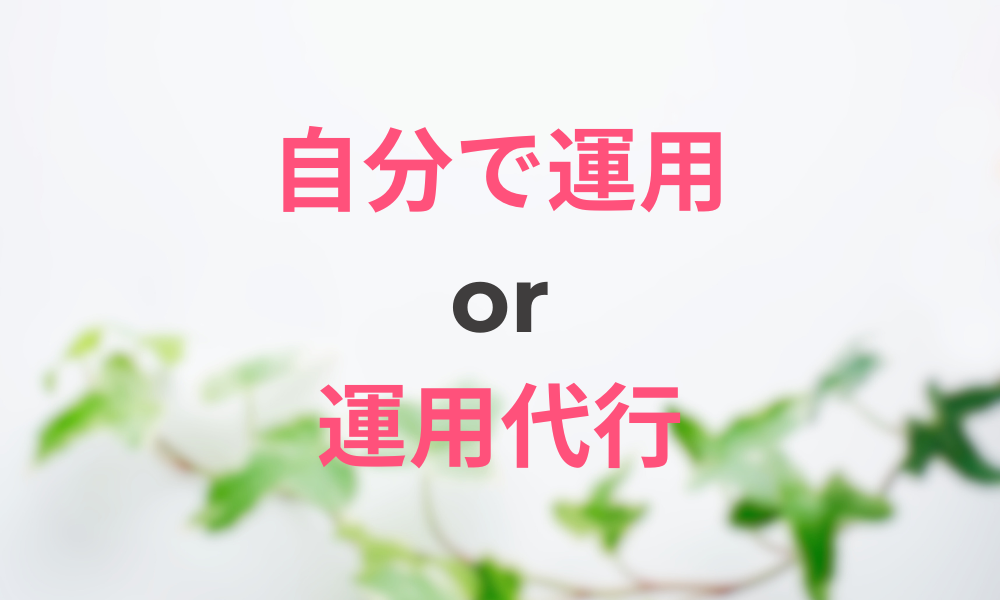
民泊運営を始める際に悩みやすいのが、「すべて自分で管理すべきか」「プロに任せるべきか」という点です。副業として取り組む場合、時間的な余裕やスキルの有無によって最適な選択肢は異なります。
ここでは、民泊の運営スタイルの違いや特徴、メリット・デメリットを比較し、どちらが自分に合っているかを判断する材料を提供します。
「副業で自主管理」は可能か
民泊を完全に自主管理で運営することは可能ですが、想像以上に業務の幅が広く、継続には体力と時間が求められます。特に副業として始める場合、本業とのバランスを崩さずに運営できるかが大きな課題となります。
実際の自主管理では、以下のような業務が日常的に発生します。
・ゲストからの問い合わせ対応(多言語対応が必要なケースも)
・予約管理・カレンダー調整
・チェックイン・チェックアウトの手配
・清掃業者の手配や鍵の管理
・トラブル時の緊急対応(設備不具合・近隣クレームなど)
これらのタスクを365日・24時間体制で対応する必要があるため、本業が忙しい人には大きな負担となる可能性があります。
とはいえ、運営経験を積むことでコツや仕組み化も可能になり、自分のスタイルを確立できればコストを抑えて高収益を狙えるのも事実です。
したがって、自主管理を目指すなら、最初からすべてを完璧にこなそうとせず、まずは小規模・短期間から試してみるのが現実的です。
代行業者を使うメリット・デメリット

民泊の運営を代行業者に委託することで、本業との両立やストレス軽減が図れます。特に副業として民泊を始める場合、時間と労力の節約が最大のメリットです。
主な代行サービスには以下のようなものがあります。
・予約・カレンダー管理
・ゲスト対応(問い合わせ・トラブル対応)
・清掃・リネン交換手配
・チェックイン・チェックアウト対応
・宿泊者レビュー管理 など
これらを一括で委託するフルサポート型や、一部業務だけを代行するカスタム型も選べるため、自分に合った形で始めやすいのが特徴です。
ただし、手数料がかかるといったデメリットも存在します。収益の一部を業者に支払う形にはなりますが、安心感や本業との両立性を重視したい場合には有力な選択肢です。
サポートを受けて効率よく運用する選択肢
民泊運営をスムーズに行いたいなら、専門サポートを受ける選択肢も検討しましょう。特に初めて民泊を始める場合は、制度理解・物件選び・届出・集客まで一貫して支援してもらえると、大きな安心材料になります。
具体的には、次のようなサービスが提供されていることが一般的です。
・物件選びのアドバイス:民泊に適した立地や間取り、設備の基準を踏まえた物件提案
・リフォームや家具選びのサポート:民泊用に必要な内装・設備の整備
・法的手続きの支援:届出・消防対応・自治体とのやりとりの代行
・運用後の改善提案:レビュー分析や価格設定の見直しなど
こうしたトータルサポートを受けることで、副業としての民泊も安心して始められる体制を整えることができます。
費用はかかるものの、「手続きが不安」「何から始めていいかわからない」という初心者にとっては、リスクを抑えて最短で立ち上げる手段として有効です。
民泊に関するよくある質問

民泊を始めたいと考えても、制度やお金、運営の負担など、実際には不安がつきものです。
ここでは、副業として民泊を検討している方が特に気になるポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。
本業があっても民泊運営はできる?
可能です。民泊運営は「副業としての運用」を前提とした仕組みも整っており、本業がある方でも時間をかけずに運営できる方法があります。
例えば、以下のような対応策をとることで、労力を抑えつつ収益化が可能です。
・清掃やゲスト対応を外部業者に委託する
・スマホで完結する管理アプリや自動メッセージ機能を活用する
・民泊代行サービスに運営を任せる
実際、副業として民泊を始める会社員や主婦の方も多く、無理のない範囲で収益を得る手段として定着しつつあります。ただし、繁忙期の対応やトラブル時に備え、事前の準備とスケジューリングが重要です。
民泊でも住宅ローンは使える?
原則として、住宅ローンで購入した物件を営利目的の民泊に使うことはできません。
住宅ローンは「自己居住用」の目的で金融機関から借りるものだからです。
ただし、以下のような例外や対応策があります。
・自宅の一部(空き部屋など)を短期的に貸し出す形なら、黙認されるケースがある
・ローン返済後に民泊へ転用する
・最初から「投資用ローン」や「事業用ローン」を組む
注意点として、住宅ローンで購入した物件を無断で民泊に転用した場合、ローン契約違反となり、一括返済を求められるリスクもあります。
民泊を視野に入れて不動産を購入する場合は、事前に金融機関に相談することが必須です。
確定申告や税金の扱いはどうなる?
民泊運営で得た収益は「事業所得」または「雑所得」として扱われ、確定申告が必要になります。副業であっても、所得が年間20万円を超える場合は申告義務が生じます。
民泊収入に関係する主な税金は以下の通りです。
・所得税・住民税:収入から経費を差し引いた利益に対して課税
・消費税:年間売上が1,000万円を超える場合に課税対象
・固定資産税:物件保有に対して毎年課税される
また、経費として計上できるものには以下のようなものがあります。
・光熱費、清掃費、リネン代
・仲介サイトの手数料
・設備・備品購入費
・修繕費、保険料、通信費 など
節税の観点からも、収支を正確に記録しておくことが重要です。税理士に相談することで、適切な申告と節税対策が可能になります。
副業として始めた場合、会社にバレることはありますか?
会社に知られずに民泊を運営することは可能ですが、リスクがゼロとは言い切れません。特に住民税の課税方法によっては、自治体から会社へ通知が届くこともあります。
バレたくない場合は「確定申告時に普通徴収を選ぶ」「開業届を出しておく」といった対策が有効です。また、勤務先の就業規則で副業が禁止されていないかも事前に確認しておきましょう。
外国人ゲストとのやりとりが不安です。
仲介サイトのプラットフォームでは、翻訳機能があるため英語ができなくてもある程度は対応可能です。とはいえ、トラブル時や緊急対応ではスムーズな意思疎通が必要になるでしょう。
基本的な定型文(チェックイン方法、ハウスルール、Wi-Fi接続など)はあらかじめ用意しておくと安心です。また、近年は民泊対応のチャット代行サービスもあるため、英語対応が苦手な方でも安心して運営できます。
民泊トラブルで困ったらどうする?
民泊運営では、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
・宿泊者による備品の破損や室内の汚損
・近隣住民との騒音トラブル
・無断宿泊や人数超過、規約違反行為
・キャンセル・ノーショーによる収益減少
こうした事態に備えるためにまずは、ハウスルールを明確に提示し、予約時に同意を得ることが重要です。また、損害保険の加入や、セキュリティカメラ・スマートロックの設置など、トラブルを未然に防ぐ工夫も有効です。
それでもトラブルが発生した場合には、以下のような対処法があります。
・宿泊予約サイトを通じてサポートに報告・補償申請を行う
・状況に応じて警察や自治体に相談する
・管理代行会社を利用して対応を委ねる
安心して運営を続けるためには、すぐに第三者に相談できる体制を作っておくことが重要です。
個人でも複数物件を運営できますか?
可能です。むしろ副業からスタートして、複数物件を運用している個人事業主は増えています。ただし、管理業務や清掃の手間も増えるため、自動化や外部委託を視野に入れた仕組みづくりが大切です。
また、複数物件を扱う場合は、資金繰りやキャッシュフローの管理も複雑になるので、表計算ソフトなどで日々の管理を徹底しましょう。
住宅宿泊管理業者や代行業者に頼んだ方がいいですか?
本業が忙しいサラリーマンの場合、集客やゲスト対応、清掃手配などをすべて自分で行うのは困難です。そのため、運営の一部または全部を外部に任せる「民泊代行業者」の活用は非常に有効です。
ただし、手数料は売上の20〜30%前後が一般的で、利益が圧迫されるおそれもあります。自分の時間と利益のバランスを見て、必要な部分だけ依頼するのもひとつの手です。
民泊に向いている方の特徴
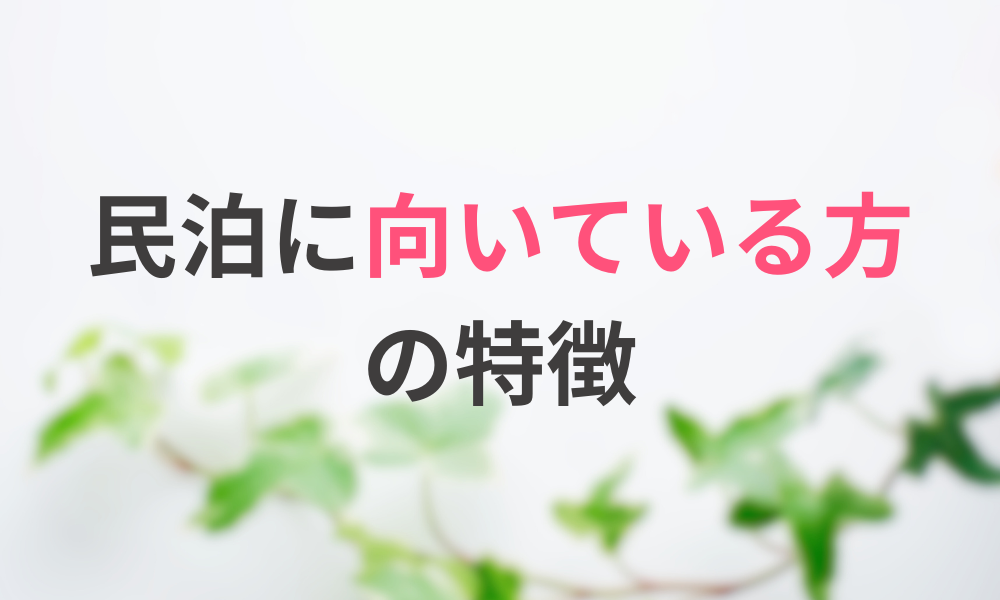
民泊は比較的自由度が高く、さまざまなスタイルで始められる副業です。その中でも特に、次のような人には民泊運営が向いている傾向があります。
・不動産投資に興味はあるが、初期費用はできるだけ抑えたい
・本業に支障なく副収入を得たい、将来的な資産形成も考えている
・おもてなしや接客に抵抗がなく、人との交流が苦にならない
・自分のペースで小さく始めて、コツコツ事業を育てていきたい
不動産に興味があるが初期投資を抑えたい人
「不動産投資には興味があるけれど、数千万円単位の初期費用をいきなり出すのは難しい。」そんな方にとって、民泊はおすすめです民泊は、必ずしも物件の購入から始める必要はありません。家主の許可を得て賃貸物件を活用する「借り上げ型」の民泊であれば、数十万円単位の初期資金で運用を始めることも可能です。
また、必要最低限の家具や家電、清掃環境を整えれば、十分に運営を始められます。最初は1室からスタートし、実績を積んでから複数物件に広げていくことも可能です。
不動産の知識や投資経験がない方でも、民泊を通して「物件選定」「運用管理」「収支管理」といった基礎を実践的に学ぶことができます。将来的に本格的な不動産投資にステップアップしたいと考えている人にとっては、低リスクで経験を積みながら、自分の適性や運用スタイルを見極められる絶好のチャンスです。
将来の資産形成を副業で始めたい人

将来に向けた資産形成を考えている方にとって、民泊は収益性と柔軟性を兼ね備えた魅力的な選択肢です。特に会社員として安定収入があるうちに副業として始めておくことで、毎月のキャッシュフローを増やしながら資産を積み上げていけます。
民泊運営によって得られる収益は、生活費の補填だけでなく、次の投資への原資にもなります。たとえば、民泊で得た利益を貯めて頭金に回せば、将来的に不動産の購入やリフォーム資金としても活用できます。このように、段階的な資産形成戦略がとれるのも大きな利点です。
また、副業として取り組むことで、万が一利益が出なかった場合でも、本業によって生活基盤が確保されているため、精神的な負担を抑えることができます。小さく始めてスキルと経験を積みながら、将来の選択肢を広げたい人には特に向いているでしょう。
おもてなしや人との交流が苦にならない人
民泊は、ただ部屋を貸すだけのビジネスではありません。宿泊者が快適に過ごせるように配慮したり、地域の魅力を伝えたりすることで、リピーターや高評価レビューにつながります。そのため、ホスピタリティ精神がある人や、人と接することに抵抗がない人にとっては、やりがいを感じやすい副業です。
たとえば、近隣のおすすめ飲食店や観光地の情報を伝えるだけでも、ゲストの満足度は大きく変わります。英語や中国語などの語学スキルがある方であれば、外国人旅行者との交流もスムーズに進み、より高い評価を得られる可能性も高まります。
もちろん、直接のやりとりが苦手な場合は、無人チェックインや代行業者の活用も可能です。しかし「自分のおもてなしでゲストに喜んでもらえる」ことに価値を感じるタイプの人には、民泊はとても適したフィールドといえます。
自分のペースで事業を育てたい人
民泊は、スタート時点で必ずしも大きな規模や高い売上を目指す必要はありません。副業としてスモールスタートし、自分の生活スタイルや本業の状況にあわせて、少しずつ運営を広げていける柔軟さがあります。
たとえば、最初は1室のみで運用を始め、需要の手応えを感じたら2室・3室と増やしていく方法も可能です。また、自主管理から始めて、手が回らなくなってきたら代行業者に一部業務を委託するなど、自分の負担に応じたステップアップもできます。
このように、事業成長のスピードや方向性を自分でコントロールできるのが、民泊の大きな魅力です。「将来的には本業にしたいけれど、まずは副業として少しずつ…」といった計画を持つ方にとって、最適な副業の一つといえるでしょう。
まとめ|民泊副業は“正しい始め方”が成功の分かれ道
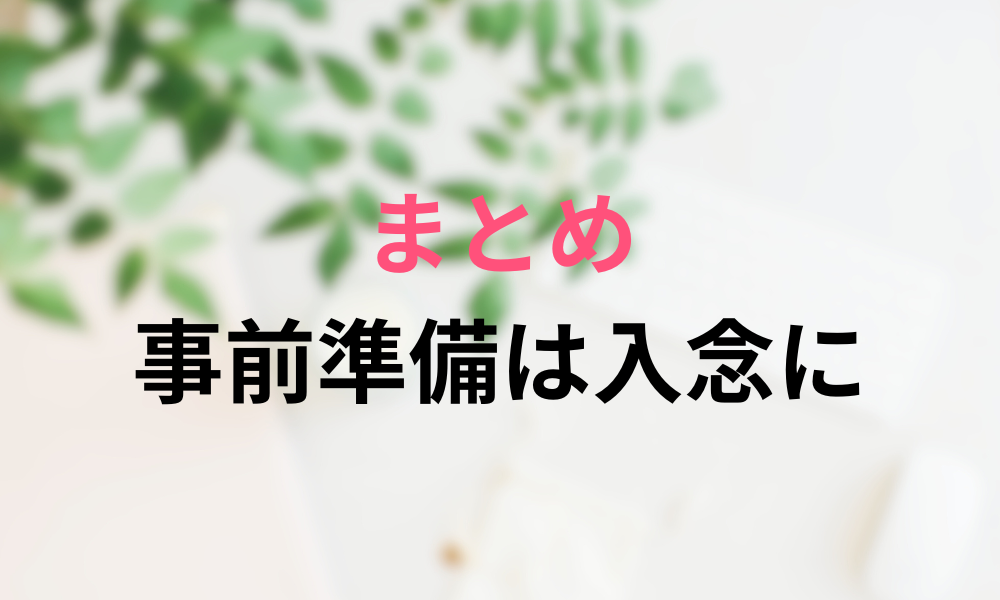
民泊は、副業としてのハードルが比較的低く、工夫次第で大きな収益を狙える魅力的なビジネスです。ただし、収益を得るまでの過程には、物件の選定、法律の確認、集客の工夫、運営の効率化など、取り組むべきことが数多くあります。
特にサラリーマンの副業として取り組む場合、限られた時間のなかで「何を外注し、何を自分でやるか」を取捨選択することが重要です。すべてを自分でこなそうとすると、時間も労力も足りなくなり、本業にも支障が出かねません。反対に、初期段階から代行業者や自動化ツールを取り入れることで、月に数時間の運用で安定収益を確保できる可能性もあります。
また、民泊ビジネスに限らずですが、はじめの事業計画や収益モデルの把握が重要です。初期費用がいくらかかるのか、毎月の必要稼働率は何%か、利益が出るまでに何ヶ月かかるのかを具体化する必要があります。これらを曖昧なまま始めると、短期で撤退せざるを得なくなることも少なくありません。
逆に言えば、こうした準備をしっかり行えば、民泊は継続的なストック型収入をもたらしてくれる強力な資産になります。立ち上げた物件が毎月自動的にお金を生み出し、2軒目、3軒目と拡大していくことで、将来的には本業の収入を超えるような副収入に育てることも十分に可能です。
民泊には法律の知識や手続きの手間など、独特の難しさがあるのも事実です。しかし、それらを避けずにひとつずつ乗り越えていくことで、「誰でも始められるけれど、正しく続けられる人が少ない」という市場の特性を味方につけることができます。
まずはひとつ、興味のあるエリアで小さくスタートし、運営を通じて得た経験やデータをもとに、次の一歩を検討する。このように「試しながら学ぶ」ことができるのは、民泊の大きな魅力です。
将来の資産づくりに向けて、民泊という一歩を踏み出してみませんか?
