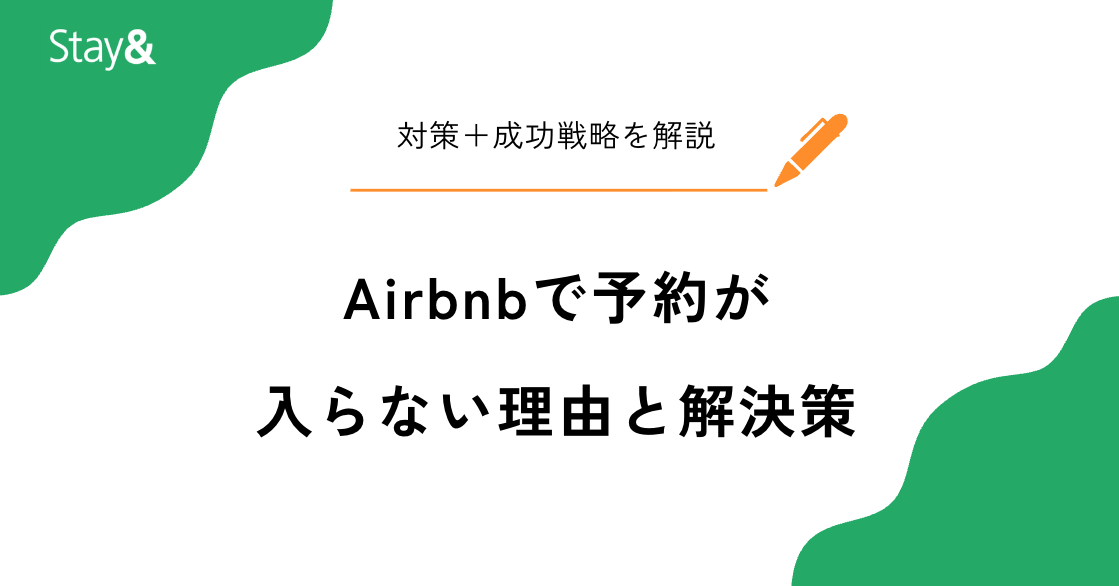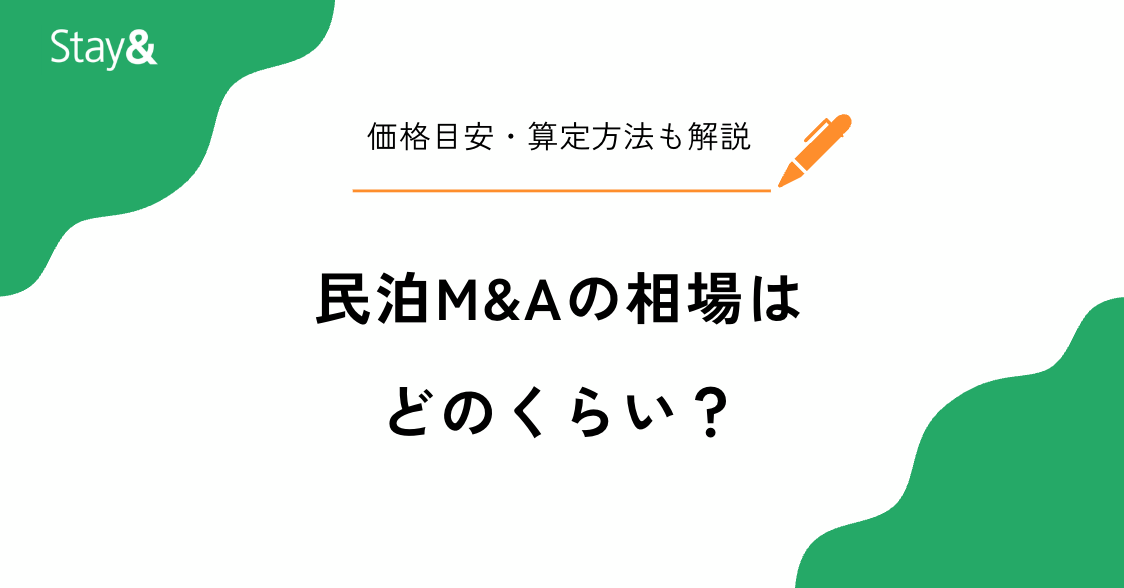民泊申請を自分でやる方法とは?流れ・必要書類、代行に依頼するメリットまで解説
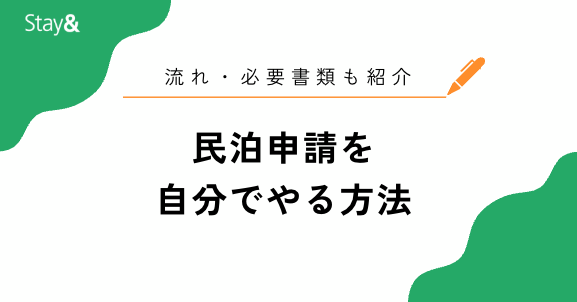
「民泊の申請って自分でできるの?」
「行政書士に頼むべき?」
この記事では、民泊申請を自分で行う方法や流れ、必要書類をわかりやすく解説します。
後半では、申請を代行に依頼するメリットや費用感についても紹介しています。
どちらが自分に合っているか判断したい方にもおすすめです。
目次
結論:民泊の申請は自分でできるの?

民泊の申請は、資格がなくても自分でできます。
実際に、多くの方が費用を抑えるために自力で申請にチャレンジしています。
ただし、始める前にまず決めるべきなのが「どの制度で運営するか」です。
民泊には以下の3つの制度があります。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):最も一般的。届出だけでOK、年180日まで営業可能。
- 旅館業法:許可が必要。365日営業できるがハードルはやや高め。
- 特区民泊:一部の自治体のみ対応。長期滞在向けに活用される。
どの制度を使えるかは、物件の場所や条件によって変わるため、まずは制度ごとの特徴を理解しておく必要があります。
民泊の申請は自分でやらずに、プロに頼むべき?
結論として、民泊の申請は「時間や労力をかけられない人」や「初期投資に余裕がある人」はプロ(行政書士など)に依頼するのが安心です。
逆に、費用をできるだけ抑えたい方や、今後も複数物件で民泊を展開したい方は、最初の1件目は自分で申請してみるのがおすすめです。
特に住宅宿泊事業法(民泊新法)は届出制で、自力でも比較的ハードルが低い制度です。
とはいえ、物件の条件や地域のルール次第では予想以上に手間がかかることもあるため、不安な部分だけ部分的にプロに相談する「ハイブリッド型」も賢い選択です。
まとめると:費用を抑えられる一方で、時間と労力は必要
民泊の申請を自分で行う最大のメリットは、費用を大きく抑えられることです。
専門家(行政書士など)に依頼すると数万円から数十万円かかることもありますが、自分で申請すればこの費用を節約できます。
一方で、法律や制度について調べたり、保健所や消防署と連絡を取り合ったりと、それなりに時間と手間がかかります。
特に初めての場合は、書類の書き方や条件の確認に膨大な時間がかかることも。
そのため、「お金を払ってでもプロに任せたい」と考える人も多くいます。
民泊の運営や手続きは手間と知識が必要になるので、専門家に任せることで安心してスタートできるというメリットがあります。
専門家に依頼したい方は「民泊の申請代行の費用はいくら?行政書士に依頼するメリットや注意点」の記事で相場や依頼方法などをチェックしましょう!
自分に向いているか判断するチェックリスト
「民泊の申請、自分でやってみようかな?」と考えている方は、以下のポイントにどれだけ当てはまるかチェックしてみてください。
- ✅ 平日の日中に役所へ行ける時間がある
- ✅ 法律や制度を調べるのが苦ではない
- ✅ 書類作成やパソコン作業に抵抗がない
- ✅ 開業費用をなるべく抑えたい
- ✅ 自分で行政や物件オーナーと交渉できる
3つ以上当てはまるなら、自力申請でも十分対応できるでしょう。
逆に、時間が取れない方や不安が多い方は、専門家に部分的に依頼するのも賢い選択です。
民泊申請を自分で行う全体の流れ【全制度共通】
民泊の申請は、制度ごとに細かい違いはありますが、基本的な流れは共通しています。
ここでは、自分で申請する場合に押さえておきたい10のステップを順を追って説明します。
最初は難しそうに感じるかもしれませんが、ひとつずつ丁寧に進めれば初心者でも十分対応できます。
①:民泊制度の種類を理解し、必要な許認可を把握する
民泊を始めるには、まず自分がどの制度を使うのかを決める必要があります。
主な制度は「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」「旅館業法(簡易宿所)」「特区民泊」の3つです。
それぞれ運営日数の上限や申請手続き、必要な設備要件が異なります。
制度を間違えると、あとで手戻りになることもあるため、まずは制度の特徴をしっかり理解しましょう。
②:民泊用途に適した物件をリサーチ・内見する【賃貸の場合】
制度の方向性が決まったら、次に重要なのが「民泊に適した物件」を探すことです。
立地や間取りはもちろん、玄関の構造や避難経路、階数、近隣との距離などもチェックポイントです。
また、現地を見ずに契約するのはリスクが高いので、必ず内見をして現状の写真や図面を取っておくのが基本です。
あとで行政に相談する際にも資料として活用できます。
③:オーナーの承諾と賃貸条件を事前に確認する【賃貸の場合】
物件が賃貸である場合は、契約前に必ずオーナーの「民泊利用の承諾」を得ておくことが重要です。
不動産会社が「民泊OK」と言っていても、オーナーが知らなかったというトラブルが後を絶ちません。
契約書に民泊利用が明記されているかも確認し、できれば承諾書を文書で残しておきましょう。
オーナーNGの場合はその時点で別物件を探す判断が必要です。
④:仮申込後、保健所に相談して設備要件を確認する
民泊物件を決めたら、契約前に保健所へ相談に行きましょう。
ここで、宿泊施設として必要な条件(キッチン・トイレ・浴室の有無、広さや換気など)をチェックしてもらいます。
保健所の担当課は市区町村によって異なる場合があるため、事前に電話やネットで「旅館業」「民泊」担当の窓口を調べてから訪問しましょう。
ここでNGが出れば契約は見送りが賢明です。
なお、このツイートにも記載がある通り、例えばその物件が東京都武蔵野市にあるのであれば「武蔵野市 保健所 旅館業(または民泊)」と検索してしっかりと場所を確認してから行きましょう。
(※ちなみに武蔵野市は旅館業と民泊新法で担当窓口が違います。)
⑤:消防署にアポを取り、必要な消防設備を確認する
保健所でOKが出たら、次は消防署へ。
民泊は宿泊施設扱いになるため、火災報知器や誘導灯など、一定の消防設備が必要です。
事前にアポを取っておかないと、担当者が外出中のことも多く、無駄足になる可能性があります。
また、消防署の担当区域は細かく分かれているので、物件の「町名・丁目」単位で担当署を調べてから連絡しましょう。
⑥:建築課で構造や用途変更の要否をチェックする
最後に、役所の建築課(または建築指導課)にて、建物の構造や用途に問題がないかを確認します。
たとえば3階建て以上の場合、旅館業では階段の区画や非常用照明が求められることがあります。
また、物件が「住宅」として登記されている場合、用途変更が必要かどうかもチェックポイントです。
図面を持参すると具体的なアドバイスが受けられます。
⑦:各行政機関からの確認が取れたら正式に契約する
保健所・消防・建築課すべてで問題がないと確認できたら、ようやく物件契約に進みます。
このステップを飛ばして先に契約してしまうと、あとから「民泊は不可だった」となり、高額な初期費用をムダにするリスクがあります。
契約は「行政確認が済んでから」が原則。
慎重に進めることで、開業後のトラブルを防ぐことができます。
⑧:必要書類を揃えて、届出または許可申請を行う
制度に応じて、住宅宿泊事業(届出制)または旅館業(許可制)の手続きを進めます。
必要な書類は、身分証明・図面・使用承諾書・設備配置図・周辺地図など。
自治体によって若干の違いがあるため、提出先のHPで確認しましょう。
また、申請書類の作成に不安があれば、行政書士に依頼するのも1つの手です。
⑨:現地調査や指導内容に対応し、開業準備を整える
申請後は現地調査が行われ、実際の物件が書類通りか、安全基準を満たしているかをチェックされます。
もし指導や改善指示があれば、それに従って修繕や設備追加を行いましょう。
ここでの対応が遅れると開業が遅れたり、許可が下りない場合もあるため、できるだけ迅速に対応することが重要です。
⑩:家具や備品を設置し、OTAなどで集客を開始する
許可が下りたら、いよいよ民泊運営のスタートです。
ベッドや寝具、アメニティ、案内用タブレットなどの備品を用意し、OTA(AirbnbやBooking.comなど)に登録して集客を始めましょう。
写真撮影や価格設定も重要なポイントです。
予約が入る前にハウスルールや清掃体制も整えておくと、トラブルの少ない運営ができます。
民泊を自分で申請するのにかかる費用と時間

ここでは制度別の費用相場、自力で進めた場合のスケジュール、そして費用を抑えるコツをご紹介します。
制度別|行政書士に依頼した場合の相場
行政書士に民泊申請を依頼する場合、制度によって相場が異なります。
住宅宿泊事業法(民泊新法)は10〜20万円ほどが一般的です。
旅館業法では構造図や消防対応が必要なため、20〜40万円ほどかかるケースもあります。
特区民泊は申請先が多く、住民説明や消防届出の代行も含めて30万円以上になることも。
費用は物件の規模や地域によっても変動するため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
専門家に依頼したい方は「民泊の申請代行の費用はいくら?行政書士に依頼するメリットや注意点」の記事で相場や依頼方法などをチェックしましょう!
自力で申請した場合のコストとスケジュール例
自分で民泊申請を行う場合、かかる費用は主に「証明書の発行費用」「図面の印刷」「郵送代」など、数千円〜数万円程度です。
ただし、時間的コストは意外と大きく、情報収集や行政とのやりとり、書類作成に20〜40時間ほどかかることもあります。
民泊新法なら書類が少なく、オンライン申請も可能なため比較的短期間で完了しますが、旅館業法などは1ヶ月以上かかるケースもあります。
コストを抑えるための工夫とポイント
費用を抑えるためには「自分でできることは自分でやる」という方針が有効です。
たとえば、間取り図は不動産業者の「マイソク」をコピーして使い、手書きで必要な情報を加えればOK。
消防との相談も自分で行えば、届出代行の費用も節約できます。
また、申請前に自治体のHPで必要書類をリスト化しておくと、二度手間が防げます。
完全に自力でやるのが不安な場合は、「図面作成だけ外注」など部分的な依頼もおすすめです。
民泊申請でよくあるトラブルと未然に防ぐためのポイント
民泊申請は手順さえ理解すれば自分でもできますが、進める中で思わぬトラブルにぶつかることもあります。
とくに物件選びや書類の確認不足が原因で、あとから「申請できない物件だった」と発覚するケースが多いです。
ここでは、よくある4つの失敗例と、それを未然に防ぐためのポイントをご紹介します。
以下の動画で民泊開業における注意点などをプロ目線で解説しているので、以下の動画でリアルな話をチェックしてみてください!
用途地域や登記の不適合でNGになる
民泊申請で意外と多いのが、物件が「そもそも営業できない場所」に建っていたというケースです。
用途地域(例:第一種低層住居専用地域)では旅館業の許可が下りないことがあります。
また、登記上の建物用途が「倉庫」や「事務所」になっていると、民泊用途として認められないことも。
事前に登記事項証明書を取得し、用途地域も市区町村で確認しておくと安心です。
管理規約で民泊禁止とされていた
マンションやアパートなどの集合住宅では、管理規約で民泊を禁止しているケースが多く見られます。
たとえ法的に届出できても、規約違反になれば営業停止やトラブルの原因に。
申請前に管理規約を取り寄せて、「宿泊事業」や「営利目的の使用」が禁止されていないかを必ずチェックしましょう。
不明な場合は管理組合に直接確認するのも有効です。
大家・管理会社の承諾が得られないケース
賃貸物件で民泊を始める場合、大家さんや管理会社から「民泊OK」の承諾をもらう必要があります。
しかし、騒音やマナーの悪い宿泊者への不安から、断られるケースも少なくありません。
口頭ではなく、書面で「転貸承諾書」をもらうのが基本です。
交渉時には、清掃やゲスト管理体制をきちんと説明するなど、信頼を得る努力も大切です。
消防設備の設置で数十万円の追加費用発生
物件によっては、民泊営業のために消火器・誘導灯・火災報知器などの消防設備を新たに設置しなければならず、想定外の出費につながることがあります。
とくに一戸建ての場合は、建築時に消防対策が施されていないため注意が必要です。
申請前に必ず消防署に相談し、どの設備が必要かを確認してから費用を見積もることで、余計な出費を防げます。
【Q&A】民泊申請を自分でやる際によく質問

Q1. 副業でもできる?勤め先にバレない?
民泊は副業として行うことも可能です。
ただし、勤務先が副業を禁止している場合は注意が必要です。
また、届出時に公的な機関へ氏名や住所を提出するため、完全に「バレない」ようにするのは難しい場合もあります。
報酬があれば確定申告も必要なので、会社員の方は事前に就業規則を確認しておきましょう。
Q2. マンションでも民泊できる?
マンションで民泊を行う場合は、建物の「管理規約」によって可否が決まるのが一般的です。
法律上は届出ができても、管理組合が「民泊禁止」としている場合は、運営することはできません。
また、マンションのような区分所有建物では近隣住民とのトラブルが起こりやすいため、事前に管理規約をよく確認し、可能であれば管理組合にも相談しておくのが一般的です
Q3. 申請後にNGになったらどうなる?
もし申請した後に不備があったり、条件を満たしていないことが分かった場合は、修正や再提出を求められます。
すぐに不許可になるわけではないので安心してください。
特に民泊新法では「届出制」のため、形式が整っていれば基本的に受理されますが、旅館業や特区民泊では審査があるため、事前相談と下準備が重要です。
Q4. 複数物件を同時に申請できる?
はい、複数の物件を同時に申請することは可能です。
ただし、物件ごとに必要な書類や条件が異なるため、1件ずつ丁寧に準備する必要があります。
また、住宅宿泊管理業者に委託する場合や、自身が家主不在型で運営する場合は、物件数が増えるほど管理体制にも注意が必要です。
最初は1件ずつ確実に進めるのが安心です。
まとめ|民泊申請は自分でもできる!成功の鍵は「準備と確認」
民泊の申請は、正しいステップを踏めば初心者でも自分で行うことが可能です。
特に民泊新法を使えば、届出制で比較的スムーズに始められるのが大きな魅力です。
ただし、物件の条件や地域ルールによっては難易度が高くなるケースもあるため、申請前の準備と事前相談がとても大切です。