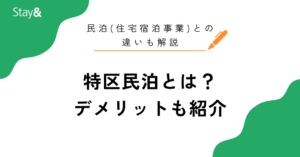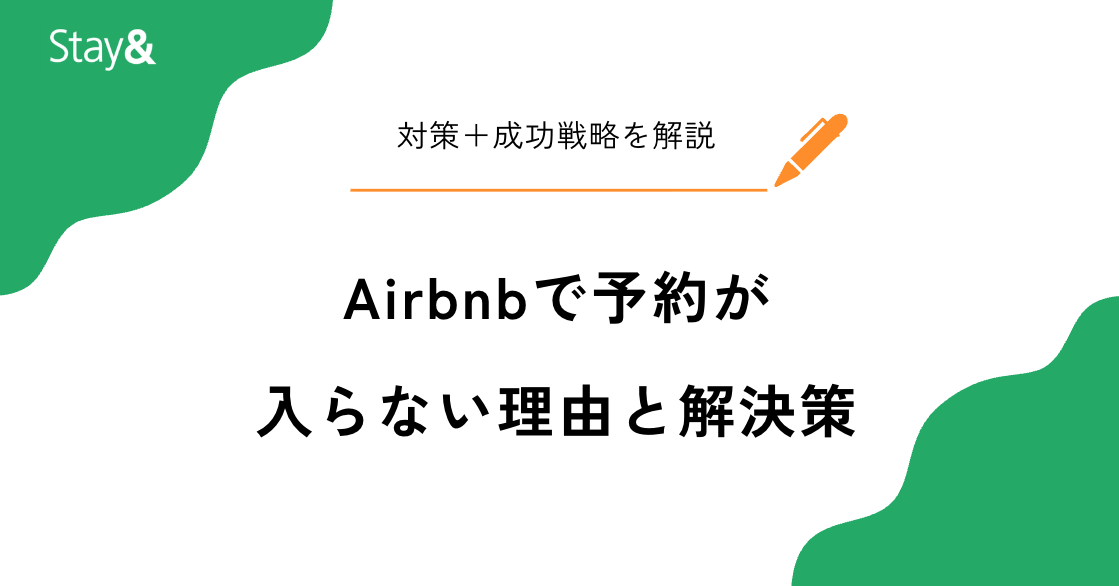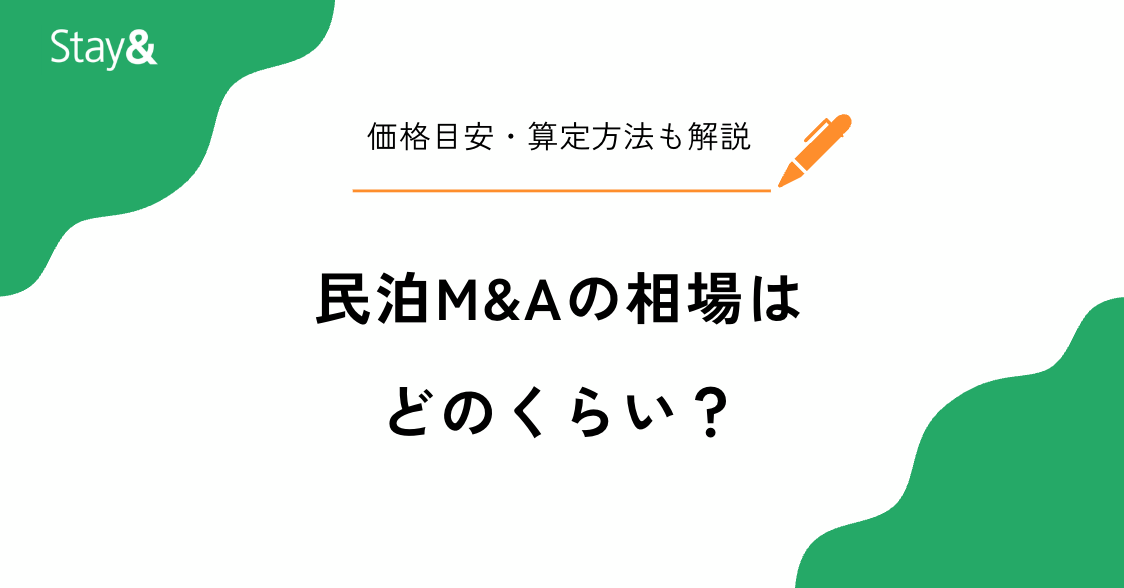民泊とは?ゼロからわかる3つの制度の特徴とホテル・旅館との違いも解説
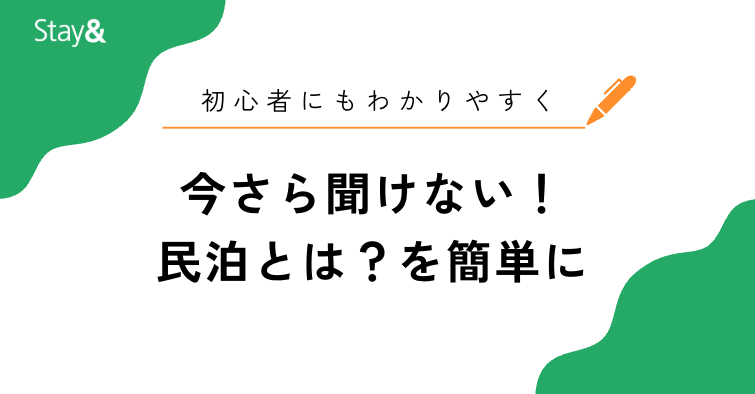
「民泊ってそもそも何?」「ホテルとの違いは?」と疑問に思ったことはありませんか?
近年、Airbnbをはじめとする民泊サービスが広まり、観光や副業として注目を集めている「民泊」。
実は民泊には法律で定められた3つの制度があり、それぞれ運営ルールや始めやすさが異なります。
この記事では、初心者でもゼロから理解できるように、「民泊とは何か?」という基本から、住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の制度の違い、さらにホテルや旅館との違いまで、わかりやすく解説します。
これから民泊を利用したい方も、運営に興味がある方も、ぜひ参考にしてください。
目次
民泊とは?初心者にもわかりやすく解説

民泊とは、自宅や空き家、マンションの一室などを使って、旅行者などに宿泊場所を提供するサービスのことです。
もともとはAirbnbのようなプラットフォームを通じて広まった仕組みで、ホテルや旅館とは異なり、一般の住宅を活用する点が特徴です。
日本では法律の整備が進み、「住宅宿泊事業法(新法民泊)」をはじめとした制度のもとで合法的に運営できるようになっています。
副業や空き家活用の手段としても注目されています。
投資目線で民泊について知りたい方は「民泊投資とは?利回りやメリット、リスクまでわかりやすく解説」の記事をご覧ください。
民泊とホテル・旅館との違い
民泊とホテル・旅館の大きな違いは、「営業の形態」と「宿泊施設の種類」にあります。
ホテルや旅館は主に観光業者や法人が運営し、専用の施設を使って営業するのに対し、民泊は個人が自宅などの住宅を使って運営するケースが一般的です。
また、民泊では食事の提供がない場合が多く、無人チェックインなど簡素なサービスになることも。
価格は民泊の方が割安なことが多く、地域性や個性を重視した宿泊体験を楽しめる点も異なります。
民宿とはどう違う?その定義と法的な違い
「民泊」と「民宿」は、どちらも“民家に泊まる”という点では似ていますが、法律や運営の方法には大きな違いがあります。
民宿は、旅館業法に基づいて許可を受けた正式な宿泊施設で、「簡単な旅館」といったイメージです。主に観光客向けに、継続して宿泊サービスを提供しています。
民泊は、空き家や自宅の一部を使って、短期間だけ泊めるスタイルです。年間の営業日数に制限があったり、届出だけで始められる場合もあります。より自由で柔軟な運営が特徴です。
まとめると:
- 民宿は、常に営業する本格的な宿泊施設
- 民泊は、柔軟で手軽に運営できるスタイル
という違いがあります。
民泊は誰が運営している?
民泊は大きく分けて「個人」と「法人」のどちらでも運営可能です。
副業として自宅の空き部屋を貸す個人もいれば、複数の物件を管理して本格的にビジネス化している法人もあります。
最近では、不動産投資家や企業が物件を取得して民泊専用として運用するケースも増加中です。
また、物件の管理や運営を代行する「民泊運営代行業者」に依頼することで、オーナーが現地にいなくても運営できる仕組みも整っています。
民泊にはどんな制度がある?3つの民泊制度を比較してわかりやすく解説
ひとくちに「民泊」と言っても、実は日本では法律によって異なる3つの制度に分類されています。
それぞれに特徴や条件、申請方法があり、目的や物件の場所によって適した制度は変わってきます。
ここでは、「簡易宿所型民泊(旅館業法)」「特区民泊(国家戦略特区)」「新法民泊(住宅宿泊事業法)」の3種類について、初心者でもわかりやすく比較・解説します。
現在、日本の法律では以下の3つの制度に分かれています。
① 簡易宿所型民泊(旅館業法に基づく)
このタイプは旅館やホテルと同じ「宿泊業」として営業許可を取得する民泊です。
簡易宿所として分類され、許可取得は難しいものの、営業日数の制限がないのが大きな魅力です。
- 旅館・ホテルと同じく許可制
- 年間の営業日数に制限なし
- ホテル並の設備が必要(例:最低床面積3.3㎡/人以上)
- 収益性は高いが、ハードルも高い
② 特区民泊(国家戦略特区に基づく民泊)
国家戦略特区に指定された地域のみで認められる制度です。
条例で民泊が可能とされた地域に限り、特定の条件を満たすことで運営が可能です。
申請のハードルは比較的低めですが、地域制限や最低宿泊日数のルールがあります。
- 特定地域のみ(例:東京都大田区、大阪市など)
- 条例に基づいた認定申請が必要
- 宿泊日数は2泊3日以上
- 外国人向けサービスや言語対応などの条件も
③ 新法民泊(住宅宿泊事業法による届出制民泊)
2018年に施行された新しい法律によって生まれた制度で、最も手軽に始められる民泊の形です。
オンラインでの届出のみで運営できるため、副業やお試し運営にも適しています。
ただし、年間営業日数は180日以内という制限があります。
- 2018年施行。届出制で簡単に始めやすい
- 年間180日以内の営業制限あり
- 住宅専用地域でもOK
- 不在時は管理業者の委託が必要
どの民泊制度を選べばいい?民泊の3つの制度の比較表
民泊には複数の制度があり、それぞれに向き・不向きがあります。
大切なのは、自分の目的と物件の条件に合った制度を選ぶことです。
以下の表では、民泊の3つの制度(新法民泊・特区民泊・簡易宿所型)の違いを、許可の取得方法・営業日数・対象エリア・必要設備などの観点から比較しています。
| 項目 | 新法民泊 (住宅宿泊事業法) | 特区民泊 (国家戦略特別区域) | 簡易宿所型 (旅館業法) |
|---|---|---|---|
| 所管省庁 | 観光庁・国土交通省 | 内閣府(+自治体) | 厚生労働省 |
| 許可・届出方法 | オンライン届出 | 自治体への認定申請 | 保健所に営業許可申請 |
| 営業日数制限 | 年間180日まで | 制限なし | 制限なし |
| 宿泊日数の下限 | 1泊2日〜 | 2泊3日以上 | 1泊2日〜 |
| 営業可能エリア | 全国(条例により制限あり) | 特定の特区エリアのみ | 全国(住居専用地域は不可) |
| 物件要件 | 住宅 | 住宅・マンション可 | 旅館・ホテル基準の設備 |
| 最低床面積 | 3.3㎡/人 | 原則25㎡/1室 | 3.3㎡/人(自治体による) |
| 管理業者の必要性 | 家主不在時は必要 | 原則不要 | 不要 |
| 消防・衛生設備 | 必要(簡易基準) | 必要(地域による) | 必要(旅館業基準) |
| 開始までの難易度 | 低(最も簡単) | 中(認定次第) | 高(審査・設備要件あり) |
| おすすめの人 | 副業で気軽に始めたい人 | 特区エリアで柔軟に運営したい人 | 本格的に宿泊ビジネスをしたい人 |
「まずは副業で気軽に始めたい」という人には、新法民泊(住宅宿泊事業法)がおすすめです。
オンラインで届出すれば始められ、マンションの一室などでも運営が可能。営業日数は年間180日以内と制限がありますが、初期費用も比較的少なく、リスクを抑えてスタートできます。
一方、「しっかり稼ぎたい」「空き家をフル活用したい」という人は、簡易宿所型(旅館業法)が適しています。営業日数の制限がなく、本格的な宿泊ビジネスとして運営できますが、設備要件や許可申請のハードルはやや高めです。
また、特区エリア(例:大田区・大阪市など)に物件がある場合は、特区民泊という選択肢もあります。2泊3日以上などの条件がありますが、認定手続きは比較的簡単で、営業日数の制限もありません。
このように、どの制度を選ぶかで運営の自由度や収益性が変わってきます。
「目的」「地域」「物件の条件」をもとに、無理のないスタイルを選びましょう!
民泊の利用者視点|宿泊したい人向け情報

民泊を宿泊者として利用する際は、予約方法・選び方・注意点を理解しておくことで、安心して利用できます。
特に初めて利用する人は、以下のポイントを押さえておきましょう。
民泊の予約方法(Airbnbなど)
民泊の予約は、AirbnbやBooking.comなどの専用サイトやアプリを使って簡単に行えます。
希望のエリアや日程を入力すると、条件に合った民泊物件が一覧で表示され、写真や設備内容、料金、レビューなどを確認できます。
気に入った物件があれば、そのままオンラインで予約・決済が完了。
チェックイン方法は物件ごとに異なり、現地での鍵の受け渡しや、暗証番号を使った無人チェックインなどがあります。
民泊を選ぶメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ホテルよりも価格が安いことが多い | 施設の質にばらつきがある |
| キッチンや洗濯機など生活設備が充実 | スタッフが常駐していない場合がある |
| 現地の生活をよりリアルに体験できる | 予約時にルールやレビューの確認が必須 |
民泊はコスパよく、現地の雰囲気を楽しみたい人におすすめですが、施設の質や対応は物件ごとに差があるため、事前の確認が重要です。
宿泊時のルールや注意点
民泊では、宿泊者として守るべきルールがいくつかあります。
例えば、「騒音を出さない」「ゴミの分別」「近隣住民への配慮」など、一般的なマナーが求められます。
また、ホストが提示しているハウスルール(喫煙NG、ペット不可など)には必ず従う必要があります。
チェックイン・チェックアウトの時間や、緊急時の連絡方法も事前に確認しておきましょう。
トラブル回避のためにも、予約前にレビューや注意事項をしっかり読むことが大切です。
民泊の運営者視点|始めたい人向け情報
民泊は、副業や空き家活用としても人気のビジネスです。
個人でも始めやすいですが、制度や費用をしっかり把握しておくことで大きな失敗を防げます。
個人で民泊を始めることはできる?
個人でも民泊を始めることは可能です。
特に「住宅宿泊事業法(新法民泊)」を利用すれば、自宅の空き部屋などを活用して比較的手軽にスタートできます。
ただし、届出や設備の整備など一定のルールを守る必要があるため、自治体や専門家への事前相談がおすすめです。
副業として空き部屋を貸し出したい人や、将来的に不動産運用を考えている人にも人気の選択肢となっています。
民泊の収益モデルと稼げる仕組み
民泊の収益は、宿泊料から清掃費・運営コスト・手数料などを差し引いた残りが利益となります。
1泊ごとの宿泊単価や稼働率に応じて収入が変動するため、立地や物件の魅力が非常に重要です。
都市部や観光地では高い稼働率が見込めますが、競合も多いため差別化がカギです。
また、自分で運営せずに代行業者を使えば、手間を抑えつつ収益化が可能です。
副業レベルから本格的な投資対象まで、幅広いスタイルで展開できます。
始めるために必要な手続きと費用
民泊を始めるには、まず対象物件が法律上の条件を満たしているか確認が必要です。
その上で、住宅宿泊事業の届出(または旅館業の許可)を行い、消防設備や衛生面の基準も整えます。
費用は、物件取得やリフォーム、備品購入、申請書類作成などで数十万〜百万円以上かかることもあります。
できるだけ費用を抑えたい場合は、自宅の一部を使って小規模にスタートする方法が現実的です。
民泊に関するよくある質問(FAQ)
民泊に関してよくある疑問を以下に簡潔にまとめました。
民泊は副業でもできる?
はい、民泊は副業としても可能です。
特に「住宅宿泊事業法(新法民泊)」では、年間180日以内の営業制限があるため、本業と並行して運営するケースが多く見られます。
自宅の空き部屋を使って収益化したい人にとっては、リスクを抑えて始めやすいのが特徴です。
ただし、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
近所で民泊をしているのは合法?
民泊が合法かどうかは、物件の場所や運営の仕方、届け出の有無によって異なります。
合法的に民泊を行うには、「住宅宿泊事業法」や「旅館業法」などの制度に沿った届け出・許可が必要です。
近所で民泊をしている場合も、きちんと届出を出していれば合法ですが、無届けで運営していれば違法となる可能性もあります。
気になる場合は、自治体や保健所に確認することも可能です。
民泊でトラブルになったらどうする?
民泊でのトラブルには、騒音やゴミ出し、設備の破損などがよくあります。
利用者側としては、ハウスルールを守り、事前にレビューを確認して信頼できるホストを選ぶことが大切です。
もしトラブルが起きた場合は、予約サイト(例:Airbnb)のサポートセンターやホストに速やかに連絡しましょう。
また、保険に加入している物件も多く、対応してもらえるケースもあります。
まとめ|民泊とは結局なにか?
民泊とは、空き部屋や住宅を活用して、旅行者に短期間の宿泊サービスを提供する仕組みです。
ホテルとは違い、地域の暮らしに近い体験ができる点や、比較的リーズナブルに泊まれる点が特徴です。
法律の整備が進んだ今では、合法的に運営するルールも整い、副業や不動産活用として注目されています。
これから民泊を利用したい人も始めたい人も、仕組みや制度を正しく理解し、安全で安心な活用を心がけましょう。