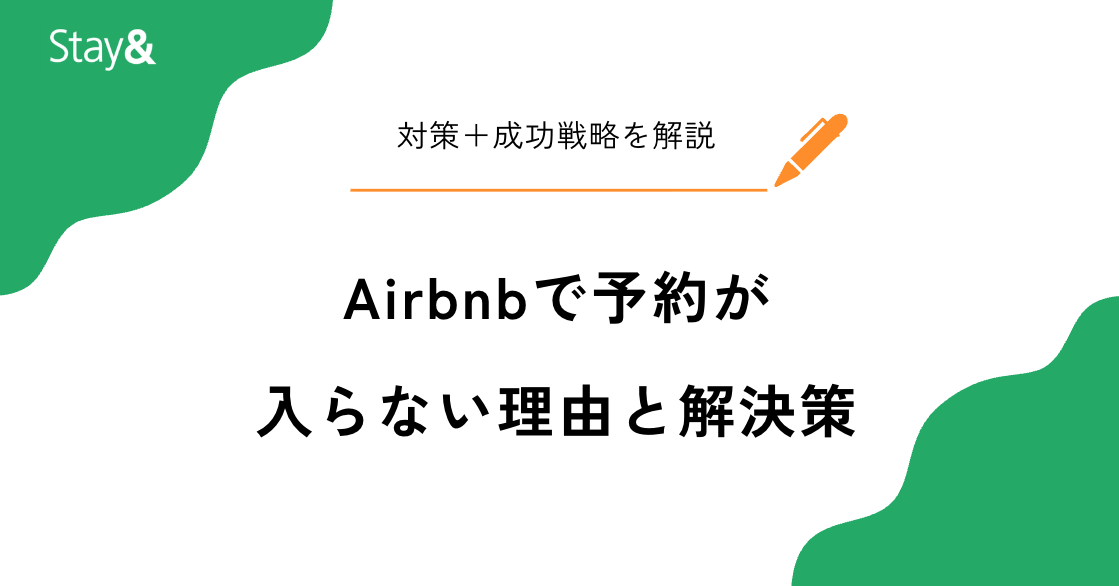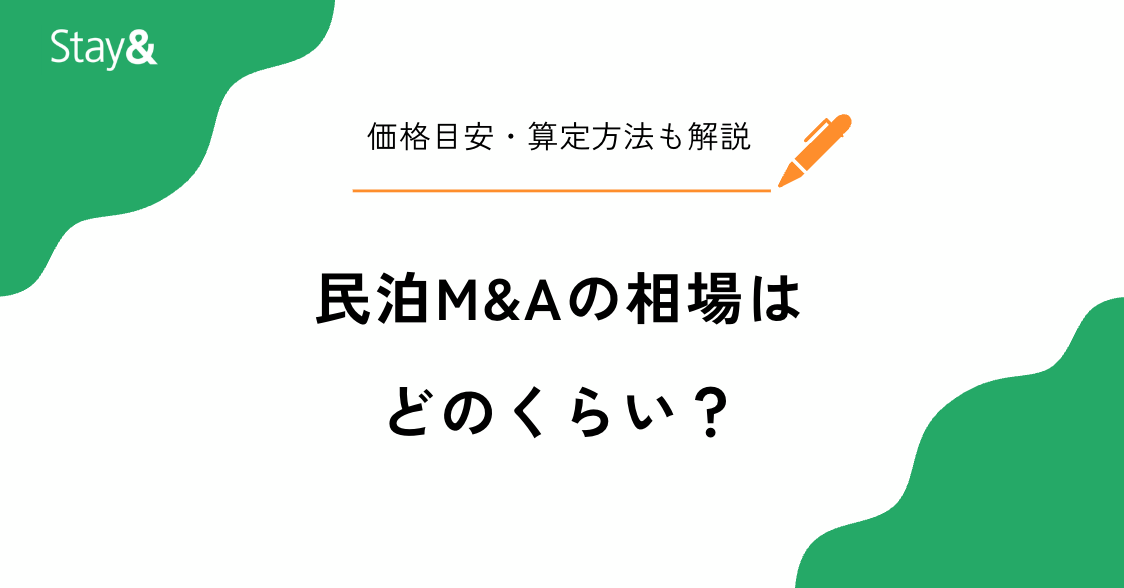無許可の民泊は違法?罰則や通報の仕方・注意点まで徹底解説
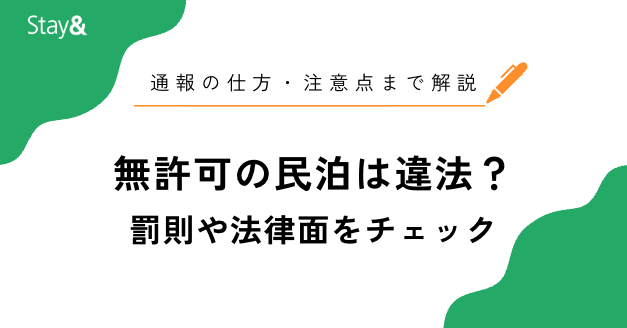
民泊ビジネスは副業や不動産活用として人気が高まっていますが、法律を正しく理解せずに始めると、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
特に「無許可での民泊運営」は明確に違法であり、罰則の対象にもなります。
この記事では、無許可民泊がなぜ違法なのか、どのような罰則を受けるのかを分かりやすく解説します。
なお、民泊申請のやり方は「民泊申請を自分でやる方法とは?流れ・必要書類、代行に依頼するメリット」の記事で解説しています。
目次
無許可民泊は明確に「違法」【法的根拠と結論】
無許可で民泊を行うことは、法律に違反しているため、明確に「違法」です。
民泊を始めるには、「旅館業法」または「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて、許可を取るか、届け出をする必要があります。
この手続きをしないまま宿泊料をもらって営業すると、旅館業法違反となり、罰則(罰金や処罰など)を受けることになります。
「少しだけなら大丈夫だろう」と思って無許可で営業すると、犯罪として罰せられるおそれがあるので非常に危険です。
たとえ短期間・一部屋のみの貸し出しでも、条件に該当すれば違法と判断されるため注意が必要です。
旅館業法・民泊新法・特区民泊のいずれにも該当しない営業は違法
民泊を合法的に運営するには、次のいずれかの法制度に基づく手続きが必要です。
- 「旅館業法の許可」
- 「住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出」
- 「特区民泊の認定」
このいずれにも該当しない民泊は、法律上“無許可営業”と見なされ、違法となります。
たとえ短期的な貸し出しでも対象になるため、十分注意が必要です。
「宿泊料を取って泊める=許可が必須」という大原則
人に宿泊させてお金をもらう行為は、基本的に「営業」とみなされます。
これには個人が自宅を一部貸すケースも含まれます。
つまり「宿泊料を取って泊める」行為には、必ず許可や届出が必要です。
この原則を知らずに無許可で民泊を始めてしまうと、後に重大なトラブルや罰則を受けるリスクがあります。
無許可民泊に科される罰則一覧【知らないと危険】

「知らなかった」では済まされないのが民泊の法律。
無許可で民泊を運営していた場合、厳しい罰則が科される可能性があります。
この章では、代表的な罰則をわかりやすく紹介しますので、自分の運営が該当していないか、確認しておきましょう。
最大100万円の罰金 or 懲役6ヶ月:旅館業法第10条違反
無許可で民泊を運営すると、旅館業法第10条違反として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」、またはその両方が科される可能性があります。
以前は3万円以下の罰金に過ぎませんでしたが、法改正により大幅に罰則が強化されました。
違法民泊の摘発数も増加しており、安易な無許可営業は非常に危険です。
宿泊名簿不備・虚偽申請:50万円以下の罰金
宿泊者の情報を正しく記録しなかった場合や、虚偽の情報で届出・申請をした場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
名簿には氏名、住所、職業、宿泊日などの正確な情報が必要で、特に外国人宿泊者の場合はパスポート番号や写しの保存も義務付けられています。
立入検査の拒否・虚偽報告:50万円以下の罰金対象
行政による立入検査を拒否したり、虚偽の報告を行ったりした場合も、50万円以下の罰金対象となります。
特に最近では、無許可民泊に対しても立入調査が可能になり、行政の監視体制が強化されています。
正しく運営していないと、思わぬ形で調査を受けるリスクがあるため注意が必要です。
事例でわかる:実際に摘発された無許可民泊のケース

無許可民泊は、実際に摘発・罰則が科されたケースが複数存在します。
この章では、警告を無視して営業を続けた結果逮捕された事例や、苦情により閉鎖された集合住宅民泊のケース、罰則強化前後の処分の違いを取り上げます。
都内で10回警告を無視し逮捕された事例
東京都では、無許可で民泊を運営していた業者が、保健所から10回にわたる警告を無視し続けた結果、旅館業法違反で逮捕されたケースがありました。
この事業者は複数の物件を無届で運用し続けていたことが発覚し、簡易裁判所により罰金処分を受けました。
これは「知らなかった」では済まされない典型例です。
苦情が殺到した集合住宅型民泊の閉鎖例
集合住宅での無許可民泊が原因で、近隣住民から苦情が殺到し、管理組合の要請により民泊が閉鎖された事例も多数あります。
苦情の内容は、深夜の騒音、ゴミの放置、不審者の出入りなど。
こうした問題が放置されると、住民トラブルに発展し、物件の評価や資産価値にも影響を与える恐れがあります。
罰金3万円から100万円へ:過去と現在の処分の違い
以前は、無許可民泊に対する罰則は「3万円以下の罰金」程度と軽微でしたが、法改正により現在では「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に強化されています。
また、立入検査や虚偽申請に対しても罰則が適用されるようになり、違法民泊への取り締まりが年々厳しくなっていることがわかります。
トラブルの実態:無許可民泊が引き起こす社会問題

無許可民泊は単なる違法営業にとどまらず、地域社会に深刻なトラブルを引き起こす原因にもなっています。
ここでは、近隣住民への迷惑行為、外国人との文化摩擦、災害時の対応不備、そして行政や自治体の対応について紹介します。
騒音・ゴミ・治安悪化などの近隣被害のトラブル
無許可民泊では管理が行き届かないことが多く、宿泊者による深夜の騒音やゴミの放置、不審者の出入りといった近隣トラブルが頻発しています。
こうした問題が続くと、住民の安心・安全な暮らしが脅かされ、自治会からの苦情や、最悪の場合は損害賠償に発展するケースもあります。
情報提供やマナー指導の不足によるトラブル
無許可民泊では外国人宿泊者への情報提供やマナー指導が不足しており、文化的な違いや生活習慣のズレがトラブルの原因になります。
また、災害や火災が発生した場合、避難経路の説明や緊急連絡体制が整っておらず、安全面でも大きなリスクがあります。
合法運営ではこれらの対策が義務付けられています。
住民からの苦情や自治体の対応状況
近年では、無許可民泊に関する苦情が自治体に多数寄せられており、多くの市町村が「通報窓口」や「民泊相談窓口」を設けるなどの対応を強化しています。
特に大阪市や京都市では専用の電話・メール受付体制も整っており、住民と行政が連携して違法民泊の是正に取り組んでいます。
違法民泊は通報できます!通報先と手順まとめ
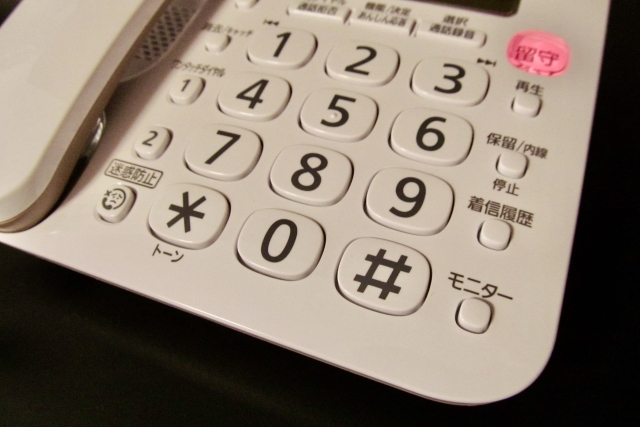
違法な民泊を発見した場合は、住民が通報することで是正につなげることができます。
現在では、全国的に保健所や専用のコールセンターが設置されており、通報手続きも簡単です。
ここでは、通報先・通報方法・匿名での通報が可能かなどを具体的に解説します。
全国共通:最寄りの保健所・国のコールセンター
違法民泊の通報は、まず最寄りの保健所に連絡するのが基本です。
また、国が設置する「民泊制度コールセンター(0570-041-389)」でも対応しており、全国どこからでも相談・通報が可能です。
コールセンターでは内容に応じて事業者への指導や自治体への引き継ぎも行われます。
大阪市・京都市など自治体の専用通報窓口
大阪市や京都市などでは、違法民泊の増加に対応するために、専用の通報窓口が整備されています。
電話・FAX・メールで24時間受付可能なケースもあり、住民が気軽に通報できる体制です。
例えば、大阪市では環境衛生監視課、京都市では「民泊通報フォーム」が活用されています。
通報は匿名でもOK?通報時に伝えるべき情報
通報は基本的に匿名でも受け付けてもらえます。
ただし、対応をスムーズに行うためには、以下の情報をできるだけ正確に伝えることが望ましいです。
- 民泊の住所や部屋番号
- 宿泊者の出入り状況(頻度・時間帯)
- 騒音やゴミなどの具体的な迷惑内容
- 写真や動画などの証拠(任意)
不安を感じた場合は、まずは相談だけでも問題ありません。
なぜ無許可民泊が後を絶たないのか?背景と構造的課題

法律で厳しく取り締まられているにもかかわらず、なぜ無許可民泊はなくならないのでしょうか?
ここでは、制度上の課題や現場でよくある問題点を取り上げ、その背景にある要因をわかりやすく整理します。
届出の煩雑さや制度理解不足が原因
無許可民泊が多い理由のひとつに、民泊の制度が複雑である点が挙げられます。
旅館業法、住宅宿泊事業法、特区民泊などの違いを理解していないまま、「とりあえず始めてしまう」ケースも少なくありません。
届出手続きや設備基準が面倒だと感じる人も多く、違法に手を出す温床となっています。
賃貸物件や分譲マンションでのルール無視
賃貸住宅や分譲マンションでは、多くの場合、契約や管理規約で民泊が禁止されています。
しかし、無許可民泊を行う一部のオーナーはこれを無視し、他人名義で運営したり、無断で貸し出すなどのケースが後を絶ちません。
こうした行為は契約違反だけでなく、法的トラブルの原因にもなります。
外国人オーナー・Airbnb未対応事例
外国人オーナーによる無許可運営や、Airbnbなどのプラットフォームで未確認のまま掲載された物件も問題視されています。
一部の外国人オーナーは日本の制度を理解せずに営業を始めてしまい、トラブルに発展するケースがあります。
また、仲介サイト側も全ての掲載物件の合法性をチェックできていないのが現状です。
合法民泊にするには?3つの法制度と選び方

民泊を合法的に運営するには、主に3つの法制度のいずれかに従う必要があります。
それぞれ営業可能な日数や手続き、対象地域に違いがあるため、自分の物件や運営目的に合わせて最適な制度を選ぶことが大切です。
旅館業法:無制限営業が可能な本格運営向け
旅館業法は、年間の営業日数に制限がなく、収益性の高い本格的な民泊運営に適しています。
ただし、施設基準や設備要件が厳しく、自治体ごとに細かな審査があるため、事業者向けの制度といえます。
旅館・ホテルと同等の許可が必要なため、事前の準備と自治体との調整が重要です。
住宅宿泊事業法(民泊新法):180日以内の簡易民泊向け
民泊新法は、自宅や空き家を活用した民泊を想定した制度です。
最大180日までの営業が可能で、オンラインまたは保健所で届出を行うことで運営ができます。
営業日数に上限があるため、副業や趣味レベルでの運営に向いています。
届出住宅には標識の掲示義務があります。
特区民泊:地域限定、日数制限なしで安定収益化も可能
特区民泊は、国家戦略特区に指定された一部地域で認められている制度です。
旅館業法の許可なしでも、認定を受ければ日数制限なく営業が可能です。
宿泊日数は2泊3日以上が基本で、条例によってはマンションの一室でも運営可能。
ただし、特区対象エリア外では利用できません。
民泊運営に必要な法的手続きと設備基準

民泊を合法的に運営するためには、単に届出を出すだけでなく、法律に基づいた正しい手続きと設備基準のクリアが必要です。
営業を始めるには?届出・標識掲示・定期報告の義務
民泊を始めるには、まず「住宅宿泊事業者」として所轄の保健所またはオンラインシステムで届出を行う必要があります。
届出が完了すると、届出番号が発行され、それを記載した標識を施設の玄関などに掲示することが義務付けられます。
さらに、営業を継続するためには、2ヶ月に1回の宿泊日数等の報告も必要です。
これらの手続きを怠ると、行政指導や罰則の対象となるため、必ず正しく行いましょう。
消防法・建築基準法に適合した設備が必要
民泊施設は、宿泊施設としての安全性を確保するために、消防法や建築基準法に適合している必要があります。
具体的には、煙感知器や消火器、避難経路の表示、非常用照明の設置などが求められます。
建物の構造や規模によっては、防火設備の追加工事が必要な場合もあります。
地域によって基準が異なるため、事前に自治体や消防署に相談し、設備が基準を満たしているかを確認することが大切です。
管理業者や仲介業者には登録義務がある
民泊の運営にあたり、管理業務や宿泊者との仲介を第三者に委託する場合、該当する業者はそれぞれ「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」として登録されている必要があります。
管理業者は国土交通大臣に、仲介業者は観光庁長官への登録が義務です。
未登録業者との取引や、無登録での運営は法律違反となり、運営者も罰則の対象になる可能性があります。
委託前に必ず登録状況を確認しましょう。
無許可民泊を避けるためのセルフチェックリスト

民泊を始める際、「知らずに違法だった」とならないよう、事前の確認が非常に重要です。
以下のチェックポイントをもとに、自分の物件や運営状況が法令に沿っているかどうかを確認しましょう。
物件は民泊OKな管理規約か
分譲マンションや賃貸物件では、管理規約や賃貸借契約で民泊が禁止されていることがあります。
「他人を泊めて収益を得る行為」は、規約違反や無断転貸に該当する可能性もあるため、まずは必ず契約書や規約を確認しましょう。
許可の明記がなければ、オーナーや管理組合への事前確認が必要です。
設備(風呂・トイレ・避難経路等)は整っているか
民泊施設には、宿泊に必要な基本設備の整備が義務づけられています。
例えば「浴室・トイレ・台所・洗面設備」が1つの敷地内にあることが条件です。
また、避難経路の表示や火災警報器の設置など、消防設備も重要です。
基準を満たしていない場合、営業許可が下りないこともあるため要注意です。
届出済みか、標識が玄関にあるか
民泊新法に基づいた届出が完了していれば、届出番号付きの標識が施設の玄関などに掲示されているはずです。
これがない場合、無許可営業の可能性が高く、通報対象になることもあります。
自分の物件に標識があるか、また定期報告などの運用ルールを守っているかも確認しましょう。
まとめ:リスクを避け、合法的に民泊を始めるために
無許可民泊は明確に違法であり、最悪の場合は逮捕や高額な罰金といった厳しい罰則が科せられます。
民泊を始める際は、「制度を理解しているか」「届出や設備は整っているか」「物件が民泊可能か」といった点を必ず確認しましょう。
適切な手続きを踏めば、民泊は収益性のある健全なビジネスとして運営できます。
ルールを守り、安心・安全な民泊運営を心がけましょう。