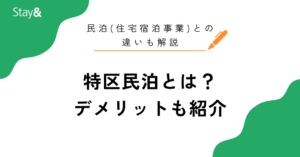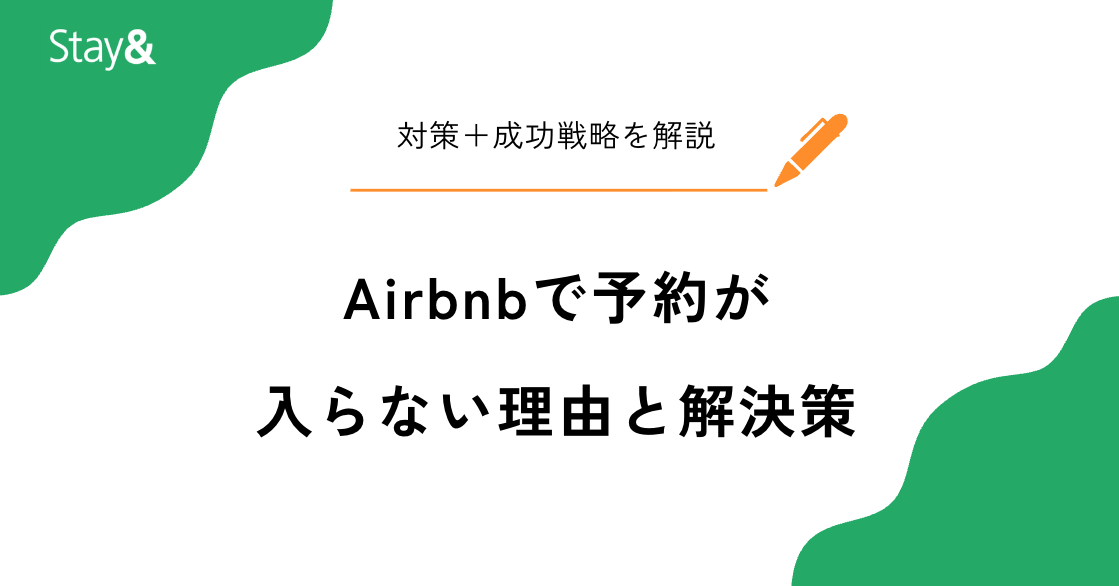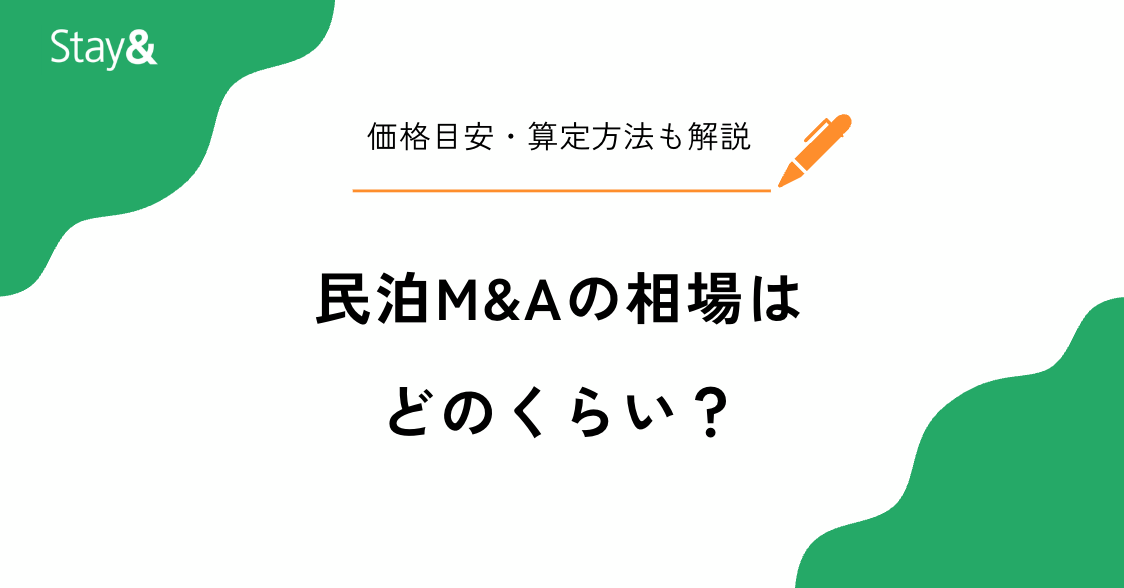民泊の上乗せ条例とは?【2026年最新版】東京23区の制限内容と対応策を徹底解説
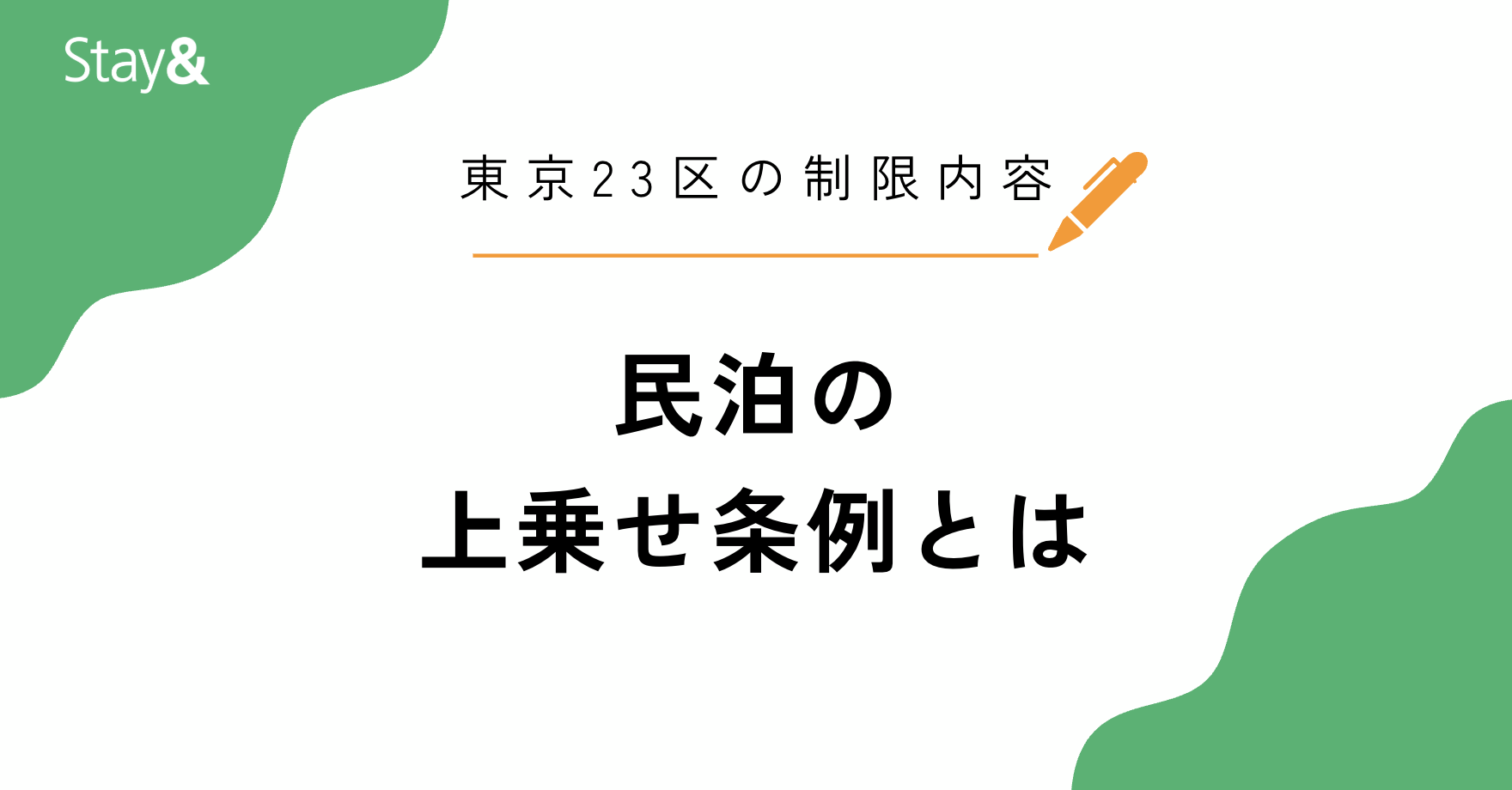
民泊を始めたいと思っても、エリアによっては営業に厳しい制限があることをご存じですか?
特に東京都23区では、国の民泊新法に加えて、各自治体が独自に定める「上乗せ条例」が存在し、営業日数やエリアに大きな差が出ます。
本記事では、上乗せ条例の基礎知識から、23区ごとの違い、対策方法までを初心者にもわかりやすく解説します。
目次
民泊の上乗せ条例とは?まずは基本から理解しよう
上乗せ条例とは、民泊新法に基づく基本ルールに、各自治体が独自に追加する規制のことです。
民泊新法では年間180日までの営業が可能とされていますが、例えば「週末のみ営業可」「文教地区は禁止」といった制限を自治体が定めることがあります。
これは地域住民の生活環境を守るための措置です。
つまり、民泊を始める際には「法律だけでなく、地域ごとの条例も必ず確認する必要がある」というのが大前提になります。
上乗せ条例の対象:どんな物件・地域に影響するのか
上乗せ条例の対象は、「すべての民泊物件」ではなく、特に住居専用地域や文教地区にある物件が中心です。
また、家主が住んでいない「家主不在型民泊」や、管理者が常駐していない場合に制限が強まることもあります。
つまり、同じ区内でも物件の所在地や運営スタイルによって、条例の適用範囲や内容が異なるのです。
事前に「用途地域」と「運営形態」の両方を調べることが、適法な運営への第一歩です。
法令 vs 条例:どちらが優先されるのか
結論から言うと、民泊運営には「法令も条例も両方守る必要がある」ため、どちらが優先という話ではありません。
民泊新法で年間180日までの営業が許可されていても、条例で「週末のみ」と決められていれば、その地域では週末のみの営業に限られます。
条例はあくまで「上乗せ」の位置づけですが、現実的にはそれが営業可能日数やエリアを決める基準となります。法令+条例=民泊のルールと理解しましょう。
【一覧比較】東京23区の上乗せ条例まとめ(2026年版)
東京23区では、区ごとに民泊の営業条件が大きく異なります。
特に「上乗せ条例」が設定されているかどうかは、運営のしやすさに直結します。
ここでは、東京23区で営業がしやすい区・厳しい区・条件によって緩和される区を整理し、最後に分かりやすい一覧表としてまとめます。
民泊をどのエリアで始めるべきか、最も効率的な判断材料になる情報を網羅的に提供します。
上乗せ条例がない区(営業しやすいエリア)
上乗せ条例がない区では、民泊新法の規定(年間180日以内)さえ守れば、特別な制限なしに営業が可能です。
2026年現在、以下の5区が該当します。
- 墨田区
- 北区
- 葛飾区
- 豊島区
- 江戸川区
これらのエリアでは手続きも比較的シンプルで、初めての民泊運営にも向いています。
ただし、家主不在型では管理業者への委託が必要な場合もあるため、詳細な確認は必須です。
週末限定・季節限定など制限が厳しい区
中央区・目黒区・荒川区などは、条例によって営業日が「週末のみ」に制限されています。
また、港区や渋谷区では「春休み・夏休み・冬休みのみ」といった季節限定の営業期間が設定されており、稼働率に大きく影響します。
こうした厳しい区では、収益を安定させるには短期集中型の運営や他の用途(マンスリーマンション)との併用など工夫が必要になります。
営業期間の少なさ=リスクと捉え、慎重なエリア選定が求められます。
家主居住型・管理者常駐で緩和されるパターン
一部の区では、家主が同居している「家主居住型」や、物件に管理者が常駐している「管理者常駐型」の場合、営業制限が緩和または撤廃されるケースがあります。
該当区の一例。
- 台東区
- 千代田区
- 港区
- 杉並区
このようなパターンを活用すれば、条例の厳しいエリアでも営業が可能になる場合があります。
営業制限に悩んでいる方は、まず運営形態の見直しを検討してみましょう。
【早見表】23区別の営業制限とポイント一覧表
以下は、2026年時点の最新情報をもとに作成した「東京23区の営業制限早見表」です。
民泊を始める場所を選ぶ際に、ひと目で確認できる参考資料としてご活用ください。
| 区名 | 上乗せ条例 | 営業制限の主な内容 |
|---|---|---|
| 墨田区 | なし | 民泊新法に準拠 |
| 中央区 | あり | 土曜正午〜月曜正午のみ |
| 目黒区 | あり | 金曜・土曜のみ |
| 港区 | あり | 季節によって制限(3期間) |
| 台東区 | あり | 管理者常駐で制限なし |
| 江戸川区 | なし | 民泊新法に準拠 |
| 渋谷区 | あり | 春・夏・秋・冬に制限期間あり |
| 豊島区 | なし | 制限なし(家主不在型は要対面確認) |
| 荒川区 | あり | 土日のみ |
自分の物件で民泊はできる?判断基準と確認方法
民泊を始める前には、物件が「営業可能なエリア」かどうかを確認することが不可欠です。
法律に適合していても、地域の条例や用途地域によっては営業ができない場合もあります。
この章では、自分の物件が民泊に向いているかどうかを判断するための具体的なチェックポイントと相談先を解説します。
まず確認すべき「用途地域」とは
民泊可能かどうかを判断するには、まず物件が所在する「用途地域」を確認しましょう。
用途地域とは、都市計画によって定められたエリア区分のことで、住宅専用地域・商業地域・工業地域などに分かれます。
特に「第一種低層住居専用地域」などの住宅系用途地域では、民泊営業に制限がかかるケースが多いです。
用途地域の確認は、各自治体の都市計画図や用途地域マップで行えます。
自治体の相談窓口・資料の見方
民泊運営を考えている物件の所在地が属する自治体には、必ず事前に相談しましょう。
多くの区では「民泊担当窓口」や「住宅宿泊事業担当課」があり、用途地域や上乗せ条例の適用範囲を詳しく教えてくれます。
また、自治体の公式サイトには民泊ガイドラインや条例資料、手続きフローなどが掲載されています。
資料の中で特に注目すべきは「制限区域」「営業可能日数」「説明会義務」などです。
事前説明や近隣対策が必要なケースとは
一部の自治体では、民泊営業前に「近隣住民への事前説明会」や「書面による周知」が義務付けられています。
例えば、文京区では営業開始の15日前までに説明会を行う必要があります。
また、管理体制や騒音への対応、ごみ出しのルールなどを事前に明確にし、トラブルが起きた場合の対応方法も整えておくことが求められます。
とくに家主が現地にいない場合は、地域の方との良好な関係づくりが重要になります。
民泊営業が制限されるパターンと具体例
東京23区では、場所や条件によって民泊営業に厳しい制限が課される場合があります。
どのようなパターンで制限されるのかを事前に知っておくことで、物件選定の失敗を防ぎ、スムーズな営業が可能になります。
ここでは、特に注意が必要なエリアや条例を具体例とともに解説します。
文教地区や住居専用地域での制限内容
文教地区や住居専用地域では、民泊営業に強い制限がかかることが多いです。
例えば、新宿区や文京区では、これらの地域においては「金曜~日曜のみ営業可」といった曜日指定の制限が導入されています。
これは静かな生活環境を守るための配慮です。
特に「文教地区」は学校や図書館など教育施設が多いため、観光客の出入りが敬遠されやすく、民泊には不向きなエリアとされています。
小学校・中学校の近くにある物件の制限
一部の区では、学校の近くにある物件に対しても民泊の制限があります。
たとえば大田区では、小・中学校から100メートル以内の物件は、月曜日から金曜日までの営業ができません。
これは、子どもの通学の安全や、落ち着いた生活環境を守るためのものです。
こうしたルールは、自治体ごとのガイドラインに書かれているので、学校の近くで物件を探すときは特に注意が必要です。
年末年始・平日営業制限など注意が必要な条例
荒川区や足立区では、週末しか営業できないだけでなく、年末年始(12月31日〜1月3日)の営業も禁止されている場合があります。
また、中央区では平日の営業自体が全面的に禁止され、「土曜正午~月曜正午」のみ営業可とする厳しいルールが設けられています。
このような時間的制限は、稼働率に直接影響するため、民泊ビジネスの採算性に大きな差が出る要因になります。
【実践編】上乗せ条例が厳しいエリアでも民泊を実現する方法
上乗せ条例が厳しくても、運営の工夫次第で民泊を実現することは可能です。
この章では、家主居住型や旅館業との併用など、制限を回避・緩和しながら合法的に民泊を行う方法を紹介します。
特に都心部や人気観光エリアで民泊を始めたい方には、実践的なノウハウとして役立ちます。
家主居住型・管理者常駐型で規制を回避する
結論として、
- 家主が同居している「家主居住型」
- 物件に管理者が常駐している「管理者常駐型」
は、条例の制限が大きく緩和されるケースが多いです。
たとえば台東区では、管理者が常駐していれば平日も営業可能です。
これは地域住民の不安(騒音・治安など)を和らげる仕組みとして、条例で優遇されているためです。
初期コストはかかりますが、長期的には営業日数を確保できる有効な対策です。
特区民泊・旅館業法とのハイブリッド運用
民泊新法だけに頼らず、「特区民泊」や「旅館業許可」とのハイブリッド運用を検討するのも有効です。
特に大田区のように国家戦略特区に指定されている地域では、特区民泊を活用することで年間営業日数の上限がなくなります。
また、条件を満たせば旅館業法での運営も可能になり、制限の厳しいエリアでも合法的かつ柔軟に営業できます。
複数制度を理解し、最適な組み合わせを選ぶことがポイントです。
営業日数を最適化して収益を上げるコツ
条例で営業日数が制限されていても、「繁忙期に集中して稼働する」ことで収益を最大化できます。
たとえば、週末や連休、花見・花火大会など観光需要が高まる時期に予約を集中的に取り込む戦略です。
また、平日はマンスリーマンションとして貸し出すなど、複数用途の使い分けも効果的。
制限を逆手に取った営業計画を立てることで、少ない日数でも高い利益を目指せます。
【Q&A】民泊の上乗せ条例に関するよくある質問
ここでは、民泊の上乗せ条例に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。
運営中の方もこれから始める方も、疑問や不安を事前に解消しておきましょう。
条例は今後変更される可能性はある?
はい、上乗せ条例は今後変更される可能性があります。
住民からの苦情や観光需要の増減など、地域の状況に応じて自治体が改定するケースがあります。
特に選挙後や観光政策の見直しタイミングで改正が行われることが多いため、定期的に自治体の公式サイトをチェックすることが大切です。
また、民泊事業者向けのメルマガやニュースリリースの登録もおすすめです。
既に届出済みでも条例が変わったらどうなる?
基本的には、新しい条例が施行された時点でその内容が適用されます。
つまり、すでに届出済みであっても、営業日数や対象地域の制限が変更される可能性があります。
多くの場合、一定の「経過措置期間」が設けられますが、その後は新ルールに従う必要があります。
継続的に合法運営を続けるためには、条例の動向を常に把握しておくことが不可欠です。
条例違反したらどうなるの?罰則は?
条例違反が発覚した場合、営業停止命令や罰金(最大100万円)などの行政処分を受ける可能性があります。
特に、無届出での営業や、住民説明を怠った場合は厳しい対応を取られる可能性も。
さらに違反情報が公開されることもあるため、物件の資産価値や信頼性にも影響が出るリスクもあります。
まとめ:上乗せ条例は民泊成功のカギ!まずは情報収集と確認から
民泊をうまく運営するには、「エリアの選び方」と「自治体ごとのルール(上乗せ条例)の理解」が大切です。
どんなに良い物件でも、営業の制限が厳しい場所では、思うように稼働しないことがあります。
まずは、検討しているエリアの用途地域や条例の内容をしっかり確認し、必要があれば自治体に相談しましょう。
また、家主が住んでいるタイプや、管理者が常駐するタイプなど、運営の形を工夫することで対応しやすくなります。
事前の情報収集と準備が、民泊の成否を大きく左右します。