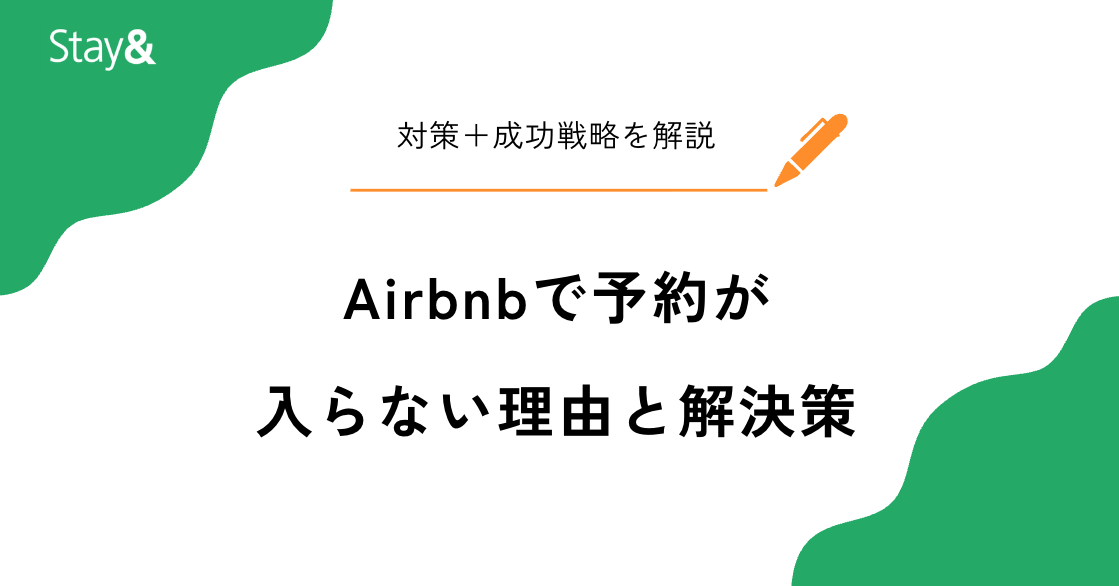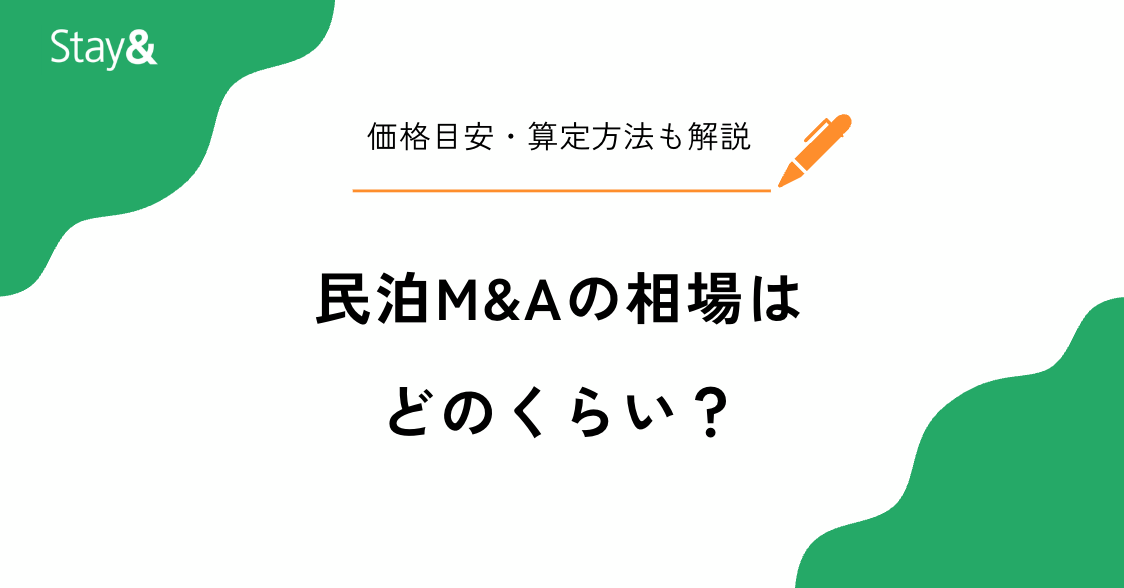一軒家で民泊許可を取る方法!法律・申請手順・費用・注意点まで網羅
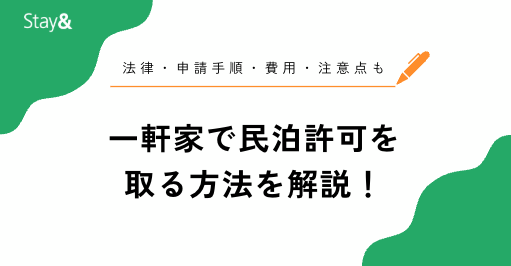
「空き家を民泊として活用したい」
「一軒家で副収入を得たい」
と考えている方に向けて、本記事では一軒家で民泊許可を取得するための方法を徹底解説します。
民泊を始めるには、法律の理解や各種申請、消防設備の整備など、押さえるべきポイントが多数あります。
この記事では、初心者でもわかりやすいように、3つの民泊制度の違い・許可申請の流れ・初期費用の目安・注意点まで、実践に役立つ情報を網羅的に紹介。
これから一軒家で民泊を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも一軒家でも民泊ってできるの?

結論から言うと、一軒家でも民泊は可能です。
民泊に関する法律やルールを守ったうえで、所定の手続きや設備を整えれば、誰でも合法的に運営できます。
特に、使っていない空き家や実家を活用したい方には、一軒家民泊は非常に相性の良い方法です。
最近では、宿泊需要の多様化やインバウンド回復の影響もあり、一棟貸しの民泊が注目を集めています。
一軒家民泊の基本と今注目されている理由
民泊とは、自宅や空き家を旅行者に貸し出し、宿泊できるようにするサービスです。
中でも「一軒家をまるごと貸す民泊」は、広くてプライベートな空間が確保しやすいため、家族やグループ旅行に人気があります。
また、2020年以降のコロナ禍で、他の人との接触を避けられる一棟貸しの需要が急増しました。
そのため、都市部だけでなく地方でも、空き家の有効活用として注目されています。
空き家や実家を活用するケースが増えている背景
近年、人口の減少や高齢化により、全国で空き家が増えています。
特に地方や郊外では、相続で受け継いだものの使い道がなく、そのまま放置されている一軒家が多く見られます。
こうした空き家を民泊として活用する例が増えているのは、維持費をまかなえるうえに、副収入も得られるからです。
さらに、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が整備されたことで、法律に沿って安心して運営できるようになったことも追い風となっています。
このように、使っていない資産を有効に活かせる点から、一軒家を使った民泊は今、注目を集めています。
賃貸でもできる?持ち家との違いとは
一軒家民泊は賃貸物件でも可能ですが、いくつかのハードルがあります。
最大の違いは「オーナーの許可が必要かどうか」です。
持ち家であれば自分の判断で民泊に転用できますが、賃貸物件の場合は貸主(オーナー)の明確な許可が必要です。
また、管理規約や契約条件によっては禁止されている場合もあります。
一方で、持ち家は自由に改装や設備の設置がしやすいのもメリットです。
とはいえ、どちらの場合も民泊を始める前には、建物の用途地域や条例、設備基準の確認が必要です。
事前に確認すべき地域ルールと制限

ここでは、一軒家で民泊を運営するうえで事前に確認すべき地域ルールと制限についてご紹介します。
用途地域によって民泊ができないケースもある
一軒家で民泊を始める場合、まず確認すべきなのが「用途地域」です。
用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた土地利用の区分で、住居専用地域や商業地域などに分類されています。
例えば、第一種低層住居専用地域では民泊営業が制限されているケースもあります。
たとえ自宅でも、「宿泊施設」としての営業が法律上できない場合があるため、建物のあるエリアの用途地域を事前に市区町村の都市計画課などで調べておきましょう。
自治体によって異なる条例のチェック方法
民泊のルールは、全国で同じではありません。
自治体ごとに決められている「民泊条例」によって、営業できる日数や、申請の受付時間、近所の人への説明が必要かどうかなどが違ってきます。
たとえば、東京都の大田区では「特区民泊」として、年間の営業日数に制限なく民泊ができますが、他の区では「新法民泊」として営業日数が制限されることもあります。
そのため、民泊を始める前には、必ずその地域のルールを確認しましょう。
自治体のホームページを見たり、住宅課・観光課・保健所などの担当窓口に電話や訪問で相談するのが確実です。
一軒家民泊にはどんな許可・準備が必要?

一軒家民泊にはどんな許可・準備が必要になるのでしょうか。
ここでは、一軒家民泊を始めるうえで必要になる許可・準備について解説します。
民泊運営には届出・認定・許可のいずれかが必要
民泊を合法的に運営するためには、「届出」「認定」「許可」のいずれかが必要です。
これは選ぶ制度によって異なります。
例えば、「民泊新法」は届出制で、比較的簡単にスタート可能です。
一方、「特区民泊」は自治体からの認定が必要で、対象エリアが限られます。
「旅館業法(簡易宿所)」の場合は正式な営業許可が必要で、基準も厳しくなります。
それぞれの制度に応じた行政手続きを理解し、正しいルートで申請を行うことが大切です。
【準備】消防設備の整備|火災報知器・誘導灯などの設置基準
民泊を始めるには、安全対策として消防設備をきちんと整える必要があります。
基本的には、すべての部屋に自動式の住宅用火災報知器を設置しなければなりません。
さらに、場合によっては誘導灯や消火器も必要になることがあります。
また、「家主が住んでいるタイプ(家主居住型)」と「住んでいないタイプ(家主不在型)」では、求められる基準が異なるため、あらかじめ管轄の消防署に相談して確認しておきましょう。
【準備】住宅設備の整備|キッチン・浴室・トイレの要件
一軒家で民泊を始めるには、宿泊する人が快適に過ごせるように、必要な住宅設備をしっかり整えることが大切です。
基本的に必要とされるのは、キッチン、浴室(またはシャワー)、トイレ、洗面台の4つです。
これらがそろっていないと、「住むための家」として認められず、民泊として営業できないこともあります。
また、設備は使いやすく、掃除しやすいものを選ぶと清潔に保ちやすくなり、宿泊者からの評価も良くなります。
【準備】家具・アメニティ・Wi-Fiなども準備しておこう
最低限の住宅設備が整ったら、次は宿泊者が快適に過ごせるように「家具やアメニティ」を準備しましょう。
ベッドや寝具、テーブル、椅子などの家具のほかに、タオル、シャンプー、ドライヤーなどの備品も必要です。
最近では、Wi-Fiの有無も宿泊者の満足度に大きく影響します。
ターゲットとなるお客様に合わせて、インテリアや設備を工夫すると、レビュー評価が上がりやすくなり、リピーターや高い稼働率につながります。
一軒家で民泊を始める7つのステップ

「一軒家を民泊として活用したいけれど、何から始めればいいのか分からない…」
そんな方のために、民泊開業の流れを7つのステップに分けて解説します。
以下の手順を順番に進めていけば、誰でもスムーズに一軒家民泊をスタートできます。
STEP1|民泊に適した一軒家かをチェックする
民泊を始めるには、まずその一軒家が民泊として使えるかどうかを確認することが大切です。
用途地域の制限、建物の構造、築年数などをチェックしましょう。
また、間取りが複数人での宿泊に向いているか、騒音トラブルが起きにくい場所かどうかも重要なポイントです。
さらに、物件が持ち家か賃貸かによっても対応が異なります。
賃貸の場合は、オーナーの許可が必要になるため、必ず事前に確認しましょう。
民泊に向いている物件を選ぶことが、スムーズに運営を始めるための第一歩です。
STEP2|どの法律で申請するかを決める(民泊新法・旅館業法・特区民泊)
民泊には「民泊新法(住宅宿泊事業法)」「旅館業法」「特区民泊」という3つの制度があります。
どの制度を使うかによって申請方法や営業日数、必要設備が異なるため、まずは自分の一軒家に合った制度を選びましょう。
- 副業や短期的な運用には→民泊新法
- 本格的に運営するなら→旅館業法
- 特定地域なら→特区民泊
が向いています。自治体のルールも合わせて確認しましょう。
STEP3|消防設備・住宅設備の準備をする
民泊を始めるには、法律に従って消防設備や住宅設備をしっかり整える必要があります。
消防設備としては、火災報知器、消火器、そして避難経路の確保が求められます。
住宅設備では、キッチン、トイレ、浴室、洗面所が最低限必要です。
施設の種類や地域によって求められる内容が異なるため、事前に消防署や保健所に相談し、必要な条件をしっかり確認しておきましょう。
これらの設備は、民泊の申請時にもチェックされる大事なポイントなので、準備を怠らずに進めることが大切です。
STEP4|自治体へ民泊の届出・許可申請を行う
必要な設備が整ったら、次は民泊運営に関する届出または許可申請を行います。
民泊新法の場合は「届出」、旅館業法では「許可申請」、特区民泊は「認定申請」が必要です。
提出書類には、建物の平面図や間取り図、使用承諾書、運営ルールなどがあります。
自治体の担当窓口に相談しながら進めることで、スムーズに手続きを完了できます。
行政書士に依頼する方法もあります。
STEP5|家具・家電・アメニティを設置して内装を整える
許可取得後は、宿泊者が快適に過ごせる空間づくりを進めましょう。
ベッドや寝具、冷暖房、冷蔵庫、洗濯機などの家電のほか、タオルやシャンプーなどのアメニティも用意しておくと親切です。
また、インテリアにこだわることで予約率が上がることも。
特に一軒家民泊は「非日常感」が求められるため、写真映えする内装に仕上げると集客にもつながります。
STEP6|プロカメラマンで写真撮影し、民泊サイトに掲載する
内装が完成したら、プロのカメラマンに依頼して写真を撮影しましょう。
写真のクオリティは予約数を左右する重要な要素です。
広角レンズで室内の広さや清潔感を伝えることができるため、スマホ撮影よりも断然おすすめです。
STEP7|運営開始
許可が下り、部屋の準備や写真撮影が完了したら、いよいよ民泊の運営をスタートできます。
まずは、AirbnbやBooking.comなどの民泊サイトに掲載し、宿泊者からの予約を受け付けましょう。
運営が始まると、問い合わせ対応・清掃手配・レビュー管理などやることが意外と多くなります。
自分で対応するのが大変な場合は、民泊運営代行サービスを活用するのも一つの手。
手数料はかかりますが、運営の手間を大きく減らせるため、初心者にもおすすめです。
【費用シミュレーション】一軒家民泊にかかるコスト

一軒家で民泊を始めるにあたり、「どれくらいお金がかかるのか?」という点は誰もが気になるポイントです。
ここでは、開業前に必要な初期費用から、運営中に発生するランニングコストまでを具体的に解説します。
費用を事前に把握することで、無理のない資金計画を立てることができ、黒字運営にもつながります。
なお、一軒家民泊の開業費用についてもっと詳しく知りたい方は「民泊一軒家の相場を徹底解説!地域別・タイプ別・開業費用まで完全網羅」の記事をご覧ください。
申請代行・図面作成などの行政関連費用
民泊を合法的に運営するためには、行政への届出や許可申請が必要です。
これらの手続きは自分で行うことも可能ですが、初めての方は行政書士などの専門家に依頼するケースが多く、その場合は申請代行費用が発生します。
相場はおおよそ10〜20万円程度。
また、間取り図や配置図などの図面作成が必要になることもあり、外注する場合はさらに2〜5万円ほどかかることがあります。
消防・住宅設備などの初期設備費用
消防署の指導に基づき、火災報知器・消火器・誘導灯などの設置が求められます。
費用は設備の種類や規模によって異なりますが、一般的に10〜30万円ほどが目安です。
さらに、浴室やトイレ、キッチンなど住宅設備が古い場合は、リフォームや設備追加が必要となり、これも最低10万円〜大規模だと300万円以上かかるケースもあります。
物件の状態次第で金額が大きく変わるため、現地調査の上で見積もりを取りましょう。
家具・内装・撮影などの運営準備費
宿泊者の満足度を左右するのが、家具や内装、アメニティ類の充実度です。
ベッドやソファ、家電製品を揃えるだけでも20〜50万円ほどかかることがあります。
さらに、インテリアコーディネートや写真映えする内装を整える費用も想定しましょう。
仕上げにプロカメラマンによる物件写真撮影(3〜5万円程度)を行うことで、予約率を高める効果が期待できます。
ランニングコスト(清掃・光熱費・代行手数料)
民泊運営には、開業後も継続的にかかる「ランニングコスト」があります。
代表的なものは、以下の通りです。
- 清掃代(1回あたり3,000〜6,000円)
- 電気・ガス・水道などの光熱費
- 運営代行会社に依頼する場合の手数料(予約額の10〜30%)
収益性を見込むには、こうした費用を事前に把握し、宿泊単価や稼働率とのバランスを考慮してシミュレーションを立てることが重要です。
押さえておきたい!民泊の3つの種類と営業スタイル

1. 旅館業法(簡易宿所型)|営業日数制限なしだが厳しい要件
旅館業法に基づく「簡易宿所型」は、営業日数に制限がなく、年間365日稼働できるのが最大のメリットです。
その分、建築基準法や消防法の要件が厳しく、通常の住宅とは異なる設備や構造が必要です。
例えば、玄関が共用ではなく専用出入口が必要だったり、窓の大きさや避難経路に条件があったりします。
家主不在型の長期運営を目指す場合に向いていますが、個人での導入ハードルはやや高めです。
2. 特区民泊|指定区域で可能な柔軟運営
「特区民泊」は、国家戦略特別区域に指定されたエリア内で認められている制度です。
東京都大田区、大阪市、北九州市など一部地域で利用可能で、旅館業法の許可がなくても、一定の要件を満たせば営業できます。
最短2泊から宿泊を受け入れられるため、インバウンド需要にも対応しやすいのが特徴です。
ただし、対応するエリアが限定されており、自治体ごとにルールや運用基準が異なる点には注意が必要です。
3. 新法民泊(住宅宿泊事業法)|最も一般的で始めやすい
2018年に施行された「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」は、一般の住宅を活用して民泊を行える制度です。
最大の特徴は、「届け出制」であること。
営業許可ではなく、要件を満たせば申請だけで始められるため、初心者にも始めやすい制度といえます。
ただし、営業日数が年間180日以内に制限されるため、フル稼働を前提とした収益化には工夫が必要です。副業や空き家活用には非常に適した制度です。
どの制度が自分の一軒家に向いている?判断基準を解説
どの民泊制度を選ぶべきかは、「物件の所在地」「住宅の構造」「運営スタイル」の3点を基準に考えると判断しやすくなります。
以下の比較表をご覧ください。
| 制度名 | 営業日数 | 対象エリア | 手続きの難易度 |
|---|---|---|---|
| 旅館業法 | 365日 | 全国 | 高(許可制) |
| 特区民泊 | 無制限(最短2泊) | 一部地域 | 中(認定制) |
| 民泊新法 | 最大180日 | 全国 | 低(届出制) |
それぞれの制度にはメリット・デメリットがありますので、物件と目的に合ったものを選びましょう。
許可ハードルが最も低いのは「民泊新法」
3つの民泊制度の中で、最も許可取得のハードルが低いのが「民泊新法(住宅宿泊事業法)」です。
旅館業法のような建築基準や構造要件が厳しくないうえ、届出制なので比較的簡単に始められます。
運営日数は180日以内に制限されますが、初めての民泊運営や副業として始めたい方にはちょうど良い制度です。
書類や設備の要件も明確で、情報も豊富なので、初心者におすすめです。
意外と多い!民泊開業の失敗例とその回避策

民泊は手軽に始められそうに見えますが、実際には「思わぬ落とし穴」がいくつもあります。
実際に民泊運営でつまずいた方の事例から、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。
初期費用が思ったより高くて赤字に…
物件があればすぐ始められると思いがちですが、実は初期費用が想定以上にかかるケースが少なくありません。
消防設備や住宅設備の整備、家具・家電の購入、写真撮影、申請書類の作成まで含めると、50万円〜100万円以上になることもあります。
事前に「初期費用の見積もり」を立てておくことが大切です。余裕のある予算を準備し、開業後の収支予測までシミュレーションしておきましょう。
近隣住民とのトラブルで運営停止のリスク
民泊トラブルで多いのが「近隣との関係悪化」です。
騒音、ゴミ出し、外国人観光客のマナー違反などが理由でクレームが入り、最悪の場合は運営中止になるケースもあります。
これを防ぐには、開業前に住民へ丁寧に説明することが大切です。
ハウスルールを明文化して掲示し、宿泊者にも徹底して守ってもらう工夫が必要です。
やることが多くて途中で挫折
民泊の開業には、物件探しから制度選び、申請書類の作成、設備準備、サイト登録など、想像以上に多くの作業があります。
「自分で全部できる」と思って始めたものの、途中で疲れて挫折してしまう人も少なくありません。
初めての方は、行政書士や民泊代行業者のサポートを活用することで、作業負担を大幅に減らすことができます。
全部を自力でやろうとせず、うまく外注するのも成功への近道です。
いい物件がなかなか見つからない
民泊に向いている一軒家は、実は意外と条件が厳しいです。
用途地域・建物構造・築年数・周辺環境・駅からの距離など、クリアすべきポイントが多いため、「理想の物件が見つからない」と悩む人も多いです。
無理に妥協して進めると、後で集客に苦労することに。
物件探しは時間をかけて慎重に行い、不動産会社に「民泊用途であること」を伝えて相談するとスムーズです。
一軒家民泊の許可申請で必ず押さえておきたいことまとめ
一軒家で民泊を始めるには、物件の条件確認から地域のルール、申請手続き、設備の整備まで、段階的に準備が必要です。
特に重要なのは「どの制度(民泊新法・旅館業法・特区民泊)で運営するか」の判断と、それに応じた適切な届出や許可の取得です。
また、消防や住宅設備の基準を満たすことで、トラブルなく運営ができます。近隣への配慮や集客の工夫も忘れずに。
基本をしっかり押さえることで、安心・安全な民泊経営が実現できます。