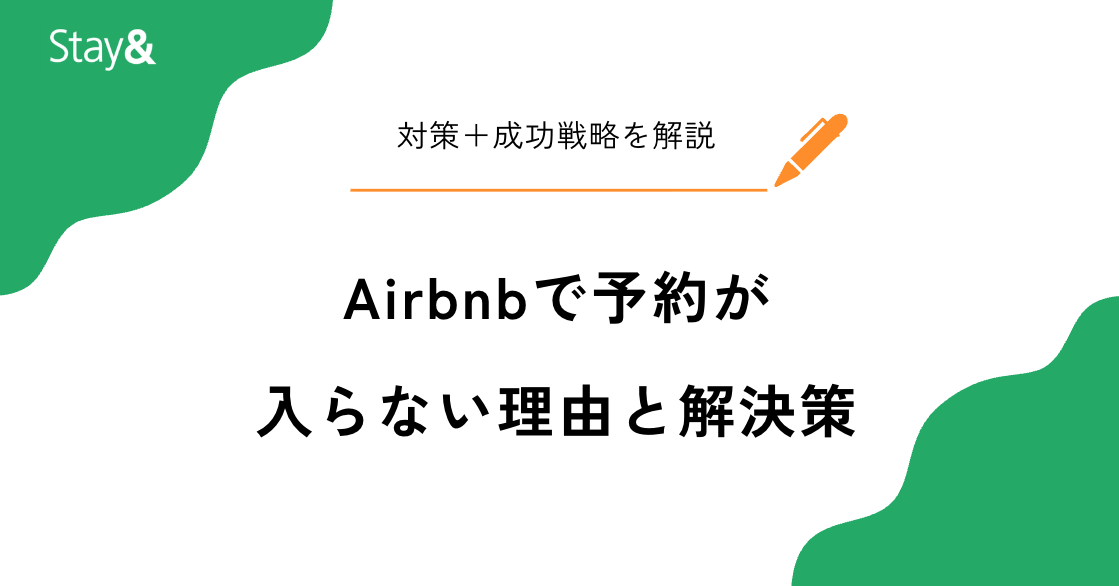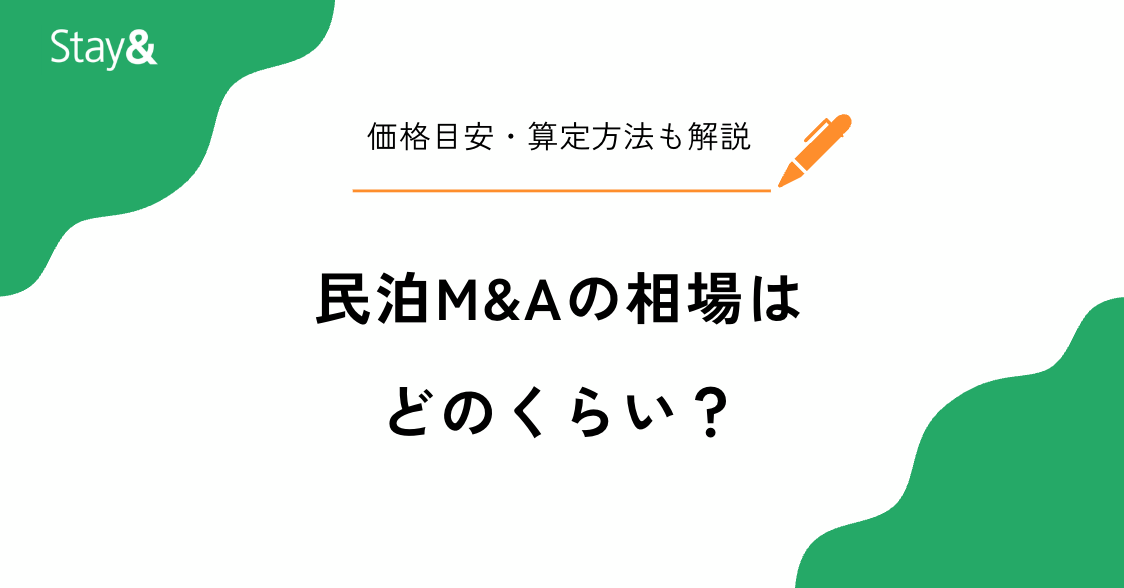田舎で民泊経営は儲かる?動画付きで徹底解説
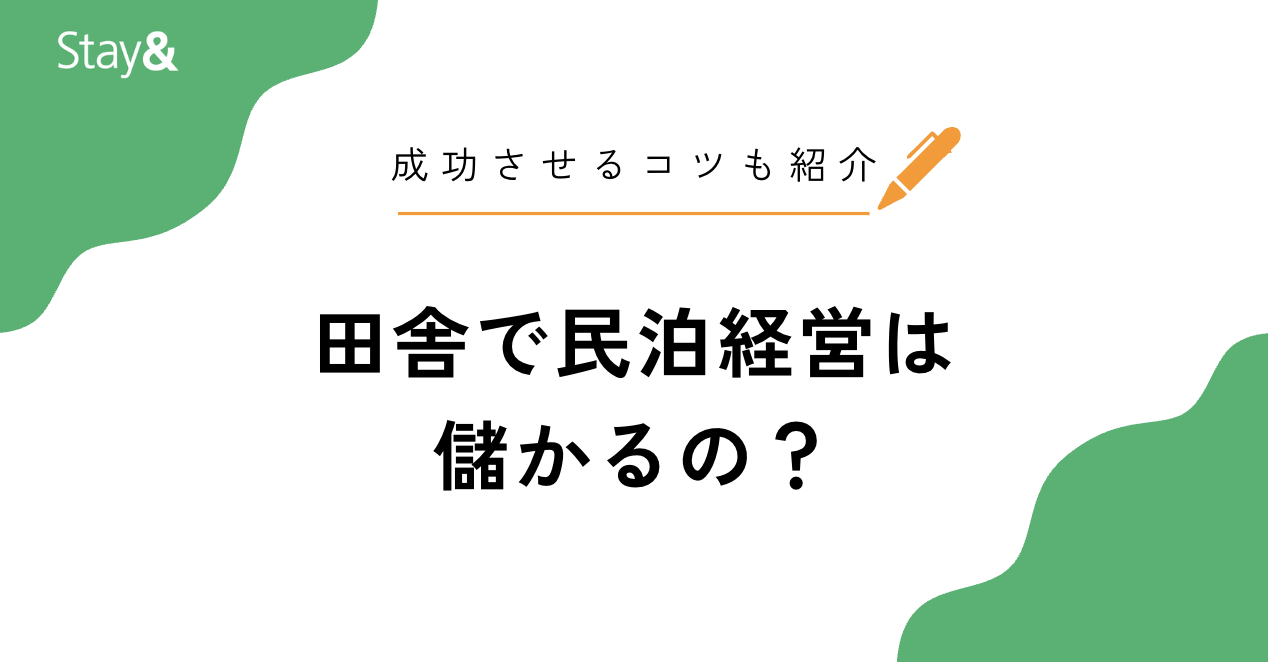
「田舎で民泊って本当に儲かるの?」そう疑問に感じる人は多いでしょう。
この記事では、田舎の民泊経営が実際に収益を上げられるのか、儲かる理由や失敗の原因、成功のコツなどを初心者にもわかりやすく解説します。
空き家を活用した副業や移住先での新しいビジネスを検討している方にも、参考になる実例や知識を盛り込みました。
目次
田舎の民泊経営は本当に儲かる?
田舎でも、やり方次第で民泊はしっかり稼げます。
初期費用が安く済み、ライバルも少ないのが大きなメリットです。
また、自然や地域ならではの体験が外国人観光客に人気です。
都会では味わえない魅力を提供すれば、少し高くてもリピーターがつきやすく、安定した収入が期待できます。
田舎の民泊が注目されている背景
田舎の民泊が注目されているのは、「空き家活用」や「地方創生」の流れが強まっているからです。
都市部では不動産価格が高くなっていますが、田舎には安く手に入る空き家や別荘地がたくさんあります。
さらに、旅行需要の回復や、外国人観光客が地方にも足を運ぶようになったことで、田舎でも民泊ビジネスが始めやすい環境が整ってきています。
都市部と田舎の民泊の違いとは?
都市部と田舎の民泊の大きな違いは、「立地」と「求められる価値」にあります。
都市部ではアクセスの良さが重視され、価格競争が激しくなりがちです。
一方で、田舎の民泊は「特別な体験」や「日常を離れた時間」を求める人が多いのが特徴です。
また、都市型の民泊はできるだけ多くの日数を稼働させて利益を出しますが、田舎型は1回ごとの料金を高めに設定したり、週末だけの運営で利益を確保するスタイルが主流です。
つまり、田舎の民泊は「量より質」で勝負するビジネスだと言えます。
実際に儲かっている事例はある?
実際にしっかりと収益を出している民泊の事例はたくさんあります。
たとえば、1泊2〜3万円の古民家民泊でも、月に10日稼働すれば月収は20〜30万円ほどになります。
さらに、地元の食材を使った料理体験や、サウナ・BBQといったオプションを追加すれば、月に50万円以上の売上を出しているケースもあります。
成功している民泊に共通するポイントは、「誰に来てほしいかがはっきりしている」「コンセプトに一貫性がある」「特別な体験を提供している」の3つです。
田舎の民泊が儲かる3つの理由

田舎での民泊経営が注目されている理由は、大きく3つあります。
- 低コストでの運営
- 競合の少なさ
- インバウンドや長期滞在ニーズの高さ
都市部と比べて費用が抑えられる上に、独自の体験を提供することで他と差別化でき、高収益につながる可能性があります。
1. 低コストで運営できる
田舎では、土地や建物の価格が安いため、物件の取得や維持にかかるコストを大きく抑えられます。
さらに、空き家を活用すれば初期費用をぐっと減らせますし、生活費や光熱費も都市部より安く済みます。
こうした点から、田舎の民泊は利益を出しやすい仕組みが整っていると言えるでしょう。
自宅や空き家の民泊開業については「【自宅や空き部屋で】民泊を始める方法!開業の流れや費用など解説」の記事で詳しく解説しています。
初期費用を抑えやすい
田舎には空き家や中古物件がたくさんあり、都市部の3分の1以下の価格で手に入ることも珍しくありません。
また、自治体の「空き家バンク」や補助金制度を利用すれば、物件の購入からリフォームまでを安く抑えられます。
開業時の費用負担を軽くできるのは、田舎で民泊を始める大きなメリットです。
ランニングコストも安い
家賃や人件費がかからない「自主管理型」の運営なら、コストを大幅に抑えられます。
さらに、固定資産税や水道光熱費も都市部より安い地域が多く、長期的に見てもコスト面で有利です。
こうした低コスト構造のおかげで、田舎の民泊は継続して黒字を出しやすいのが大きな強みです。
空き家活用には改修費がかかるケースも
ただし、空き家をそのまま使えるとは限りません。
老朽化が進んでいる場合は、屋根の修理、水回りの交換、耐震補強など、大がかりなリフォームが必要になることもあります。
そうした場合でも、補助金をうまく活用したり、自分でできる部分はDIYで対応したりすることで、費用を上手に抑える工夫が大切です。
民泊のリフォームに使える補助金については「民泊に使える補助金6選!空き家のリフォームに使える補助金まとめ【2025年最新】」の記事で詳しく紹介しています。
2. 競合が少なく検索上位が取りやすい
田舎エリアでは民泊の数が少ないため、競争があまり激しくありません。
そのぶん、AirbnbやGoogleマップなどで検索上位に表示されやすくなり、集客もしやすくなります。
さらに、SNSや口コミをうまく活用すれば、都市部のような激しい競争を避けながら、お客さんをしっかり呼び込むことができます。
3. インバウンド需要や長期滞在ニーズが高い
最近は、外国人観光客や日本のワーケーション利用者が、田舎での「特別な体験」や「ゆったりした長期滞在」を求めるようになっています。
特に、古民家や自然に囲まれた環境は、海外からの旅行者にとってとても魅力的です。
しっかりとニーズに合わせた対応をすれば、高めの料金でも十分にお客さんを集めることも可能です。
田舎民泊の収益シミュレーションと年収モデル

田舎民泊でも、運営次第で安定した収益を得ることが可能です。
特に1棟貸しや古民家型の民泊は高単価設定がしやすく、少ない稼働日でも収益化しやすい傾向にあります。
ここでは、具体的な収益モデルや繁忙期・閑散期の対策、月収・年収の目安について解説します。
収益モデル(1棟貸し・古民家タイプ)
1棟貸しや古民家タイプは、1泊あたり2万〜3万円の設定が可能で、週末稼働中心でも十分収益が見込めます。
例えば月10日稼働で1泊25,000円なら、月収は25万円。
さらに体験型オプション(農業体験・BBQなど)を加えることで、月収30万円以上も狙えます。
繁忙期と閑散期をどう乗り切る?
田舎の民泊では、ゴールデンウィーク・夏休み・年末年始などの繁忙期にしっかり稼ぐことがとても大切です。
一方で、閑散期には「長期滞在プラン」や「ワーケーション向けの設備・サービス」、「地元の人向けの割引」などで稼働率を上げる工夫が効果的です。
また、季節ごとに柔軟に料金を調整する価格戦略も、安定した収益を出すための重要なポイントです。
月収・年収のリアルな目安とは?
田舎の民泊経営では、しっかり運営すれば月収20〜40万円、年収300〜500万円が現実的です。
特に週末+繁忙期中心の稼働でも、1泊単価が高ければ利益は十分出せます。
副業としても本業としても成立可能なビジネスモデルです。
田舎民泊の開業に必要な費用と内訳
田舎で民泊を始める際には、物件取得費やリフォーム費、家具・家電の準備費用などの初期投資が必要です。
加えて、月々のランニングコストも考慮しましょう。
ここでは、開業にかかる主な費用と、コストを抑えるためのポイントをご紹介します。
初期費用(物件取得・リフォーム・家具)
初期費用は大きく分けて「物件取得」「改修・リフォーム」「家具・家電・備品」の3つに分類されます。
空き家を活用する場合、物件取得費を数十万円に抑えられることも。
ただしリフォーム費用は、100〜300万円程度かかる場合もあります。
詳しくは「民泊を始める際の初期費用はいくらくらい?【リアルな金額を公開】」の記事をご覧ください。
運用コスト(月々の経費)
毎月発生する費用には、水道光熱費、通信費、消耗品代、清掃費、OTAへの手数料などがあります。
特にプロパンガスのエリアでは光熱費が高くなる点に注意。
一般的な1棟貸し民泊での月間ランニングコストは5〜10万円程度が目安です。
初期費用を抑えるコツ
費用を抑えるコツは、「空き家バンク」や自治体の補助金制度を活用することです。
また、DIYできる部分は自分で改修する、家具は中古やリースを利用するなども有効です。
初期投資を抑えられれば、黒字化までの期間を短縮できます。
民泊経営でよくある失敗と原因

民泊経営は収益性の高いビジネスですが、事前準備が不十分なまま始めると失敗するリスクもあります。
特に田舎の場合、立地や価格設定、差別化の甘さが直接的に経営を圧迫します。
ここでは、実際によくある失敗例とその原因を分かりやすく解説します。
観光需要のないエリアで開業してしまう
需要がない地域で民泊を始めても、どれだけ設備を整えても予約はなかなか入りません。
そのため、周辺に観光地や自然の魅力、イベントなどがあるかどうかを事前にしっかり調べることが大切です。
特に田舎では、「その場所自体が目的地になるかどうか」が成功のポイントになります。
地元の観光協会の情報なども上手に活用して、需要のある場所かを見極めましょう。
他施設と差別化できていない
「どこにでもある宿」では、なかなか選んでもらえません。
たとえば、古民家風のデザイン、ペットOK、地元の体験ができるなど、はっきりとしたコンセプトが必要です。
写真・説明文・サービス内容のすべてで「この宿ならではの魅力」をしっかり伝えないと、他と差別化できずに価格競争に巻き込まれ、利益を出すのが難しくなってしまいます。
価格設定を誤っている
価格を安くしすぎると利益が出ず、高すぎると予約が入りません。
民泊新法の180日制限も踏まえ、必要売上から逆算した価格設定が重要です。
また、繁忙期・閑散期の料金差をつける「ダイナミックプライシング」も導入すると、利益を最大化しやすくなります。
収益計画が甘く赤字になる
稼働率や単価を理想値で見積もると、現実とのギャップで赤字になりやすいです。
「最悪でも月○泊できれば黒字」という保守的なシミュレーションを作っておくことが大切です。
また、定期的な見直しと、実績に基づく再計算も必要です。
初期費用をかけすぎた
立派な内装や最新設備を整えても、投資額に見合った収益が出なければ意味がありません。
高級志向の施設を作るなら、それに見合うターゲットと価格設定が必要です。
逆に、安価に提供するなら費用を極力抑えるべきです。
費用対効果の視点を忘れないようにしましょう。
清掃や運営を丸投げしすぎる
すべての業務を代行会社に任せてしまうと、その分コストがかかり、利益が減ってしまいます。
さらに、オーナー自身が現場の状況を把握していないと、サービスの質が下がり、リピーターが離れてしまう原因にもなります。
掃除などの雑務は外注しても構いませんが、戦略やサービスの質の管理は自分でしっかり行う意識が大切です。
田舎民泊を成功させるための7つの戦略

田舎の民泊は“戦略次第”で大きく収益性が変わります。
都会のような立地の強みがなくても、体験価値や地域性を活かすことで十分に勝負できます。
ここでは、地方でも民泊を成功させるために重要な7つの戦略を紹介します。
ターゲットを明確にする
最初に「誰に泊まってもらいたいか」を明確に決めることで、施設の雰囲気・サービス内容・料金設定などに一貫性を持たせることができます。
たとえば、「子連れの家族」「外国人観光客」「若いカップル」では、求める体験や設備がまったく違います。
民泊を成功させるには、まずターゲットをしっかり決めることが出発点になります。
地域に根ざした体験コンテンツを用意する
田舎民泊の強みは“地域でしかできない体験”を提供できることです。
農業体験、郷土料理づくり、森林ウォークなど、宿泊以外の魅力を作ることで口コミやリピートにつながります。
観光地が少ない場所でも“体験”があれば十分勝負可能です。
季節ごとの魅力を打ち出す
田舎は四季の変化が豊かで、それぞれ違う楽しみ方があります。
春はお花見、夏は川遊び、秋は紅葉狩り、冬は雪景色やこたつ体験など、季節に合わせた打ち出し方で集客が安定します。
季節ごとのイベントやキャンペーンも有効です。
SNS・口コミ・OTAサイトをフル活用する
田舎民泊の集客は「見つけてもらう」ことが第一歩です。
Instagramでの発信や、Airbnb・じゃらんなどのOTA(宿泊予約サイト)を活用して、多角的に露出を高めましょう。
良い口コミがつけば、自動的に予約が増える仕組みも作れます。
地元との連携を強化する
地域の商店、観光協会、農家、イベント団体などと連携することで、宿泊以上の価値を提供できます。
また、地元の理解や協力があると、トラブル回避や信頼構築にもつながります。
地域ぐるみの民泊経営が、今後ますます重要になります。
オフシーズン対策を講じる
閑散期に予約が減るのは避けられませんが、
- 長期滞在割引
- ワーケーション向けプラン
- おこもりステイ
などの割引やキャンペーンを積極的に取り入れることで、稼働率を保つことができます。
大切なのは、ただ安くするのではなく、「ここで過ごす価値」をしっかり提案することです。
価格よりも体験や過ごし方の魅力を伝えることが、選ばれるポイントになります。
リピーター戦略を組み立てる
新規顧客を獲得するより、リピーターを増やすほうが費用対効果が高く、経営も安定します。
たとえば「再訪割引」や「LINE登録での特典」、「滞在後のフォローメール」などを活用して、お客さんとのつながりを継続させる工夫が大切です。
また、サービスの質を保ちつつ、あたたかみのある対応をすることも、リピートにつながる大きなポイントです。
民泊運営に必要な許可と法律の違い
民泊を合法的に運営するには、運営スタイルに合わせた「許可」または「届出」が必要です。
日本では主に以下の3つの制度があります。
- 特区民泊
- 住宅宿泊事業(民泊新法)
- 旅館業法(簡易宿所など)
それぞれ営業日数や設備要件が異なるため、どの制度を使うかを正しく選ぶことが、スムーズな開業と安定した運営には欠かせません。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
住宅宿泊事業法、通称「民泊新法」は、個人でも比較的簡単に民泊を始められる制度です。
180日以内の営業日数制限がありますが、住宅地でも運営が可能で、届出制のためハードルが低いのが特徴です。
副業や週末運営に向いています。
旅館業法による簡易宿所との違い
旅館業法の「簡易宿所」許可を取得すれば、営業日数に制限なく年中営業が可能になります。
ただし、客室面積やフロント設置などの施設要件が厳しく、許可取得のハードルは高めです。
事業として本格的に民泊を行いたい場合に適しています。
特区民泊とは何か
特区民泊は、国家戦略特区に指定された一部の地域だけで認められている制度です。
民泊新法よりも自由度が高く、2泊3日以上の宿泊から営業が可能で、営業日数の制限もありません。
そのため、特区内であれば比較的柔軟に民泊運営ができます。
ただし、利用できるエリアが限られている点には注意が必要です。
それぞれのメリット・デメリットを比較
| 制度 | 営業日数 | 取得難易度 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 民泊新法 | 年間180日まで | 低(届出制) | 副業・週末運営向き |
| 旅館業法(簡易宿所) | 制限なし | 中〜高(許可制) | 本業として収益化したい人 |
| 特区民泊 | 制限なし(2泊以上) | 中(地域により異なる) | 特区内で自由に運営したい人 |
制度ごとの違いを理解し、自分の運営スタイルに合ったものを選ぶことが、トラブルを避ける第一歩です。
田舎の民泊で使える補助金・融資制度

田舎で民泊を始める際には、資金調達手段として「ローン」と「補助金・助成金」の両面から検討するのが効果的です。
これらをうまく活用することで、初期負担を抑えてスムーズに開業できます。
民泊向けローン(不動産投資ローン/事業用ローン)
民泊専用ローンや事業用ローンを活用すれば、初期費用の大部分をカバーできます。
不動産投資ローンは物件購入向け、事業用ローンはリフォーム費用や設備購入にも使えます。
金融機関によって条件が異なるため、事前に相談・比較が大切です。
自治体の補助金・助成金
多くの自治体では、「空き家改修補助金」「観光振興補助金」など、地域振興を目的とした補助制度があります。
工事費の1/2〜2/3を補助してくれるケースも。
自治体のホームページや商工会を通じて情報収集すると見つけやすいです。
民泊のリフォームに使える補助金については「民泊に使える補助金6選!空き家のリフォームに使える補助金まとめ【2025年最新】」の記事をご覧ください。
補助金を使うときの注意点
補助金は「事前申請」が原則で、手続きを怠ると受給できません。
また、対象となる経費や条件が細かく決まっているため、必ず交付要綱を確認しましょう。
書類作成や写真提出などの事務作業も多いため、早めの準備が必要です。
田舎の民泊経営の始め方ステップガイド

田舎で民泊を始めるには、しっかりとした計画と段階的な準備が必要です。
ここでは、初心者でも安心して取り組めるよう、開業までのステップを6つに分けて分かりやすく解説します。
エリア・物件の選定
まずは「観光資源があるか」「アクセスは良いか」「競合は多いか」といった観点からエリアを選びます。
その後、空き家バンクや地元不動産で民泊向きの物件を探します。
現地調査と将来の需要予測がポイントです。
ターゲットとコンセプトを設計
まずは、誰に泊まってほしいのか(例:外国人旅行者、子連れ家族、ワーケーション層など)をはっきりさせることが大切です。
そのうえで、そのターゲットに響くコンセプトを考えましょう。
たとえば、「古民家×地元体験」や「山奥で静かに読書できる宿」など、他にはない“独自のテーマ”を持たせることがポイントです。
こうした個性あるコンセプトがあると、宿の魅力が伝わりやすく、選ばれる理由にもつながります。
必要設備の準備と改修
ChatGPT:ターゲットに合わせた設備を整えることが大切です。
たとえば、ファミリー向けならキッチンや洗濯機があると便利ですし、外国人向けならWi-Fiや英語表記の案内が必要になります。
どの層を狙うにしても、清潔感と快適さは絶対に欠かせない基本です。
DIYを取り入れるなどして、リフォームや改装のコストを上手に抑える工夫もしていきましょう。
許認可の取得
民泊を始める前には、「住宅宿泊事業(民泊新法)」や「旅館業法」などに基づいた、適切な許可や届出が必要です。
また、地域によっては自治体の条例が厳しい場合もあるため、トラブルを防ぐためにも、事前に管轄の保健所や自治体の窓口に相談することがとても大切です。
OTA・SNSでの集客準備
Airbnbや楽天トラベルなどのOTA(予約サイト)に掲載することで、民泊の集客がスタートします。
その際、写真や紹介文のクオリティはとても重要です。第一印象で「泊まってみたい」と思わせることがポイントです。
さらに、InstagramやGoogleマップへの登録、そして口コミを書いてもらう仕組みづくりもしておくと、より効果的に集客できます。
運営開始〜レビュー対応までの流れ
開業後は、予約管理・清掃・ゲスト対応が日常的な業務になります。
特に大切なのが、最初の数件のレビューです。ここでの評価が今後の集客に大きく影響します。
そのため、丁寧な接客と清潔な環境の維持を心がけましょう。良いレビューが増えてくると、自然と予約も増えていきます。
田舎で民泊を始めるときの注意点

田舎での民泊経営は魅力的ですが、都市部とは異なる注意点があります。
ここでは、田舎で民泊を始めるときの注意点をご紹介します。
自治体ごとに独自の条例や制限が設けられている
民泊の営業ルールは全国一律ではなく、自治体ごとに独自の条例や制限が設けられていることがあります。
たとえば、ある地域では営業日数に上限があったり、住宅地での営業が禁止されている場合もあります。
そのため、開業前には必ず自治体の窓口や保健所に相談し、最新のルールを確認することが大切です。
近隣住民とのトラブルに発展することも
田舎では地域のつながりが強く、住民同士の距離も近いため、民泊に対する理解がないまま運営を始めると、思わぬトラブルにつながることがあります。
そのため、開業前に近隣へのあいさつ回りをする、ゴミ出しや騒音などのマナーをゲストにしっかり伝えるといった配慮がとても大切です。
地域との信頼関係を築くことが、安心して民泊を続けていくための土台になります。
田舎特有のインフラ課題(ガス・水道・清掃など)
田舎の民泊では、都市部に比べてインフラが整っていないケースが多く、あらかじめ確認しておくべきポイントがいくつもあります。
たとえば、
- プロパンガスによる光熱費の高さ
- 井戸水や浄化槽の定期メンテナンス
- ゴミ処理場までの距離と運搬手段
など、日々の運営に関わるコストや手間が発生します。
また、清掃業者が見つかりにくい地域もあるため、自主管理や地元の人との協力体制を検討するなど、柔軟な運営方法を考える必要があります。
よくある質問(FAQ)
ここでは、田舎での民泊経営を検討している方からよく寄せられる疑問にお答えします。
Q. 田舎で民泊をやって本当に儲かりますか?
はい、正しい戦略を立てて運営すれば、田舎でもしっかりと利益を出すことは十分に可能です。
特に、
- 空き家を活用して初期費用を抑えられること
- 競合が少ないこと
- インバウンド需要の広がり
などが、大きな強みになります。
Q. 観光地じゃなくても需要はありますか?
観光地でなくても、「体験価値」や「非日常の空間」を提供できれば、十分に需要はあります。
たとえば、農業体験ができる宿、古民家でのんびり過ごせる宿、自然に囲まれた静かな滞在など、都市では味わえない魅力があればOKです。
こうした魅力があると、長期滞在やリピーターを呼び込むことも十分に可能です。
Q. 開業までにかかる期間は?
かかる期間は物件の状態や取得する許可の種類によって変わりますが、早ければ1〜2ヶ月、平均的には3〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。
物件選び、リフォーム、許認可の手続き、集客の準備など、いくつものステップがあるため、時間に余裕をもって計画を立てることが大切です。
Q. 代行を使えば手間は減らせますか?
はい、清掃やゲスト対応、予約管理を代行業者に依頼すれば、手間を大幅に減らすことが可能です。
ただし、すべてを任せきりにするとコストがかさみ、利益率が下がることも。
自分で対応すべき部分と外注すべき部分を明確にすることが大切です。
Q. 失敗しないために気をつけるべきことは?
最も重要なのは、「需要のあるエリアを選ぶこと」と「ターゲットに合った施設をつくること」です。
また、最初から大きく投資しすぎたり、収益を楽観視しすぎるのも避けたほうがいいでしょう。
まずは小さく始めて、実際の運営を通じて課題を見つけ、少しずつ改善していくスタイルがおすすめです。
まとめ:田舎民泊は戦略次第で十分に儲かる!

田舎での民泊経営は、都市部とは違った難しさがある一方で、大きなチャンスも広がっています。
空き家をうまく活用し、地域ならではの自然や文化を取り入れた「体験価値」を提供すること。
そして、収益の見通しをしっかり立てることが、事業を安定して続けていくために欠かせません。
この記事で紹介したポイントを押さえながら戦略的に取り組めば、田舎でも十分に利益を出すことができます。
まずは小さく始めて、経験を積みながら一歩ずつ進めていきましょう。
民泊経営のように不動産を活用して収益を得る方法は、ほかにもさまざまあります。
特に最近は、少額から始められる不動産投資が注目されています。
不動産投資の基本やメリット・デメリットを知りたい方は、MANEMOの記事を参考にしてみてください。