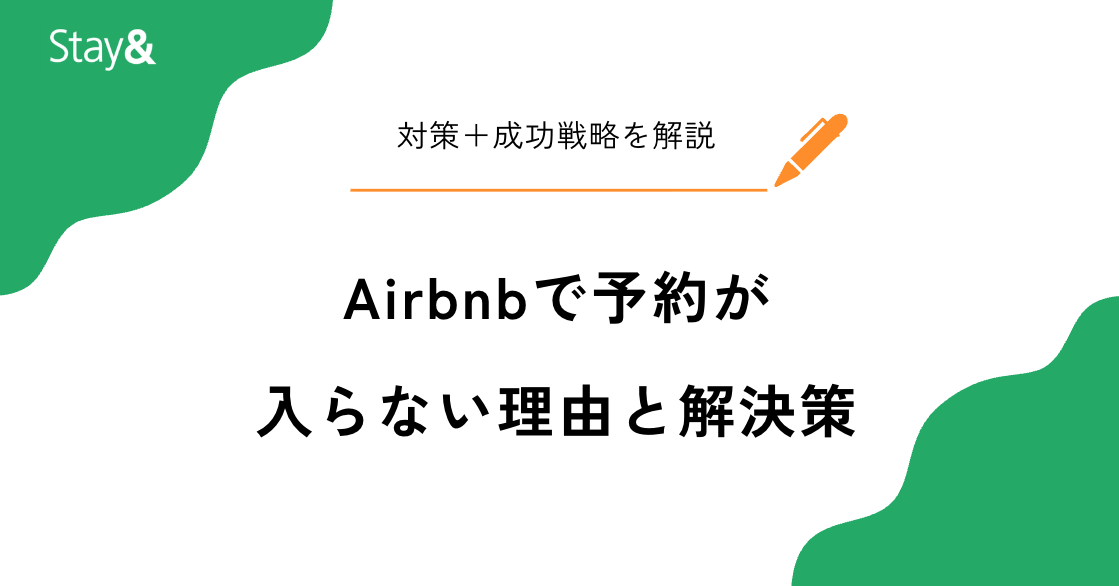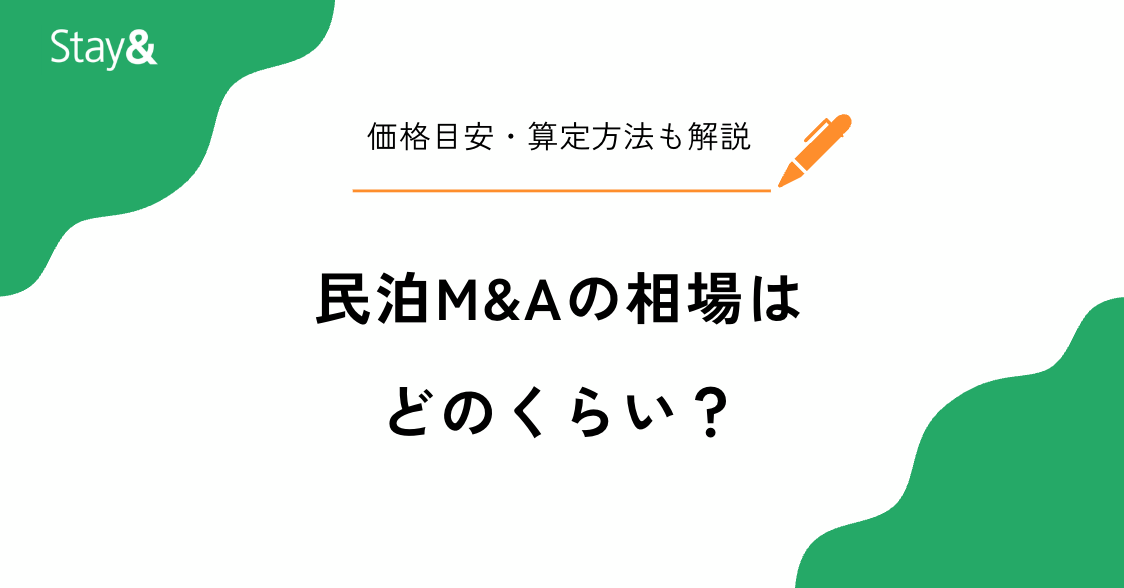【自宅や空き部屋で】民泊を始める方法!開業の流れや費用など解説
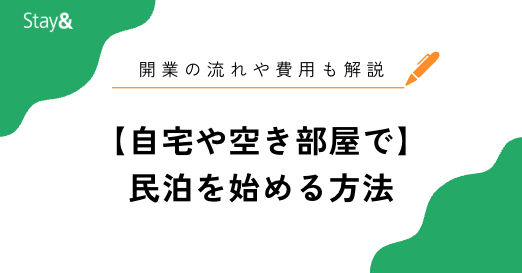
「使っていない自宅の一室や空き部屋を収益化したい」そんな方に注目されているのが、自宅を活用した民泊です。
Airbnbなどの予約サイトを使えば、特別な資格がなくても民泊を始めることができます。
実際、都市部から地方の空き家まで、多くの自宅が宿泊施設として生まれ変わり、副収入を得ている事例も多数あります。
とはいえ、「本当に自宅でできるの?」「手続きや費用はどれくらい?」「近所迷惑にならない?」といった疑問や不安もあるでしょう。
そこで本記事では、自宅で民泊を始めるための準備から、必要な手続き、初期費用、収益の目安、トラブル対策までを初心者向けにわかりやすく解説します。

監修者:井上 咲
保有資格:宅地建物取引士
ビルオーナー業として契約業務や商業ビルの買収・管理を経験。現在は専業ライターとして、不動産の専門知識を活かし複数の不動産メディアで執筆・監修を担当。
目次
自宅を民泊にするのは本当に可能?
「自宅を民泊にして副収入を得たい」と考える人は増えていますが、本当に自宅で民泊はできるのでしょうか?
結論から言えば、一定の条件を満たせば可能です。ただし、誰でもどんな家でもすぐ始められるわけではありません。
法律や地域の条例、建物の構造、所有形態(持ち家・賃貸など)によって、民泊ができるかどうかが決まります。
また、消防設備の設置や役所への届出も必要です。
この章では、まず自宅での民泊がどういう仕組みで成り立っているのかを、わかりやすく解説していきます。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違い
自宅で民泊を始めるには、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」か「旅館業法」のいずれかを適用する必要があります。
一般的には、年間180日まで営業可能な住宅宿泊事業法が自宅民泊向きです。
一方、旅館業法は365日営業が可能ですが、設備基準や申請のハードルが高め。
自宅を副業として活用するなら、まずは住宅宿泊事業法の届出から始めるのがおすすめです。
家主居住型と不在型の2種類のスタイル
自宅民泊には「家主居住型(ホームステイ型)」と「家主不在型」の2つのスタイルがあります。
家主居住型は、自宅に住みながら一部の部屋を貸す形で、ゲストとの交流が特徴。対面で対応できるためトラブルも防ぎやすいです。
一方、家主不在型は家全体を貸す形式で、相続した空き家や別荘の活用に向いています。
「家主居住型(ホームステイ型)」との主な違いは、消防法に定められたホテルや旅館並みの消防設備の義務化が挙げられます。
非常用照明や火災報知器、誘導灯の設置が求められるケースもあり、初期費用や手続きがやや複雑になります。
どちらも届出方法や必要設備に違いがあるため、事前にスタイルを決めてから準備を始めましょう。
【物件のタイプ別】あなたの自宅で民泊できるかを確認しよう!

自宅で民泊を始めたいと思っても、すべての物件がすぐに利用できるわけではありません。
物件の所有形態や契約内容によっては、そもそも民泊が許可されていない場合もあります。
以下のチェックポイントで、自分の家が民泊に向いているかを確認してみましょう。
自己所有の戸建て:自由度が高く、最も始めやすい
自己所有の一戸建ては、民泊を始めるうえで最も始めやすい物件です。
マンションのような管理規約や共有部分の制約がなく、自分の裁量で設備や間取りを柔軟に変更できるため、運営の自由度が高いのが大きなメリットです。
ただし、どの地域でも自由に営業できるわけではありません。
自治体によっては民泊に関する条例が定められており、特に都市部では営業可能な日数や区域に制限がある場合もあります。
始める前には、必ず地域のルールを確認し、法令を遵守した運営が必要です。
自己所有のマンション:管理規約と住民トラブルに注意
自己所有のマンションでも、民泊を行うことは可能です。
建物自体の立地や設備が整っていれば、宿泊者にとっても快適な滞在先となり得ます。
一方で、多くのマンションでは管理規約で「民泊禁止」または「用途制限」が設けられており、実際に運営を始めるには管理組合の承認が必要になるケースがほとんどです。
さらに、共用部分の使い方や騒音トラブルをめぐって他の居住者とのトラブルに発展するリスクもあります。
民泊を検討する場合は、事前に管理規約を確認し、周囲の理解を得ることが欠かせません。
賃貸物件:もっとも一般的だが、大家の許可が絶対条件
民泊を始めるうえで、賃貸物件を使うケースは実はもっとも一般的です。
初期費用を抑えて始められ、自宅とは別に運営することで生活への影響も少ないため、多くの人がこのパターンを検討します。
しかし、最大のハードルは「大家(オーナー)の許可を得ること」です。
通常の賃貸借契約では、第三者への又貸し(転貸)は禁止されているため、無断で民泊を始めると契約違反となり、強制退去や損害賠償のリスクがあります。
たとえ口頭で了承を得た場合でも、契約書への明記や自治体への届出など、適切な手続きを踏む必要があります。
【初心者向け】自宅民泊の始め方|7ステップでわかる開業フロー

自宅で民泊を始めるには、ただ部屋を貸すだけではNG。
法律に則った手続きや設備の整備、届け出が必要です。
以下の7ステップに沿って進めれば、初心者でもスムーズに開業できます。
STEP1:自治体・消防・保健所に事前相談
民泊を始めるには、各種の届け出や関係機関への相談が必要です。
下記のように、確認すべき法律とポイントを事前に把握しておきましょう。
| 確認すべき項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 住宅宿泊事業法 or 旅館業法 | 「家主居住型」か「家主不在型」かを決め、それに応じて制度を選択 |
| 消防法 | 消火器や火災報知器、避難経路(非常口)の設置が必要か確認 |
| 建築基準法 | 既存の建物用途を「宿泊施設」に変更する必要があるかチェック |
| 税金関連 | 所得税・住民税・固定資産税・事業税などについて専門家へ相談 |
民泊に関するルールや運用基準は、地域によって細かく異なります。
そのため、まずは管轄の自治体や消防署、保健所に相談するのがスムーズです。
また、制度全体がわかりにくい場合は、国土交通省の「民泊制度コールセンター」や、各自治体の相談窓口も活用できます。
STEP2:設備(台所・浴室・トイレなど)を基準に整える
住宅宿泊事業法では、台所・浴室・トイレ・洗面所などの設備が揃っていることが条件とされています。
古い家の場合は簡単なリフォームが必要になるケースもあります。
ゲストの満足度に直結するため、見た目の清潔感や使いやすさにも配慮しましょう。
参考サイト:住宅宿泊事業法
STEP3:消防法令適合通知書を取得
消防設備の基準を満たしているかを確認する「消防法令適合通知書」の取得も重要です。
消火器や火災報知器の設置、避難経路の確保などが求められます。
地域の消防署で点検を依頼し、安全面で問題がないかをチェックしてもらいましょう。
STEP4:住宅宿泊事業の届出を行う
届出には、物件の図面、登記事項証明書、住民同意書など複数の書類が必要です。
手続きはオンラインでも可能ですが、書類の不備があると差し戻されるため注意が必要です。
不安な場合は行政書士や代行業者のサポートも検討しましょう。
STEP5:家具・寝具・アメニティなどを用意
ゲストが快適に過ごせるように、ベッドや布団、テーブル、椅子などの家具を整えましょう。
さらに、シャンプー、タオル、歯ブラシなどのアメニティも重要。
女性や外国人観光客のニーズを想定して、細やかな気配りがポイントです。
STEP6:予約サイト(Airbnbなど)に登録
AirbnbやBooking.comなどの予約サイトに物件情報を登録します。
物件の魅力を伝える写真やキャッチコピーが集客の決め手になります。
周辺情報やアクセス方法も記載し、初めてのゲストでも安心して予約できるページに仕上げましょう。
STEP7:営業開始&定期報告の準備
届出が完了したら営業スタート。
ただし、運営後も2か月ごとの定期報告(宿泊者数・宿泊日数・苦情の有無など)が必要です。
報告を怠ると罰則の対象になるため、スケジュール管理や記録の保存を徹底しましょう。
どれくらいお金がかかる?自宅民泊の初期費用と内訳

自宅民泊は比較的低コストで始められる副業ですが、完全にゼロから始められるわけではありません。
初期費用の内訳を理解することで、無駄なく効率的に準備できます。
以下では、リフォームや設備投資、手続き費用、備品購入など、実際にかかるコストを解説します。
リフォームや設備投資の目安
民泊では、水回り(浴室・トイレ・キッチンなど)のリフォームや、老朽化した内装の改修が必要になることがあります。
費用の目安としては以下の通りです。
- 水回りのリフォーム:100〜200万円
- 配管工事:30〜50万円程度
- 壁紙・床の張替えなど軽微な内装:10〜30万円
必要に応じて、スケルトンリフォーム(全面改修)などを行えば、見た目の印象が大きく変わり予約率の向上にもつながります。
関連記事:リフォーム一括見積もり・比較サイトおすすめランキング!最新版|リフォームLabo.
行政手続き・申請代行などの費用感
住宅宿泊事業の届出は無料で行えますが、書類が多く、初心者には少しハードルが高めです。
行政書士などの専門家に代行を依頼すると、3万〜10万円程度が相場です。
また、消防法令適合通知の取得や図面作成、住民への同意書なども手続きに含まれるため、工数と予算の確保をしておきましょう。
詳しくは「民泊の申請代行の費用はいくら?行政書士に依頼するメリットや注意点」の記事をご覧ください。
家具・アメニティ・清掃用品の準備費
宿泊者が快適に過ごすための備品類も必要です。
最低限の準備費用は以下のとおりです。
- ベッドや寝具一式:3〜5万円
- テーブル・椅子・収納など:2〜5万円
- アメニティ(歯ブラシ、シャンプーなど):初期1〜2万円+消耗品補充
- 掃除道具や除菌スプレー:1万円前後
インテリアにこだわることで、写真映えし、予約率を大きく高められます。
なお、初期費用について詳しく知りたい方は「民泊を始める際の初期費用はいくらくらい?【リアルな金額を公開】」の記事を合わせてご覧ください。
実際いくら稼げる?自宅民泊の収益モデル
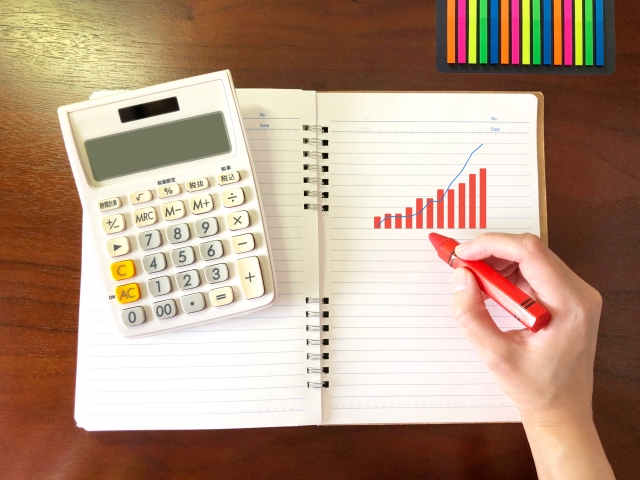
自宅民泊は空き部屋を活用することで安定した副収入を得られる可能性があります。
部屋数や宿泊単価、稼働率に応じて収入は大きく変動しますが、うまく運営すれば月数万円〜十数万円の利益も十分に見込めます。
1部屋からでも月5〜10万円の実例も
自宅の一室を民泊として貸し出すだけでも、場所や設備によっては月5万〜10万円の収入を得ている事例があります。
特に観光地や駅近など立地が良い場合、少ない日数でも高稼働率が期待でき、副業レベルとしては十分魅力的な収益が得られます。
宿泊単価×稼働率で見える収益シミュレーション
収益は以下のシンプルな式で計算できます。
宿泊単価 × 稼働日数 × 稼働率 = 月間収益
たとえば、1泊8,000円の部屋を月15日稼働(稼働率50%)させた場合の収益は「8,000円 × 15日 = 120,000円」です。
季節やイベント時期に応じて価格を調整することで、収益を最適化できます。
副業レベルでの現実的な収支イメージ
初期費用が約20〜50万円、月の維持費(清掃費・消耗品・光熱費など)が1〜2万円だと仮定した場合、月5万円の利益を出すには8〜10万円の売上が必要になります。
副業としての収支バランスを考えると、年間で数十万円の黒字化も十分現実的。安定した副収入源として魅力があります。
自宅民泊を始めるメリット

ここでは、自宅民泊を始めるメリットを詳しく見ていきましょう。
初期費用が少なく始めやすい
民泊を新たな事業として始める場合、物件購入や内装工事などに多額の費用がかかりますが、自宅を使うならそのコストを大きく削減できます。
既に住んでいる家の空き部屋を使えば、初期費用は数万円〜数十万円程度に抑えられることが多く、資金面のハードルが低い点が大きな魅力です。
遊休スペースを収益化できる
普段使っていない空き部屋や、子どもが独立して使わなくなった部屋を有効活用できるのも大きな利点です。
「ただの空き部屋」が旅行者にとっては魅力的な宿泊施設になることも。
使わないスペースに価値を生み出す手段として、民泊は非常に合理的です。
副業として柔軟に運営しやすい
自宅での民泊は、週末や繁忙期など、自分の都合に合わせて柔軟に運営できるのが大きなメリットです。
管理や清掃を自分で行えば、費用を抑えて収益を上げることもできます。
また、予約の受付を自分で調整できるプラットフォームを使えば、本業と両立しながら無理なく続けられます。
資産価値の維持・向上にもつながる
空き家や使わない部屋を放置しておくと、老朽化や傷みが進みやすくなります。
民泊として活用すれば、定期的な清掃や点検が入り、結果として物件の管理状態が良好に保たれます。
収益を得るだけでなく、資産価値の維持や向上にもつながるのは大きなメリットです。
地方や空き家でも活用できる
都市部だけでなく、地方や郊外の空き家でも観光資源やイベント施設があれば十分ニーズがあります。
特に外国人観光客や長期滞在者には、静かで落ち着いた場所が好まれることも。
立地に不安があっても、ローカルな魅力を打ち出せば収益化の可能性は十分にあります。
自宅民泊を始めるデメリット・注意点

民泊はメリットが多い一方で、事前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
以下に代表的なリスクや課題を紹介します。
近隣トラブルや騒音リスクがある
自宅で民泊を行うと、ゲストの騒音や出入りが原因で近隣住民とのトラブルになる可能性があります。
特に集合住宅では、住民の理解と協力が不可欠。
案内文やルールの掲示、チェックイン時の説明など、マナーへの配慮を徹底することが重要です。
盗難・破損などのリスク対策が必要
自宅に他人を泊める以上、家具や設備の破損、貴重品の盗難などのリスクもゼロではありません。
高価なものは部屋に置かない、監視カメラを設置する、民泊保険に加入するなど、あらかじめ対策を講じておくことが大切です。
トラブル対応マニュアルを用意しておくのも有効です。
住宅ローンや保険に影響する可能性
住宅ローンの契約内容によっては、民泊運営を禁止している場合があります。
また、住宅用の火災保険が民泊には適用されないケースもあるため、事前に契約書や保険の内容をしっかり確認しましょう。
専用の民泊保険に切り替えることで、万が一の備えにもなります。
年間180日などの営業制限がある
住宅宿泊事業法の下では、民泊として運営できるのは年間180日までと定められています。
これを超える営業を行うには、旅館業法の許可が必要になるため、収益計画はこの上限を踏まえて立てる必要があります。
短期集中型の運営戦略を考えることがカギです。
管理や清掃の手間がかかる
ゲストの入れ替わりのたびに清掃・シーツ交換などが必要になり、想像以上に手間がかかることもあります。
自分で対応するのが難しい場合は、清掃代行サービスや鍵の受け渡し代行などの外部委託も検討しましょう。
手間を減らす工夫が長期的な運営のカギとなります。
民泊運営で起きやすいトラブルとその対策
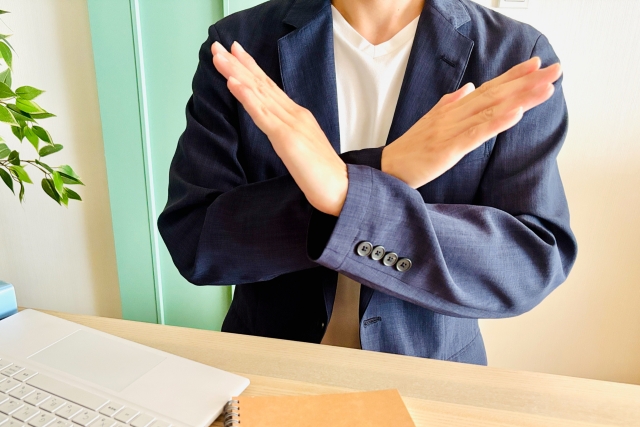
自宅民泊は魅力的な副業ですが、運営にはトラブルがつきものです。
特に、近隣住民との関係や宿泊者による問題、保険・法律の知識不足が原因になるケースが多いです。
事前にリスクと対策を知っておくことで、安心して運営を続けることができます。
近隣住民との騒音・迷惑トラブル
民泊で最も多いトラブルは「騒音」と「マナー違反」による近隣住民との問題です。
対策としては、ゲストに事前にルールを伝える「ハウスルールの掲示」や、ゴミ出し・騒音禁止の案内を多言語で設置することが効果的です。
無人運営の場合でも、緊急連絡先の表示や、管理業者によるサポート体制を整えると安心です。
盗難・プライバシー・苦情への備え
家主居住型では、プライバシーの配慮が非常に重要です。
ゲスト用のスペースとプライベートスペースをしっかり分け、貴重品は施錠・管理しましょう。
盗難や破損に備えては、Airbnbなどの補償制度や「民泊保険」への加入がおすすめ。
苦情が発生した場合に備えて、記録の保存と対応マニュアルを準備しておくとスムーズです。
住宅ローン・保険・火災対策との関係性
住宅ローンを利用している家では、民泊運営が「事業」とみなされ、ローン契約違反になる場合があります。事前に金融機関の承諾を得ることが重要です。
また、通常の火災保険では民泊は対象外のこともあるため、民泊対応の火災保険に切り替えると安心です。
万一のリスクに備え、契約内容の再確認を忘れずに行いましょう。
よくある質問|自宅民泊を始める前のQ&A

Q. 自宅の一室だけでも民泊はできますか?
はい、可能です。
自宅の一部を使う「家主居住型(ホームステイ型)」は、住宅宿泊事業法に基づいて営業できます。
ただし、年間営業日数の制限(180日)や消防設備の設置が必要です。
Q. Airbnbに登録すればすぐ始められますか?
Airbnbの登録だけでは、民泊をすぐに始めることはできません。
運営には、住宅宿泊事業の届出や消防設備の設置、管理規約の確認など、複数の法的手続きが必要です。
届け出番号が発行されてからでないと、Airbnbでも物件を公開・運営することはできません。
Q. マンションでも民泊できますか?
マンションでの民泊運営は、管理規約や住民合意が必要となり、戸建てよりもハードルが高いです。
詳細は以下の記事で詳しく解説していますので、マンション所有者の方はそちらをご覧ください。
まとめ|自宅の空き部屋が収益になる時代。できる範囲から始めてみよう
自宅民泊は、使っていない部屋を活用して副収入を得られる、新しい時代の賢い資産活用方法です。
初期費用も比較的抑えられ、片手間での運営も可能です。
とはいえ、法的手続きやトラブル対策は避けて通れません。
まずは小さく始めて、経験を積みながら運営スタイルを確立していくのがおすすめです。
自分の生活に合った形で、安心・安全な民泊ライフをスタートさせましょう。